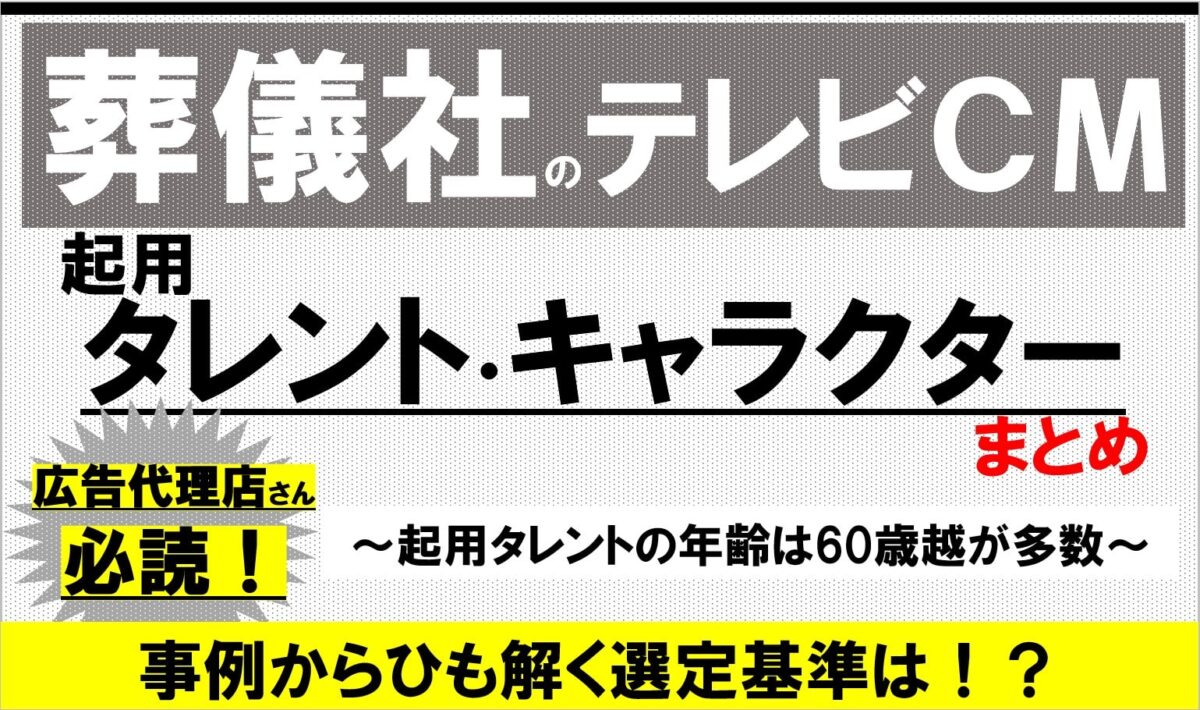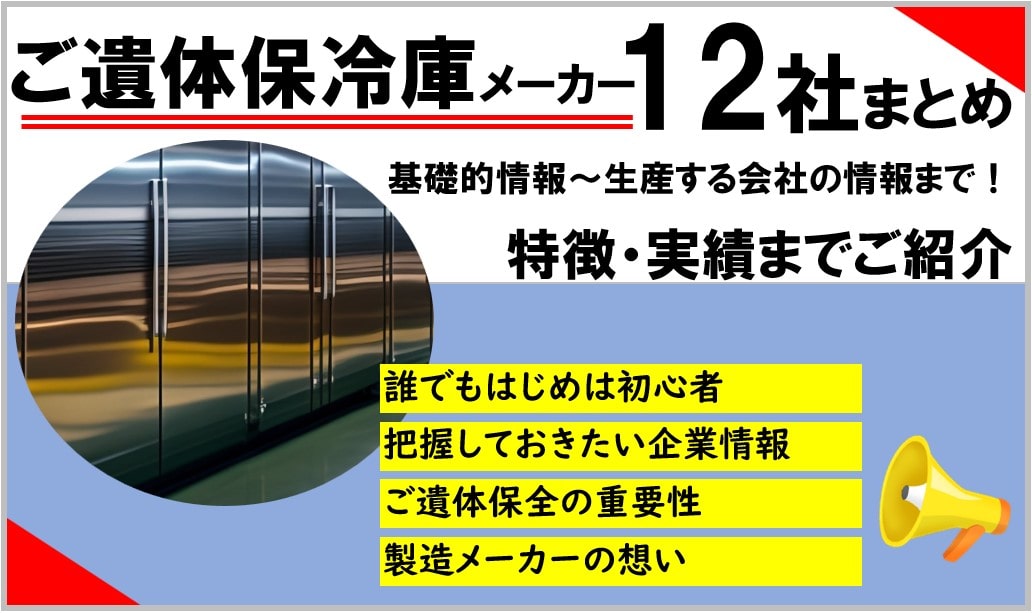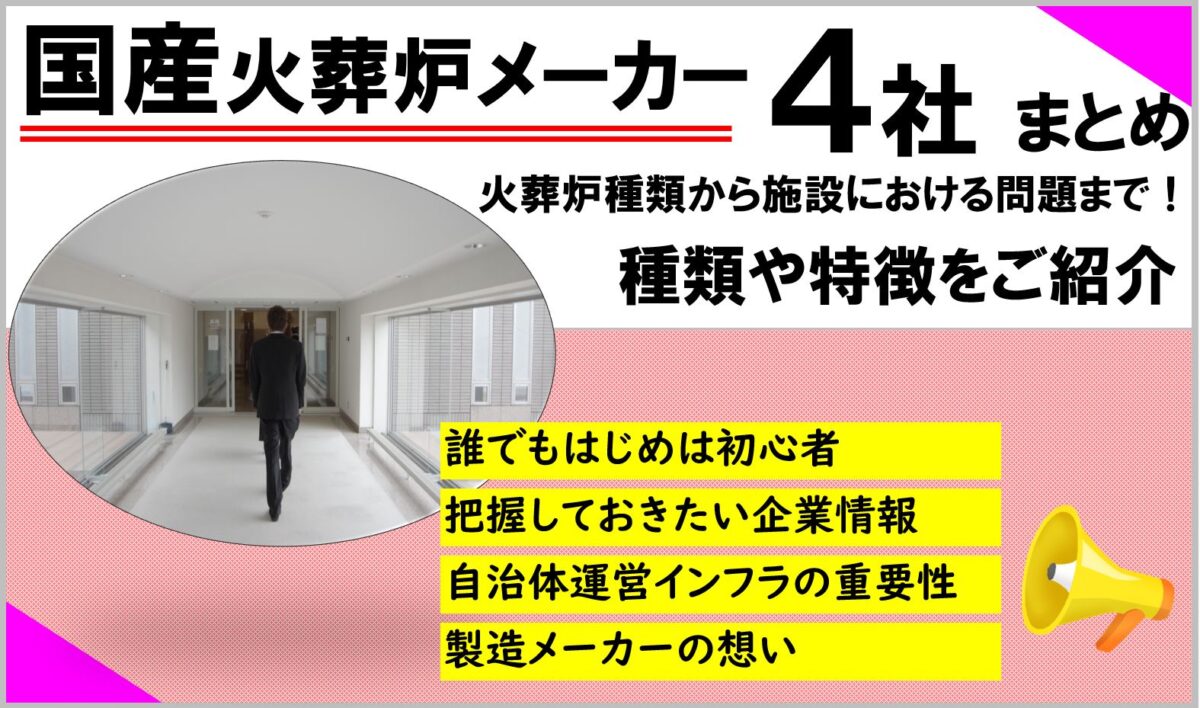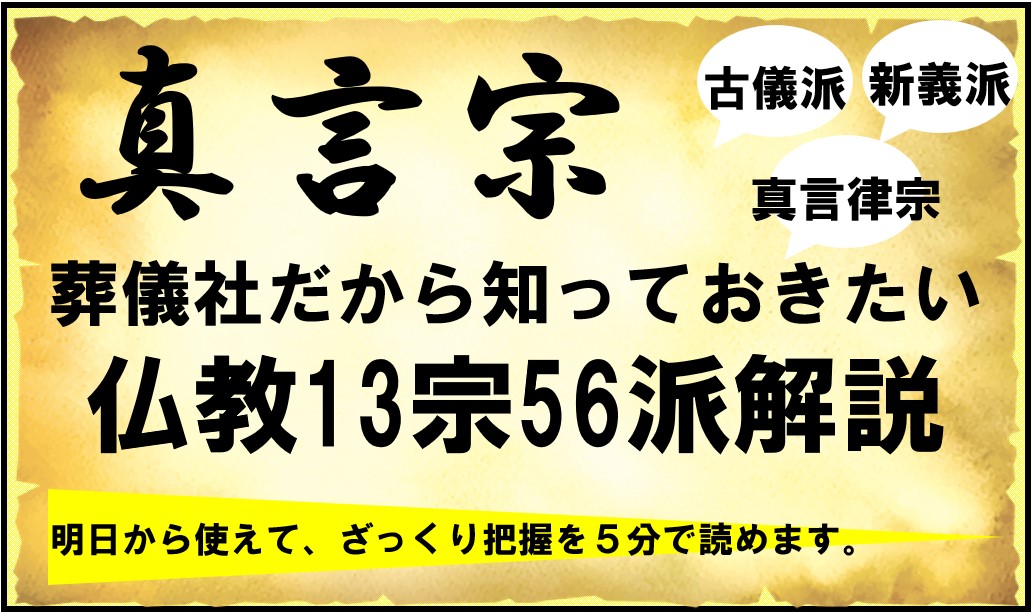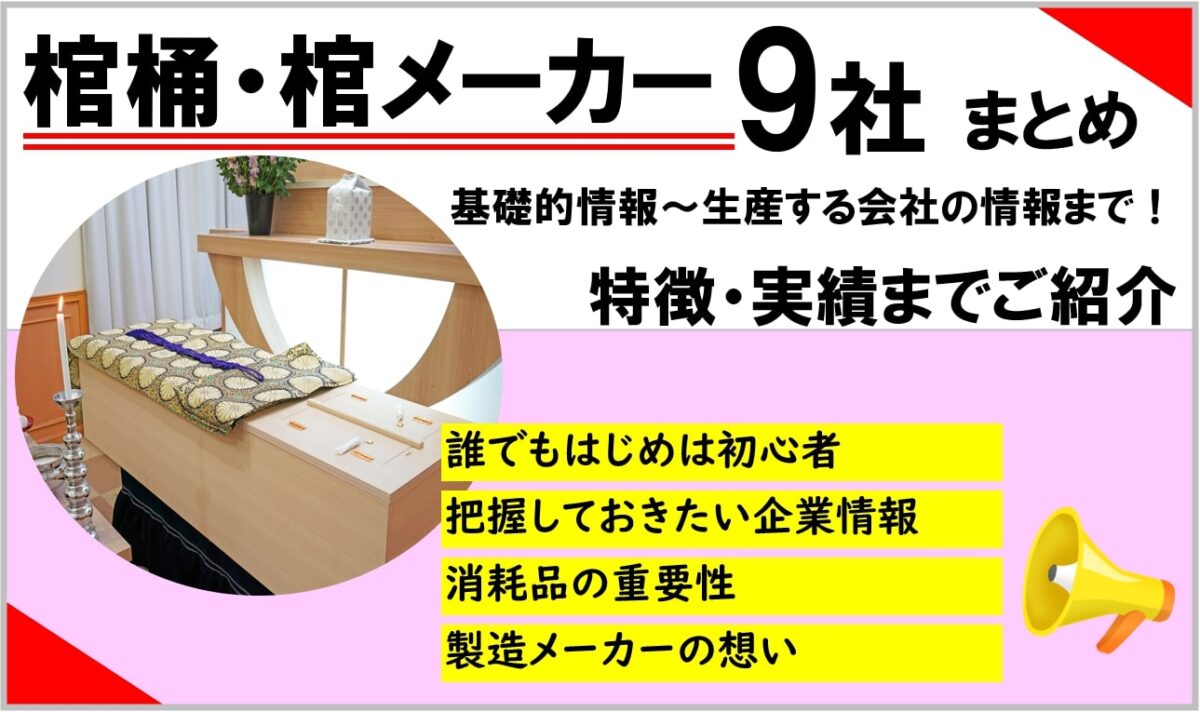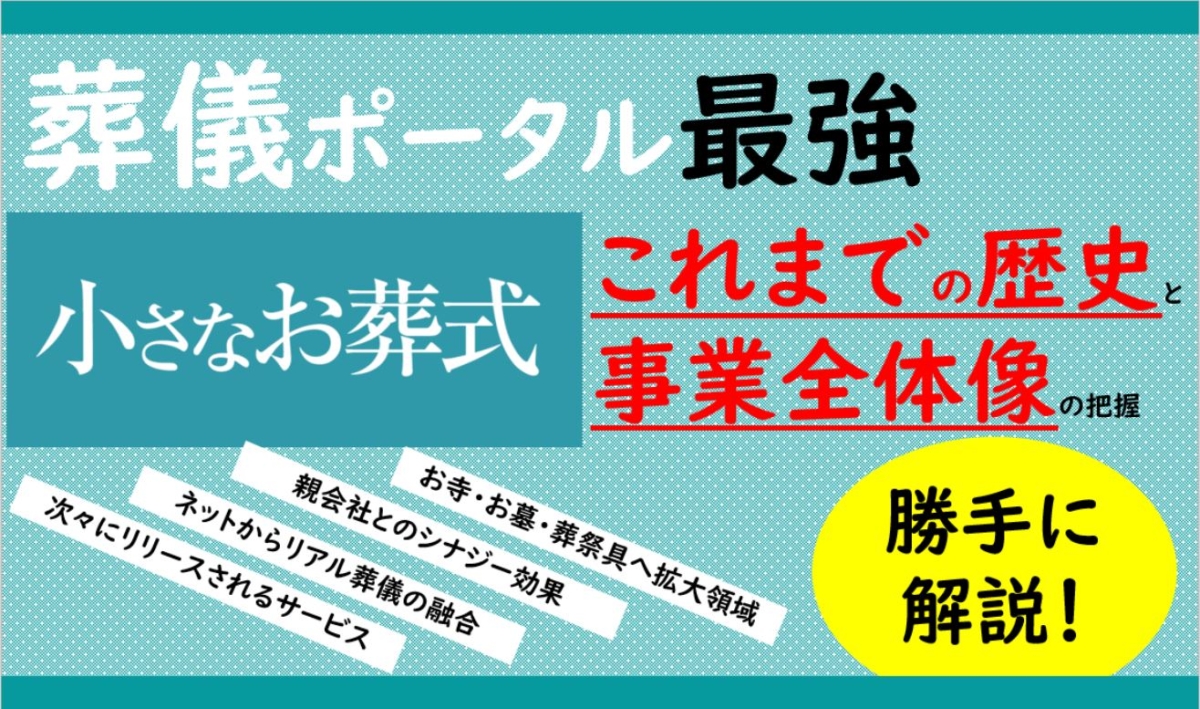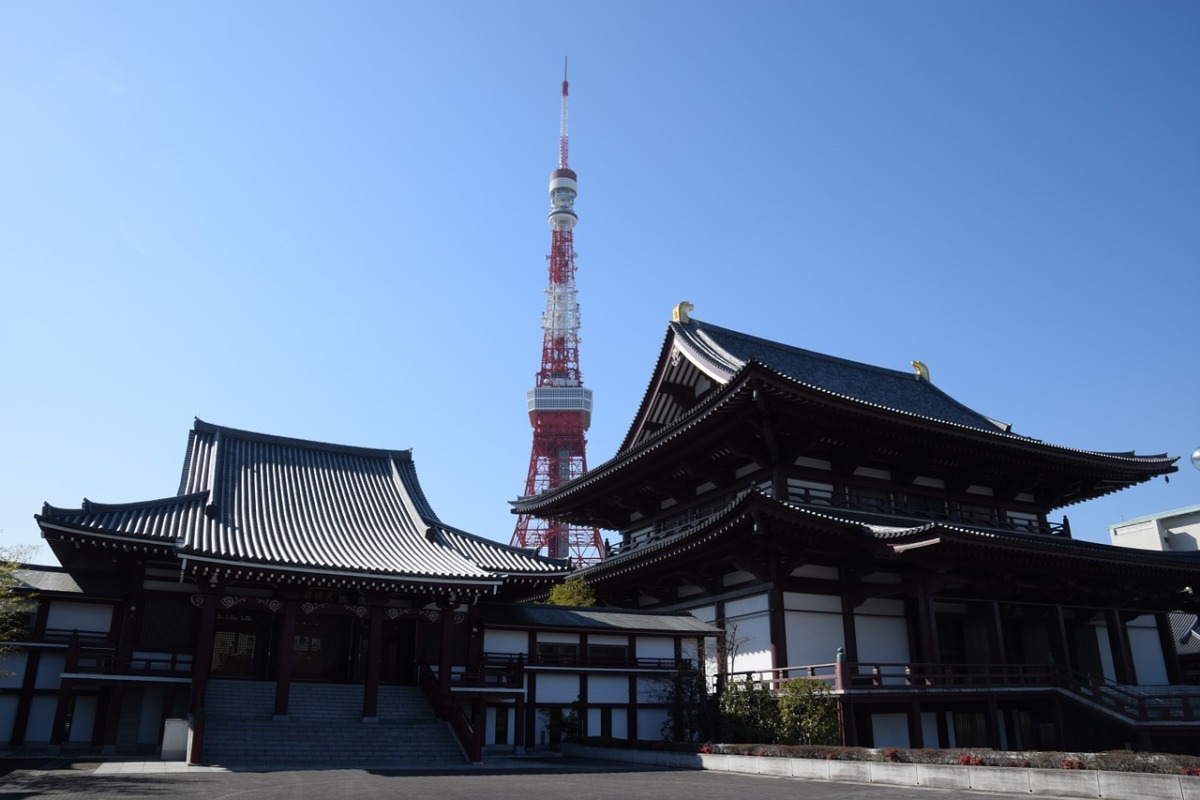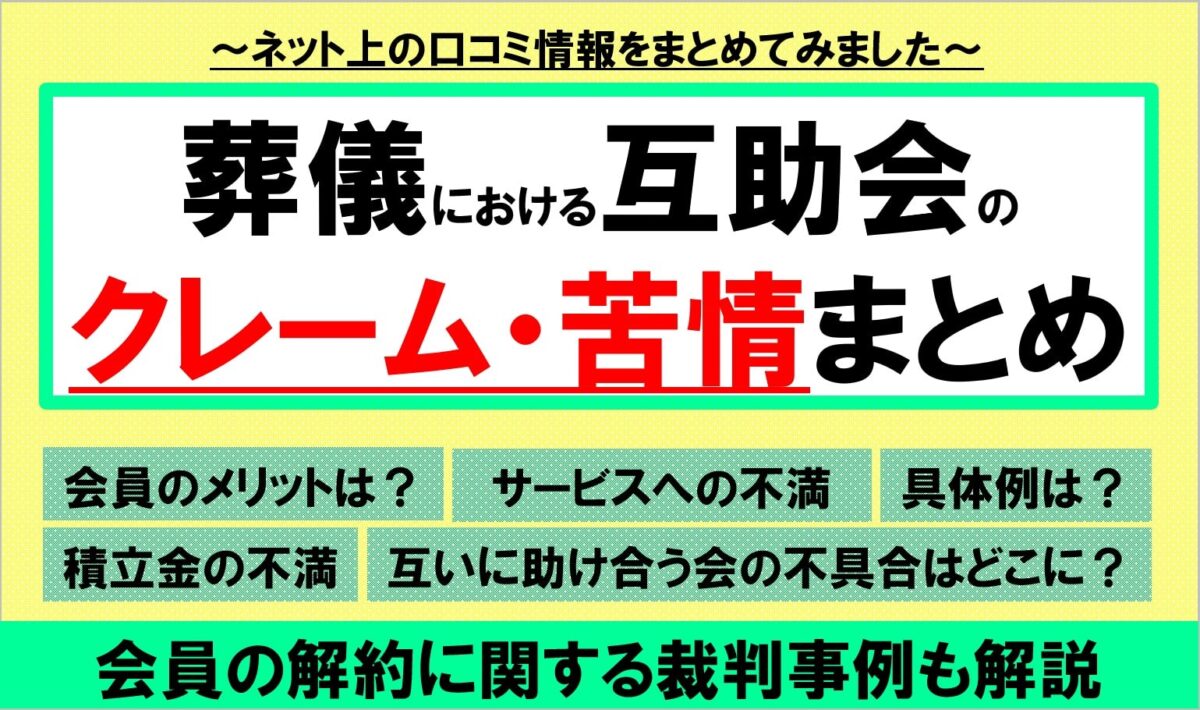-

空き家戸建て活用の「空き家リノベラボ」、相続空き家の増加に伴い、空き家活用の無料相談サービスを拡大。公式WEBサイトを空き家オーナー向けにリニューアル~Japan. asset management~一般公開
Japan. asset management株式会社は、空き家活用のプラットフォーム「空き家リノベラボ」を空き家オーナー向けの公式WEBサイトとしてリニューアル公開しました。空き家... -

空き家対策の推進に関する協定を締結 豊中市空き家相談窓口開設へ~豊中市~一般公開
豊中市は、一般社団法人既存住宅・空家プロデュース協会と「豊中市空き家対策の推進に関する協定」を締結したことを発表しました。これにより、空き家に関する相談窓口... -

空き家対策の推進に関して「大分県竹田市」と連携協定を締結いたしました。~AlbaLink~一般公開
株式会社AlbaLinkは、大分県竹田市と空き家対策の推進に関する連携協定を締結したことを発表しました。これにより、AlbaLinkの空き家の買取・再生に関する経験を活かし... -

空き家対策の推進に関して「千葉県白子町」と連携協定を締結いたしました。~AlbaLink~一般公開
株式会社AlbaLinkは、千葉県白子町と空き家対策の推進に関する連携協定を締結したことを発表しました。AlbaLinkが持つ、空き家の買取・再生に関する経験を活かし、白子... -

空き家対策の推進に関して「千葉県市原市」と連携協定を締結いたしました。~AlbaLink~一般公開
株式会社AlbaLinkは、千葉県市原市と市場性の低い空き家の流通や利活用など、空き家対策促進に関する連携協定を締結しました。本協定により、同社は空き家所有者の悩み... -

空き家対策の推進に関して「兵庫県神河町」と連携協定を締結いたしました。~AlbaLink~一般公開
株式会社AlbaLinkは、兵庫県神河町と空き家に関する連携協定を締結したことを発表しました。神河町は、かねてより空き家の管理と活用促進に課題を抱えており、本協定に... -

空き家問題の早急な解決に向けて、空き家と解体工事のプロフェッショナルを育成する認定資格制度『解体工事プランナー』がスタート。 ~タミヤホーム~一般公開
首都圏を中心に解体工事を手掛けるタミヤホームは、空き家及び解体工事のプロフェッショナル育成を目的とした認定資格制度「解体工事プランナー」の運用開始を発表しま... -

空き家問題のスペシャリストが集合 空き家流通促進機構による「マイナス不動産・建築のポジティブ化」シンポジウムが開催一般公開
一般社団法人 全国空き家流通促進機構 一般社団法人全国空き家流通促進機構(田中裕治代表理事)は、9月21日(土)に東京・渋谷で「【売れない空き家空き地をどう活かす... -

空き家問題に新たな選択肢!地域密着型AI『空き家未来AIナビ』で手軽に相談~いんしゅう鹿野まちづくり協議会~一般公開
NPO法人いんしゅう鹿野まちづくり協議会は、地域密着型AI「空き家未来AIナビ」を開発しました。増え続ける空き家問題に対応するため、AIチャットボットを活用した相談窓... -

空き家問題に一石【解体事故も無くすサービス】解体業者紹介サービス「JOBJIN」~伊藤商店~一般公開
株式会社伊藤商店は、優良解体業者を紹介するサービス「JOBJIN」の紹介手数料を完全無料化したことを発表しました。仲介事業者を利用した場合の手数料が解体費用の負担... -

空き家事業を展開するジェクトワン、埼玉県蕨市、蕨商工会議所及び埼玉りそな銀行と「空き店舗等の有効活用等の促進に関する協定」を締結~ジェクトワン~一般公開
シームレスな4者連携により蕨市内商店街の空き店舗の再生と地域経済の活性化を目指す 株式会社ジェクトワン 画像左から)蕨商工会議所 会頭 牛窪 啓詞、蕨市 市長 ... -

空き家を活かした社会問題解決のため株式会社VIDA Corporationと資本業務提携いたしました。~マークス不動産~一般公開
マークス不動産と株式会社VIDA Corporationは、資本業務提携契約を締結することを発表しました。これにより、両社の事業が組み合わせ、空き家問題の解決や社会福祉問題...