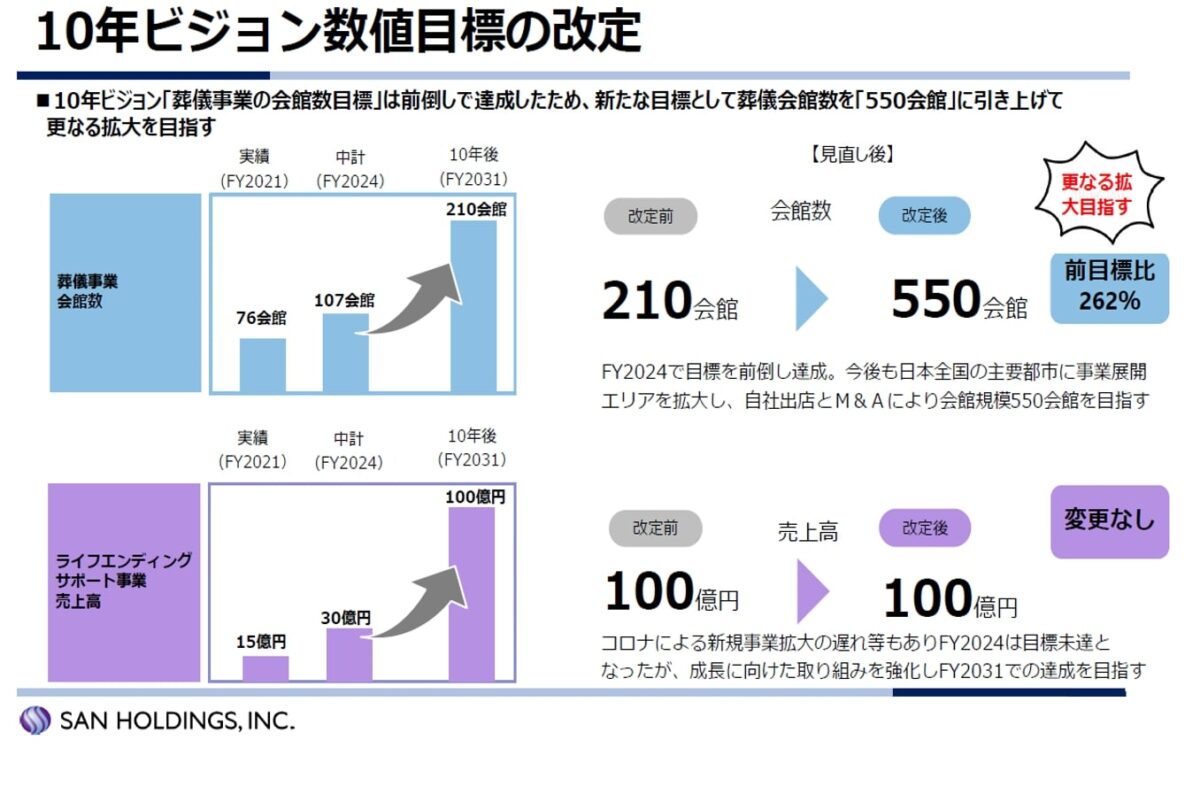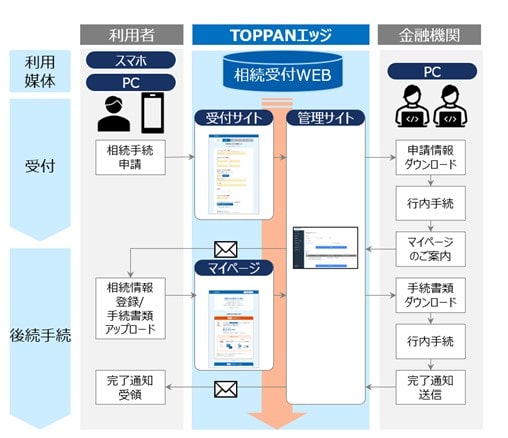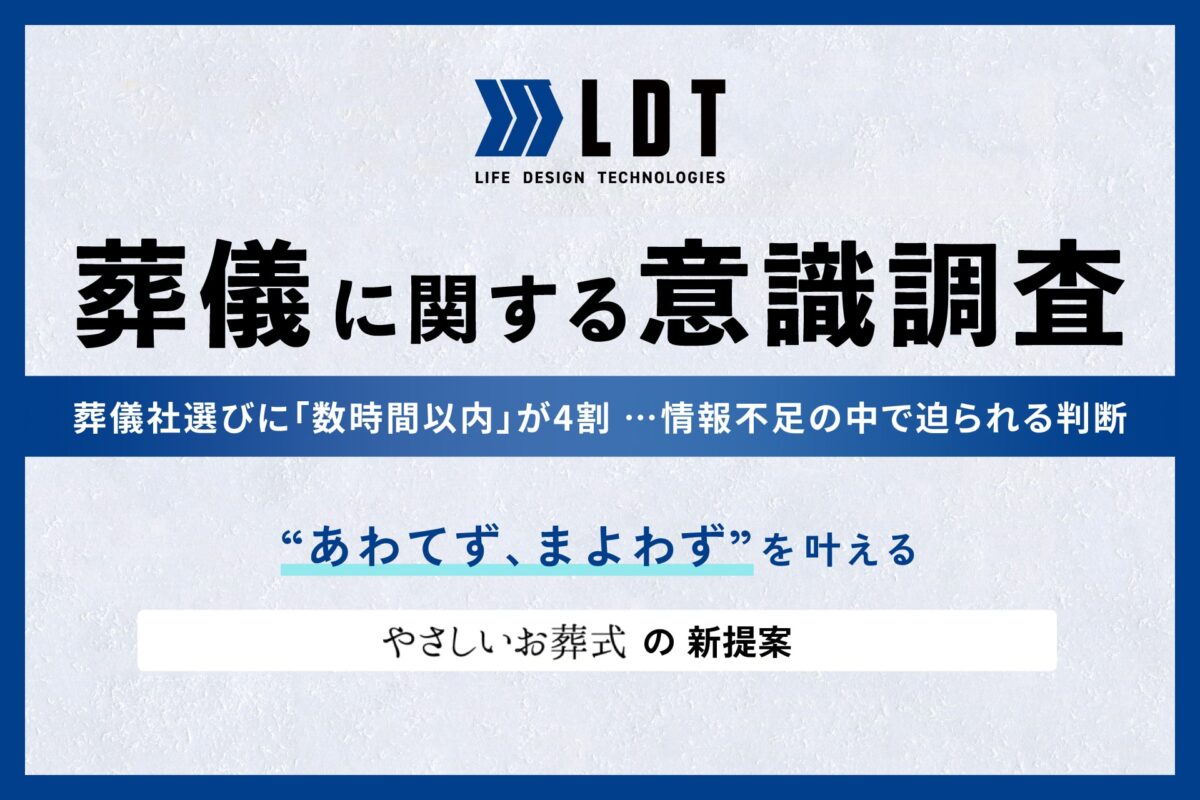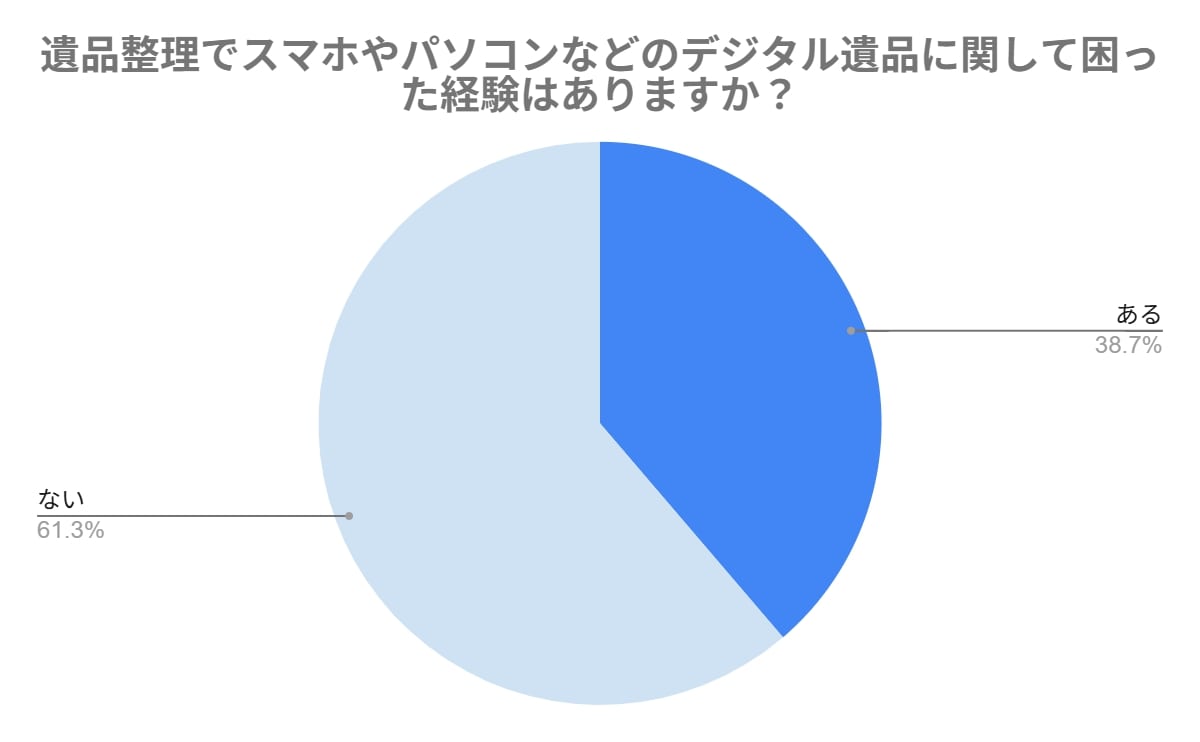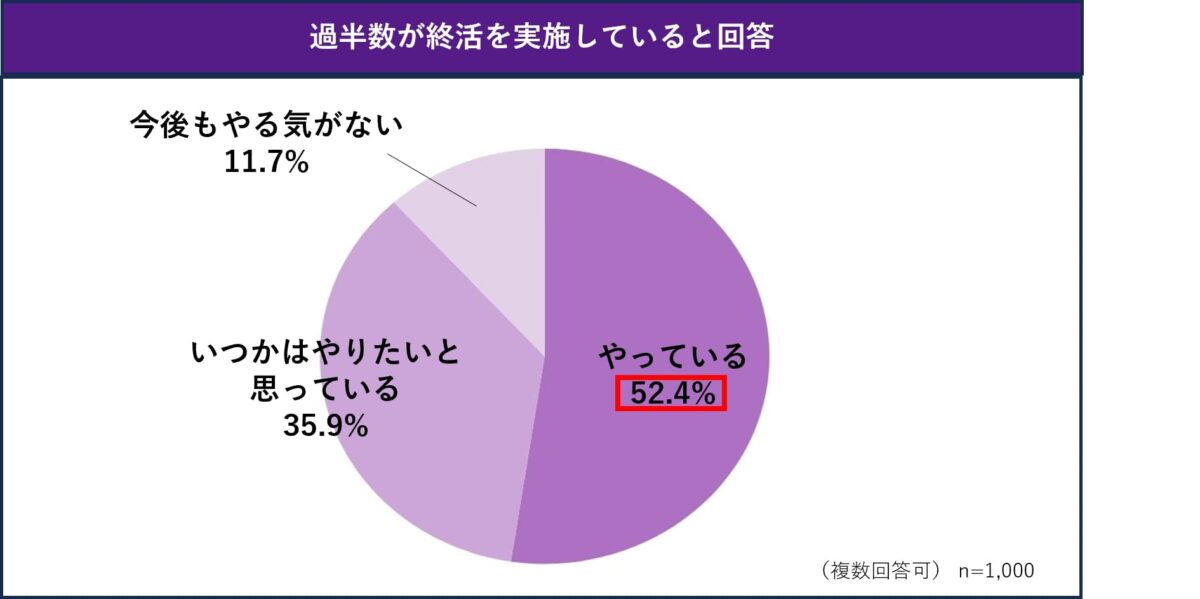葬送の原点を現代社会のなかで問うてみよう。
データは最新データに基づいている。
ある病院の改革
今、自宅で死亡する人は13%前後。残りは病院や施設である。
1955(昭和30)年には自宅での死亡が76.9%と多く、病院等が15.4%と少数であった。
1972(昭和47)年に自宅死亡が49.2%と半数を割った。
それが今や2017(平成29)年時点では自宅が13.2%、病院等が74.8%、高齢者施設等が10%となっている。
病院等(病院+診療所)死の割合が最も多かったのは2005(平成17)年で82.4%。
今その減少分を補い顕著に増加しているのが介護老人保健施設、老人ホーム等の高齢者施設等死で10%(2005年には2.8%にすぎなかった)。
戦後、病院での死者の扱われ方には一つの定型的なイメージがあった。
死亡し、死後の処置を施された遺体は、顔に白い布を被されてストレッチャーに乗せられ、急いで地下の薄暗い霊安室に移され、そこに呼ばれた葬祭業者の手で病院の裏手に停められたバン型霊柩車に乗せられ走り去るように自宅に運ばれた。昼間も深夜も。
当時の病院側の理屈としては、入院患者は治療して回復して退院することが前提である。
そうした患者に死体を見せると患者の治ろうとする意欲を削ぐ。
だからできるだけ人目を避け、とりわけ患者の目に入れないようにしなければならない。
病室から急いで安置室に運ばれた。
しかし患者は知っていた。
いくら治療しても治らない病気があること、しかし、死亡した途端に、病院にもあってはならない存在であるかのように扱われることを。
それが自分の死の場合も同様なのであろう、とばくぜんと感じていた。
ある地方の老人病院の看護師たちは、こうした医療現場の死者への対応に大きな疑問を抱くようになっていた。
いのちを大切にするのであるならば、たとえ亡くなったとはいえ死者は尊厳をもって扱われるべきではないか。
医師に比べると看護師は患者の家族と付き合うことが多い。
患者の家族は患者が死亡した瞬間から、病院にいてはならない存在かのように扱われ、追われるように出て行くことへの不満、怒りがあることを知っていた。
家族にとっては、たとえ死んでも家族なのである。
だが、病院では生きている患者は大切にされるが、死亡判定と同時に患者はあたかも「モノ」に変わる。
それはおかしいし、医療不信を招いている一因ではないか、と感じていた看護師たちは多かった。
中には、元患者の葬儀に、看護師としてではなく、一個人と列席する人もいる。
病院が新装されるにあたって看護師たちは提案した。
① 霊安室は地下にではなく、病院で最も良い位置に設置されるべきこと。
② 死亡した病院から出る時は、正面玄関から出て、その時手のすいている医師、看護師等の病院関係者はそろって見送るべきこと。
この改革は患者たちに大歓迎された。
「この病院は最後の最後まで患者を大切にしてくれる」と。
すべてのいのちは死すべきものである。
死者の尊厳をしないで「いのちを大切にしている」とは言えないだろう。
死者を暗い地下の霊安室に押し込み、裏手の人目のつかない場所から汚い存在であるこのように追い立てていた病院の治療姿勢は、患者の人間としての尊厳、その生活の質(クオリティ・オブ・ライフ)の向上よりもひたすら生物的な延命を目的としていた、治療の歪みをも反映したものであった。
今では終末期医療(ターミナルケア)の普及もあり、この病院のように、過半数とまではいかないが、少なくない数の病院が死亡した患者の取り扱いを変えている。
死の暗黙の了解
事故や災害を別にして日本人の多くは40年前までは普通に家族を自宅で看取っていた。
それは反面、近代医療のインフラの未整備をも意味していたが、それが当たり前のこととして行われていた。
自宅で死ぬ、ということにおいては死に行く者と看取る者との間に共通のサインがあり、それは伝承されてきた。
その一つが、病人が食べ物を細かくして食べやすくしても、「もう、いい」と食べることを止める時であった。
それが看取る者と終末期にある者の死に対する合意、了解であった。
また、当時は「自宅」のもつ意味が違っていた。
今や単独世帯、高齢者の2人世帯が多く、自宅で看取る態勢が困難である。
今は自宅に充分な看取り手がいない。
ときおり、「家族が介護、看護するのが当たり前」という意見を吐く人がいる。
家族の少数化、高齢化、またかつては80歳を超えて生きる人は少なく、したがって認知症患者も少なかった、という今日との差を知らない戯言である。
ある老人施設では、老人を施設に入れた場合、近親者が見舞いにほとんど来ないケースが3割近くいるという。
入居者が危篤になって連絡しても来ない家族、死亡したと連絡すると「そちら(施設)で葬式やってもらえないのですか」と他人事のように対応するケースすら珍しくない、という。
その近親者にすれば、老人施設に入れた段階で家族であることをやめたのである。
臨終を看取る人がいても1~2人だけというケースが多い。
家族の地方分散化が進んでいて、家族ですら、通夜、葬式に出席するだけで、看取ることがあまりなくなっている。
死を一人称の死(自分の死)、二人称の死(近親者の死)、三人称の死(他人の死)と区分けし、位相に違いがあることを示したのはフランスの哲学者ジャンケレビッチであった。
家族の死という本来は向き合うべき関係にある死も、あたかも三人称の死=他人の死であるかのごとく扱われることが少なくない。
死は、多くの場合、終末期の看取りがあってやってくるものである。
それでもその死の事実が近親者にはなかなか受容することが困難である。
まして災害や事故、突然死に襲われた場合、近親者が半狂乱になっても不思議ではない。
「何事もなく」近親者の死を受け止めるのは達観からではない。
あたかも三人称の死=他人の死であるかのごとく扱われることが少なくないのは、近親者の生死に交錯していないから興味も関心もないのだ。
実際、家族を巡る環境は変わりつつある。
家族内ですら温度差が大きくあるし、死者の最も傍にいるのが血縁者でないケースが増えている。