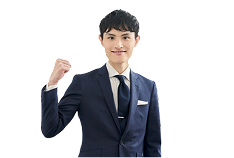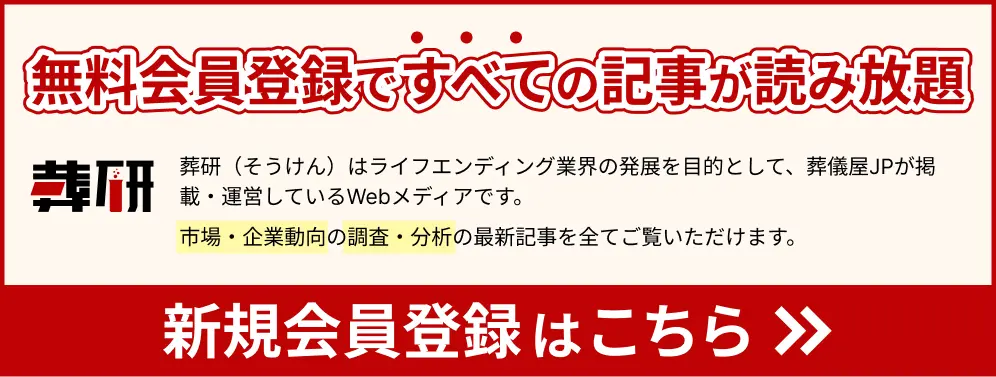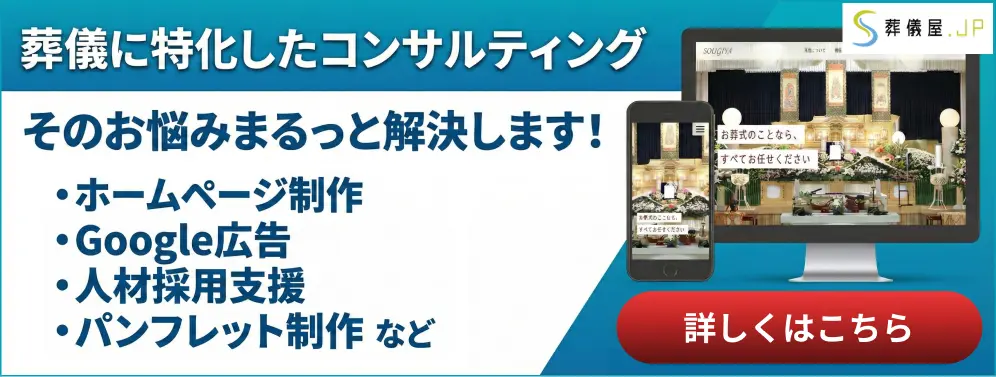高齢社会は、多死社会。いつか迎える親の死。息子である40代のわたしは、その一人でした。また、死はいつか自分にもやってきます。死は遠いことかもしれませんが、死を想うことは、今の生を想うことこと。だからこそ、今、じぶんらしい弔いを考えてみたい。わたしは、自分の母の散骨をタイのメコン川でしました。その時の顛末をこれから3回の連載でお伝えします。筆者は、サラリーマンを辞め、タイの大学で看護を学び、現在は、タイ人の妻とともに東北部にあるウドンタニ県に住んでいます。異国の地で出会った弔いに、母の老いと死に悩む私は多くのことを気づかされました。第1回目の今回は、わたしが経験したタイのお葬式についてです。
お棺を買いに行く。
義母が亡くなった。自宅で亡くなるのが主流のタイでは、葬儀の大部分を自宅で行う。
タイには、日本のような葬儀一式を取り仕切る会社はない。すべて家族、近所の人、お寺と協力してやるのだ。
深夜、葬儀用品を扱う店にお棺を買いに行く。閉じたシャッターを叩くと、すぐに開けてくれた。24時間営業とのこと。お店には、花、ろうそくなどの他に、日本人が想像できないようなものもある。例えば、火葬の時に、お棺にいれる個人があの世で使う生活用品などの紙の模型などだ。
お気に入りの服を着せた義母をお棺に移す。「お母さん、涼しくて、なかなか快適ですよ」まるで、新しい布団を買ってきたように話しかける義兄。冷蔵装置を外付けにできるお棺だったのだ。常夏の国、タイでは必要なものであり、自宅での葬儀が可能なのは、この機械のためだと、後日、タイ人が説明してくれた。
[caption id="" align="aligncenter" width="445"] 葬儀用品店[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="451"]
葬儀用品店[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="451"] お棺7500円くらいから1万5千円まで[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="530"]
お棺7500円くらいから1万5千円まで[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="530"] あの世で住むための家、衛生放送アンテナと車付[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="510"]
あの世で住むための家、衛生放送アンテナと車付[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="510"] あの世で使うお金、冥都銀行[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="523"]
あの世で使うお金、冥都銀行[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="523"] あの世でも身だしなみには注意したい、ひげそり、鼻毛カッター[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="530"]
あの世でも身だしなみには注意したい、ひげそり、鼻毛カッター[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="530"] 義母が眠る[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="526"]
義母が眠る[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="526"] お棺に取りつけられた冷蔵装置[/caption]
お棺に取りつけられた冷蔵装置[/caption]
「まずは、おなかをいっぱいに」
夜明けの台所は、近所の人たちでカオス状態だった。義母のために、葬儀でふるまう料理を作りに来ているのだ。義母は、雑貨屋を切り盛りしていた。コンビニがなかった時代の雑貨屋は、買い物だけではなく、世間話をする場でもあった。この店で最も売れる商品といえば、それは義母のおしゃべりだったのかもしれない。
グリーンカレー、鳥のからあげ、魚の胃袋のスープ、パパイヤサラダ、、。香りが漂ってくる。義母と仲が良いおばさんが「まずは、おなかをいっぱいに」と大きな肉切り包丁を振りおろしながら、私に話してくれた。タイの人たちは、ご飯をみんなで食べることだけでなく、作ることも大好きだ。野菜や肉を切り、炒める、そしてしゃべり、笑い、そして食べる。それは、生前の義母とのいつもの食事の時と同じだ。空腹を感じたわたしは、おばさんたちや妻たちと朝ごはんを食べ始めた。義母にお供えする食事を傍らに置きながら、、。
[caption id="" align="aligncenter" width="387"] グリーンカレー[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="395"]
グリーンカレー[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="395"] 魚の胃袋のスープ[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="386"]
魚の胃袋のスープ[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="386"] いくつも並んだ七輪がフル稼働する[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="388"]
いくつも並んだ七輪がフル稼働する[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="388"] みんなで食べる[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="392"]
みんなで食べる[/caption] [caption id="" align="aligncenter" width="392"] 義母へのお供え[/caption]
義母へのお供え[/caption]