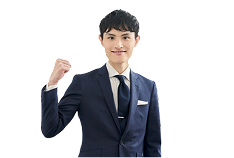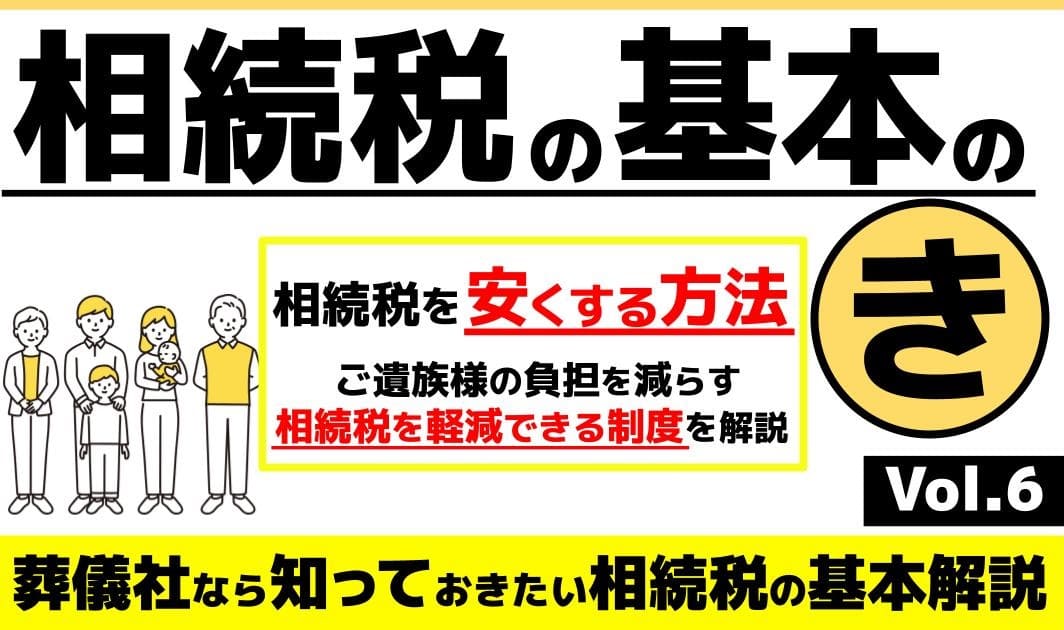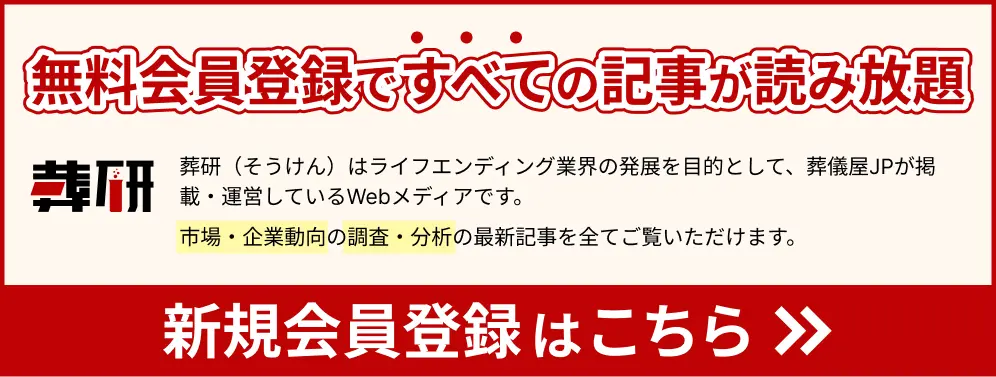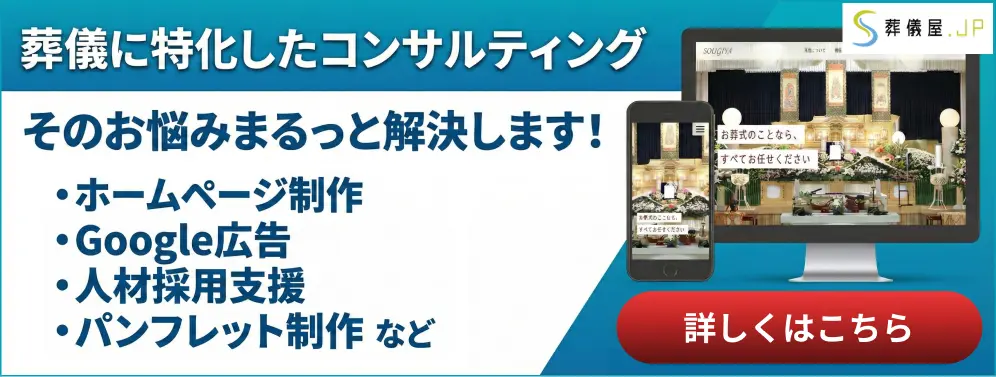相続と向き合うご遺族様にとって、「相続税をどう軽減できるか」は大きな関心事です。葬儀社の皆様は悲しみに寄り添いながらも、時にこうした経済的な不安へのサポートが求められることがあるでしょう。
相続税は多くの方が気にされる問題ですが、実際には適用される制度や特例を知ることで、負担を大幅に軽減できる可能性があります。適切な控除や特例を活用することで、数百万円から場合によっては数千万円もの税負担が軽減されるケースも少なくありません。
この記事では、相続税を安く抑えるための主要な方法を、「控除」「特例」「非課税財産」「債務控除」「生前対策」の5つの視点から整理し、ご遺族様との会話の中で役立つ知識としてご紹介します。悲しみの中にあるご遺族様に少しでも安心を提供できるよう、基本的な対策をわかりやすく解説していきます。
相続税を軽減する制度の全体像

そもそも基礎控除以下なら相続税がかからない
相続税は、故人様から財産を引き継いだ際に課される税金です。しかし、すべての相続に税金がかかるわけではありません。実は、相続税が実際に発生するのは、全体の約8%の相続ケースにすぎないのです。
では、どのような場合に相続税が課税されるのでしょうか。基本的に、故人様が残した財産の合計額から基礎控除額を差し引いた金額に対して相続税がかかります。この基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められます。

例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。つまりこの場合、相続財産の合計が4,800万円以下であれば、相続税を支払う必要はないのです。
そのため、本記事で紹介する相続税を安くする方法は、この基礎控除額よりも高額の財産を相続する場合にのみ必要となります。
なお、相続税の課税対象となる財産には、現金や預貯金はもちろん、不動産、有価証券、生命保険金、死亡退職金、美術品・宝飾品などの動産、そして自宅の土地や建物なども含まれます。相続税の課税対象となる財産については、「相続税基本のきVol.1_相続税ってどんな財産にかかるの?」で詳しく解説しています。
相続税を軽減する方法の種類と分類方法
相続税を軽減するための方法は多岐にわたります。今回は大きく5つのタイプに分類しました。以下の表で各タイプの特徴と具体例をご紹介します。
| 種類 | 内容 | 具体的な方法 |
|---|---|---|
| 控除 | 計算した相続税から一定額を差し引く仕組み | ・配偶者の税額軽減 ・未成年者控除 ・障害者控除 ・贈与税額控除 ・相次相続控除 ・外国税額控除 |
| 特例 | 相続財産の評価を下げることで結果的に相続税を軽減する仕組み | ・小規模宅地等の特例 ・貸付不動産の評価減 ・配偶者居住権 |
| 非課税財産 | 相続税の計算対象から除外される財産 | ・生命保険金の非課税枠 ・死亡退職金の非課税枠 ・墓地や仏具等の祭祀財産 |
| 債務控除 | 相続財産の総額から故人様の債務や葬儀費用等を差し引く仕組み | ・葬儀費用の債務控除 ・医療費の債務控除 |
| 生前対策 | 故人様がご存命の間に行う相続税対策 | ・生前贈与 ・相続時精算課税制度 ・特定の用途のための非課税贈与 ・生前の不動産活用(賃貸化など) |
以下で各項目を詳しく解説していきます。
相続税を軽減できる控除制度

ここでは主に、計算した相続税から一定額を差し引くことができる制度を紹介します。
どのような相続人が、どのような条件で、どれくらいの控除を受けられるのか、ひとつずつ確認していきましょう。
配偶者の税額軽減|配偶者の相続税を大幅に軽減する

相続税の控除制度の中でも、特に大きな節税効果があるのが「配偶者の税額軽減」です。これは故人様の配偶者が相続する際に、配偶者にかかる相続税を大幅に軽減できる制度で「配偶者控除」ともいわれます。
具体的には、配偶者が相続した財産のうち、次の2つのうちいずれか大きい金額まで相続税がかかりません。
例えば、故人様が残した財産が3億円で、配偶者と子供1人が相続人である場合、配偶者の法定相続分は半分の1億5,000万円となります。この場合、1億6,000万円の方が大きいので、配偶者が1億6,000万円までの財産を相続しても相続税はかかりません。
また、もし故人様の財産が4億円だった場合は、配偶者の法定相続分は2億円となりますので、その2億円まで相続税はかかりません。
ただし、配偶者の税額軽減を適用するには、いくつかの条件があります。まず、法律上の配偶者であることが必須です。内縁関係(事実婚)の場合はこの控除は適用されません。また、相続税の申告期限(通常は故人様がお亡くなりになった翌日から10ヶ月以内)までに遺産分割を完了させ、申告書を提出する必要があります。
本来、相続税申告書は相続税を払う必要がある場合にのみ提出するものですが、この配偶者の税額軽減を受けるためには、たとえ最終的な納税額がゼロになったとしても、必ず申告書を提出しなければなりません。申告をしないと、せっかくの優遇措置を受けることができないので注意が必要です。
葬儀社の方々がご遺族様に対応する際、配偶者がいらっしゃる場合は、この制度について簡単にご案内しておくと安心につながります。「配偶者の方には相続税の大きな優遇制度がありますので、ご安心ください。」と一言添えるだけでも、悲しみの中にあるご遺族様の不安を少し和らげることができるでしょう。
未成年者控除|未成年者の相続税を軽減する

故人様の子どもや孫などが未成年のまま相続人となった場合、「未成年者控除」という制度が利用できます。これは、まだ自立して生計を立てることが難しい未成年者への配慮として設けられた控除制度です。
未成年者控除は、未成年のご遺族様が18歳になるまでの年数に10万円を掛けた金額を、その未成年者が負担する相続税額から差し引くことができる制度です。控除できる金額を計算式にすると、以下のようになります。
例えば、12歳の子どもが相続人である場合、(18歳-12歳)×10万円=60万円が相続税から控除されます。
なお、この控除は成人年齢の引き下げに伴い変更があったことに注意が必要です。令和4年4月1日以前の相続では20歳を基準としていましたが、現在は18歳を基準としています。年齢は相続開始時(故人様が亡くなった時点)の満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。
未成年者控除を受けるためには、いくつかの条件があります。まず、未成年者が日本国内に住所を持っていることが必要です。海外在住の未成年者は残念ながらこの控除を受けることができません。また、法定相続人であることも条件となります。養子縁組をしている場合でも、法定相続人であれば控除の対象となります。
障害者控除|障害者の相続税を軽減する

故人様の相続人の中に障害をお持ちの方がいらっしゃる場合、「障害者控除」という制度を利用できます。これは、障害のあるご遺族様の将来の生活費や医療費などの負担を考慮して設けられた控除制度です。
控除される金額は以下のように、障害の程度によって異なります。
例えば、50歳の一般障害者のご遺族様であれば、(85歳-50歳)×10万円=350万円が相続税から控除されます。一方、同じ50歳でも特別障害者の場合は、(85歳-50歳)×20万円=700万円と、控除額が倍になります。
「一般障害者」と「特別障害者」の区分は次のとおりです。特別障害者は、一般障害者よりも障害の程度が重いと認められる方々です。
例えば一般的には、足の怪我で1km以上連続歩行できない方は一般障害者、自力で歩行することが困難であり車いすや補助具を使用している方は特別障害者として認められます。
この控除を受けるためには、障害者のご遺族様が日本国内に住所を持っている必要があります。また、法定相続人であることも条件となります。
ご遺族様が障害者控除に関して気になるポイント
Q1: 要介護認定を受けている相続人は、相続税の障害者控除を適用できる?
A1: 相続人が要介護認定を受けているというだけでは、残念ながら相続税の障害者控除の適用条件を満たしません。ただし、お住まいの市区町村窓口に「障害者控除対象者認定書」の交付申請をして認められれば、障害者控除の対象となります。
Q2: 療育手帳を持っている場合は、相続税の障害者控除を適用できる?
A2: はい、適用できます。療育手帳をお持ちの方は、知的障害があると公的に認められている証明になります。そのため、障害者控除を適用が可能です。
Q3: 故人様が障害者だった場合、相続税の障害者控除を適用できる?
A3: いいえ、適用できません。相続税の障害者控除を適用できるのは、相続財産を取得した「相続人が障害者である場合」に限られます。
贈与税額控除|贈与税との二重課税を防止する

「贈与税額控除」とは、故人様が亡くなる前に、故人様から財産を贈与されていた場合、その贈与に関して支払った贈与税を相続税から控除できる制度です。この制度は、同じ財産に対して贈与税と相続税の両方が課税されるという二重課税を防止するためのものです。
まず、基本的な考え方として、生きている人から財産をもらうのは「贈与」で贈与税がかかり、亡くなった人から財産をもらうのは「相続」で相続税がかかります。そして、亡くなる前の一定期間内の贈与は「相続財産とみなす」ことになっており、本来の相続財産と合算して相続税が計算されます。
問題となるのは、故人様が亡くなる少し前に贈与を受けていた場合、同じ財産に対して「贈与税」と「相続税」の両方がかかってしまう可能性があることです。これが二重課税と呼ばれるものです。この二重課税を防ぐために「贈与税額控除」という制度があります。
対象となる期間は従来、亡くなる前の3年以内の贈与でしたが、2024年からは段階的に延長され、2031年以降は7年前までの贈与が対象になります。また、3年超〜7年以内の贈与については一定の控除が適用されます。
例えば、お父さんから亡くなる2年前に土地をもらい贈与税として100万円支払い、その後相続でさらに財産をもらうことになった場合、相続財産の計算時には2年前にもらった土地も含めて計算しますが、すでに支払った贈与税100万円は相続税から差し引けることになります。
葬儀社の方々がご遺族様と接する際に知っておくと良いのは、故人様が生前に贈与をしていたケースは珍しくないという点です。「故人様から生前に財産をいただいていた場合は、贈与税に関する配慮がある制度がございます」と一言お伝えすることで、ご遺族様の負担軽減につながる可能性があります。
相次相続控除|連続した相続の相続税を軽減する

短期間に続けて相続が発生してしまった場合、同じような財産に対して何度も相続税が課税されるという状況が生じてしまいます。これでは相続人に大きな負担がかかってしまうため、「相次相続控除」という制度で軽減できます。身近な例でいうと、父親が先に亡くなり、数年以内に母親も亡くなってしまったケースなどが該当します。
相次相続控除とは前回の相続(一次相続)から10年以内に再び相続(二次相続)が発生した場合に、前回支払った相続税の一部を控除できる制度です。控除額は、前回の相続からの経過期間によって変わり、短い期間であるほど控除率が高くなります。
具体的な計算方法は非常に複雑なため、ここでの解説は省きます。詳しく知りたい方は「国税庁|相次相続控除」をお読みください。
なお、相次相続控除の適用は、二次相続の相続人が一次相続の相続人でもあった場合に限られます。つまり、前回の相続で相続人ではなかった人は、この控除を受けることができません。また、相続放棄をした場合や相続権を失った場合も、相次相続控除は適用されません。
葬儀社の方々がご遺族様と接する際、短期間に連続して相続が発生したケースでは、「短期間に続けて相続が発生した場合は、前回支払った相続税の一部が控除される制度がございます」と一言お伝えすることで、経済的・精神的に負担の大きい状況にあるご遺族様に少しでも安心感を提供できるかもしれません。
ただし、前述したように控除できる金額の計算が複雑なため、ご遺族様自身で手続きを行うよりも、税理士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
外国税額控除|海外資産に対する二重課税を防止する

グローバル化が進む現代社会では、故人様が海外に不動産や預金などの財産を保有していることも珍しくありません。こうした海外資産を相続する場合、日本だけでなく海外でも相続税(または相続税に相当する税金)が課税されるケースがあります。同じ財産に対して二重に課税されることを防ぐために設けられた制度が「外国税額控除」です。
外国税額控除とは、海外で支払った相続税に相当する税金を、日本の相続税から控除できる制度です。例えば、故人様がアメリカに不動産を所有していた場合、その不動産はアメリカでも日本でも相続税の課税対象となります。このとき、アメリカで支払った相続税に相当する金額を日本の相続税から差し引くことができるのです。
外国税額控除で控除できるのは、次の2つのうちいずれか小さい方です。
葬儀社の方々がご遺族様と接する際、故人様が海外に財産をお持ちだった場合は、「海外に財産がある場合、二重課税を回避するための特別な控除制度がございます」とお伝えすることで、ご遺族様が余計な負担をすることを防げるかもしれません。
なお、外国税額控除の申告には、外国で提出した相続税の申告書の写しや納税証明書など、外国語の書類が必要になることがほとんどです。これらを日本語に翻訳したり、外国の税制を理解したりする必要もあり、一般のご遺族様にはハードルが高いといえるでしょう。税理士事務所の中には国際相続案件に強い事務所があります。こういった事務所の存在もあわせてご紹介できるととても親切でしょう。
相続財産の評価を下げる特例制度

ここでは、相続する財産の評価(価値)を下げられる特例制度を紹介します。
相続する財産の評価が高いほど、相続税も高額になるため、財産の評価を下げることは相続税を軽減することになるのです。
小規模宅地等の特例|土地の評価を大幅に軽減する

相続財産の評価を下げられる特例の中でも、特に強力なのが「小規模宅地等の特例」です。この特例を使うと、条件を満たす土地の評価額を最大で80%も減額することができます。例えば、評価額1億円の土地であれば、特例適用後は2,000万円として相続税を計算できるのです。これだけでも相続税額が大幅に下がることがおわかりいただけるでしょう。
この特例が設けられた背景には、「自宅や事業用の土地を相続したものの、高額な相続税を支払うために土地を手放さなければならない」というケースを防ぐ目的があります。故人様が大切にしてきた自宅や事業の場を守り、ご遺族様の生活や事業の継続を支援するための制度なのです。
小規模宅地等の特例は、土地の用途によって適用条件や減額割合、面積の上限が異なります。主な区分は以下の3つです。
| 土地の用途 | 減額割合 | 面積の上限 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 (自宅の土地) | 80% | 330㎡まで |
| 特定事業用宅地等 (事業用の土地) | 80% | 400㎡まで |
| 貸付事業用宅地等 (アパートなど賃貸用の土地) | 50% | 200㎡まで |
例えば、故人様が住んでいた自宅の土地(居住用宅地)を配偶者や同居していた親族が相続する場合、その土地の評価額が80%減額されます。ただし、適用できるのは330㎡までの部分です。330㎡を超える部分については通常の評価額となりますので注意が必要です。
この特例を受けるための条件として特に重要なのが、「誰が」その土地を相続するかという点です。自宅の土地(居住用宅地)の場合、配偶者は無条件で適用を受けられますが、その他の親族については同居していたかどうかなどの条件があります。
事業用宅地については、その事業を引き継ぐ方が相続することが条件となっています。また、貸付事業用宅地については、その貸付事業を継続することが条件となります。いずれの場合も、相続税の申告期限(故人様がお亡くなりになってから10ヶ月以内)まで所有し続けることが必要です。
葬儀社の方々がご遺族様と接する際に知っておくと良いのは、この特例を適用するためには必ず相続税の申告が必要だという点です。相続財産の総額が基礎控除額以下で、本来なら相続税がかからないケースでも、小規模宅地等の特例を適用するためには申告が必要です。申告を怠ると、特例が受けられなくなってしまいますので注意しましょう。
貸付不動産の評価減|賃貸中の不動産の評価を軽減する

故人様が賃貸アパートやマンションなどの貸付不動産を所有していた場合、不動産の評価を通常よりも低く算定できます。これが「貸付不動産の評価減」です。この制度は、貸し出されている不動産は、所有者の意思のみでは自由に使用・処分できないという制約があることを考慮したものです。
貸付不動産の評価減は、建物と土地それぞれについて適用されます。まず、貸家(他人に貸している建物)については、通常の建物の評価額から借家権割合(30%)を控除して評価します。例えば、500万円の建物であれば、500万円×(1-0.3)=350万円と評価額が30%下がります。第三者に貸している建物の評価は30%減できると覚えておけば問題ありません。
一方、貸家建付地(貸家の敷地)については、自用地としての評価額から一定割合を控除して評価します。この割合は「借地権割合×借家権割合×賃貸割合」で計算されます。借地権割合は地域によって異なり、国税庁が定めた路線価図等に記載されています。
この評価減を適用するためには、いくつかの条件があります。まず、相続開始時点(故人様がお亡くなりになった時)に実際に賃貸されていることが必要です。また、賃貸借契約書など貸し出していることを証明する書類が重要になります。さらに、アパートやマンションなど複数の部屋がある場合は、実際に入居者がいる部屋の割合(賃貸割合)によって評価減の度合いが変わるため注意しましょう。
配偶者居住権|不動産に住む権利と所有権をわける

配偶者居住権とは簡単にいえば、故人様の配偶者が亡くなるまで(または一定期間)、故人様の所有していた自宅に住み続けることができる権利です。
例えば、故人様と配偶者、そして子どもがいる家族の場合、従来は自宅の所有権をどのように分けるかが問題になっていました。配偶者が自宅の所有権を相続すれば安心して住み続けられますが、子どもの相続分が少なくなります。一方で子どもが所有権を相続すると、配偶者の住む場所が不安定になる恐れがありました。
そこで配偶者居住権を活用すれば、配偶者は「居住権(住む権利)」を、子どもは「所有権(居住権付き)」を相続するという形で遺産分割ができます。配偶者は引き続き自宅に住み続けることができ、子どもは将来的に不動産を引き継ぐことができるのです。
相続税を軽減するという観点からも、配偶者居住権には大きなメリットがあります。
例えば、1億円の自宅があった場合、通常なら1億円の評価額に対して相続税が課されますが、配偶者居住権とすることで、配偶者の居住権部分(例えば6,000万円)と所有権部分(4,000万円)に分かれ、それぞれに対して相続税が計算されます。
配偶者には、前述した「配偶者の税額軽減」があるため、これを活用すれば相続全体の相続税を軽減することができるのです。
なお、この制度は令和2年の民法改正で誕生しました。そのため、制度の存在自体を知らないご遺族様も多いでしょう。特に高齢の配偶者がいらっしゃるご家族には、「お住まいを守りながら相続できる新しい制度があります」とお伝えすることで、住まいの将来に対する不安を和らげることができるかもしれません。
相続税がかからない非課税枠や非課税財産

相続税の計算では、一定の金額まで非課税となる制度や最初から課税対象にならない財産があります。これらを活用することで、相続税の負担を効果的に減らすことができます。ここでは、非課税枠や非課税となる財産について詳しく解説します。
生命保険金・死亡退職金の非課税枠

故人様の死亡によりご遺族様が受け取る生命保険金や死亡退職金には、一定の金額まで相続税がかからない「非課税枠」が設けられています。
生命保険金と死亡退職金の非課税枠は以下の通りです。
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、生命保険金は1,500万円まで、死亡退職金も1,500万円まで、それぞれ非課税となります。つまり、合計で3,000万円の非課税枠があることになります。
この非課税枠を活用するためには、いくつかの条件があります。まず、受取人が法定相続人であることが必要です。法定相続人以外の方(例えば内縁の妻や友人など)が受け取った場合は、非課税枠の適用はありません。また、相続放棄をした方については、法定相続人の数にはカウントされますが、その方自身が受け取る保険金等については非課税枠の適用はありません。
生命保険金の場合、契約者(保険料を支払った人)、被保険者(保険の対象となる人)、受取人の関係によって、相続税ではなく所得税や贈与税が課税されるケースもあります。ただし、一般的な「契約者=被保険者=故人様」「受取人=ご遺族様」というケースは相続税の対象となり、非課税枠が適用されるため、基本的には心配ありません。
死亡退職金については、故人様が会社にお勤めだった場合に、ご遺族様が受け取る退職金が対象となります。これは通常の退職金とは異なり、亡くなったことによって支給される特別なものです。また、「弔慰金」と呼ばれるお見舞金についても、一定の範囲内であれば非課税となります。
祭祀財産(墓地・仏壇等)は非課税財産

相続税の課税対象となるのは、原則として故人様が残されたすべての財産ですが、例外として完全に非課税となる財産があります。その代表的なものが「祭祀財産」と呼ばれる、墓地や仏壇、仏具などの財産です。
祭祀財産は、その性質上、売買や換金を目的とするものではなく、故人様を弔い、先祖を敬う目的で使用されるものです。そのため、相続税法では、これらの財産を相続税の課税対象から除外しています。具体的には、以下のようなものが祭祀財産として非課税となります。
- 墓地、墓石
- 納骨堂
- 仏壇、仏具、神棚
- 位牌、遺骨、遺影
- 系譜、祭具、霊璽(れいじ)
これらの祭祀財産は、相続財産としての金銭的価値がいくら高額であっても、相続税はかかりません。例えば、故人様が高級な仏壇や由緒ある墓地を所有していた場合でも、それらは相続税の計算から除外されます。
この非課税措置には、生前に墓地や仏壇を購入しておくことで、相続税の対象となる現金や預貯金を減らすという相続税対策としての側面もあります。例えば、1,000万円の現金を持っている方が、生前に500万円で墓地を購入していれば、相続時の課税対象は残りの500万円のみとなります。
ただし、注意すべき点もあります。祭祀財産として認められるためには、実際に祭祀のために使用されることが前提です。単なる投資目的で購入した墓地などは、祭祀財産とは認められない場合があります。
相続手続きの中で祭祀財産については特別な位置づけがありますが、非課税であるがゆえに見落とされがちな側面もあります。故人様の大切な想いが込められた祭祀財産を適切に承継できるよう、ご遺族様への情報提供をサポートいただければ幸いです。
相続財産から差し引ける費用

相続税の計算では、故人様が残した財産の総額から、債務や葬儀費用などを差し引くことができます。これを「債務控除」といい、相続税の負担を軽減する重要なポイントです。特に葬儀社の皆様にとって身近な葬儀費用や、長期入院されていた方の医療費などは、適切に控除することで相続税を減らせる可能性があります。ここでは、相続財産から差し引ける主な費用について解説します。
葬儀費用

相続税を計算する際、故人様の財産の総額から差し引くことができる重要な項目の一つが「葬儀費用」です。葬儀社の皆様にとっては特に知っておきたい制度ではないでしょうか。
相続税のルール上、故人様の葬儀にかかった費用は相続財産から差し引けます。相続税は正味の遺産額(財産総額から債務や葬儀費用を引いた額)に対して課税されるため、この控除を活用すれば相続税負担を減らせるのです。
葬儀費用として認められるのは、社会通念上、葬儀のために通常必要と認められる費用です。具体的には以下のような費用が含まれます。
- 通夜や告別式の式場使用料
- 棺や祭壇の費用
- 火葬料や火葬場使用料
- 僧侶やお布施の費用
- 会葬者への接待費用(常識的な範囲内)
なお、香典返しの費用や、初七日、四十九日、一周忌などの法要に関する費用は一般的に控除できないため注意してください。
特に相続財産が多く、相続税の申告が必要になりそうなケースでは、「葬儀費用は相続税の計算の際に差し引くことができますので、領収書は大切に保管してください」とお伝えすることで、ご遺族様の経済的負担を軽減し、信頼関係の構築につなげることができるでしょう。
医療費の債務控除

相続税の計算において、故人様が亡くなるまでにかかった医療費のうち未払い分は「医療費の債務控除」として相続財産から差し引くことができます。
医療費の債務控除として認められるのは、故人様が生前に受けた医療サービスの未払い分です。どのような医療費が控除できるのか、以下にわかりやすくまとめました。
葬儀社の皆様がご遺族様と接する際に知っておくと良いのは、医療費の支払いに関する書類(請求書や領収書など)を大切に保管するようお伝えすることです。特に長期入院されていた方の場合、医療費が高額になっていることも珍しくありません。「医療費の請求書や領収書は、相続税の計算で差し引けることがありますので、捨てずに保管されることをおすすめします」と一言添えることで、ご遺族様の負担軽減につながる可能性があります。
生前対策の基礎知識

相続税の負担を軽減するための対策は、実は亡くなる前から準備できるものがたくさんあります。生前から計画的に財産を移転することで、将来の相続税を大幅に減らせる可能性があるのです。ここでは、生前に行える代表的な相続税対策について紹介します。
生前贈与による相続財産の減少方法

生前に行える相続税対策として最もよく知られているのが「生前贈与」です。これは文字通り、生きているうちに財産を少しずつ家族に贈与することで、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を軽減する方法です。
生前贈与の最大のメリットは「暦年贈与」という制度を活用できることです。この制度では、1年間(1月1日から12月31日まで)に受け取る贈与財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかかりません。つまり、毎年計画的に110万円ずつ贈与していけば、長期間にわたって無税で財産を移転できるのです。
例えば、お子さんが2人いる場合、毎年それぞれに110万円ずつ、合計220万円を贈与することができます。10年間継続すれば、2,200万円もの財産を贈与税なしで移転できることになります。
相続時精算課税制度の活用

相続時精算課税制度は、60歳以上の方から20歳以上の子や孫への贈与において、2,500万円まで贈与税を控除できる制度です。贈与を受ける側からすれば、2,500万円までは贈与税がかからないということになり、大きな金額を一度に受け取ることができます。
この制度の特徴は、将来相続が発生した際に、すでに贈与した財産も相続財産に加算して相続税を計算する点です。つまり、完全に税金を免除するわけではなく、「今は贈与税を払わないが、将来相続税として清算する」という考え方なのです。このため「相続時精算課税制度」という名前がついています。
なお、2024年1月からは新たに年間110万円の基礎控除が設けられました。この110万円以内の贈与については、贈与税も相続税も非課税となり、申告も不要です。
この制度が特に有効なのは、将来値上がりが見込まれる不動産や株式を贈与する場合です。例えば、現在2,000万円の価値がある土地を相続時精算課税制度を使って贈与し、10年後に相続が発生した時にその土地が4,000万円に値上がりしていたとしても、相続税の計算では贈与時の2,000万円として計算されます。つまり、値上がり分の2,000万円に対する税金が全くかからないというわけです。
教育資金・結婚・子育て資金の一括贈与制度

少子高齢化対策の一環として、若い世代への資金移転を促す特別な贈与税制度があります。これらは、教育資金や結婚・子育て資金の贈与を税制面で優遇することで、世代間の資産移転を促進するものです。
以下の表は、これらの制度の概要をまとめたものです。
| 制度名 | 非課税枠 | 主な対象費用 | 適用期限 |
|---|---|---|---|
| 教育資金の一括贈与制度 | 1,500万円まで | 学校等の授業料、塾や習い事の費用、留学費用など | 2026年3月末まで |
| 結婚・子育て資金の一括贈与制度 | 1,000万円まで | 結婚式費用、新居の家賃、出産・保育関連費用など | 2025年3月末まで |
| 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度 | 省エネ等住宅:1,000万円までその他の住宅:500万円まで | 住宅の新築・取得費用、増改築費用など | 2026年12月末まで |
これらの制度は通常の暦年贈与(年間110万円までの基礎控除)と併用することができるため、例えば孫への教育資金1,500万円の贈与と、別途110万円の現金贈与を同じ年に行うことも可能です。このように複数の贈与税制度を組み合わせることで、より効果的な資産移転が実現できます。
まとめ
この記事では、相続税を軽減するための様々な方法を、「控除」「特例」「非課税財産」「債務控除」「生前対策」という5つの観点から解説してきました。相続税対策は一見複雑に感じられますが、それぞれの制度を理解し、ご遺族様の状況に合わせた情報提供ができれば、大きな安心につながります。
特に注目すべきは「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの強力な軽減制度です。これらを適切に活用することで、相続税負担を大幅に軽減できる可能性があります。また、生命保険金や死亡退職金の非課税枠、葬儀費用の債務控除など、葬儀に関連する部分での軽減措置も重要です。
葬儀社の皆様がこうした基本知識を持っていることで、必要に応じて「このような制度があります」と適切な情報提供ができるようになります。状況によっては専門家への相談も選択肢の一つとしてご案内することで、ご遺族様の不安軽減に大きく貢献できるでしょう。
悲しみの中にあるご遺族様にとって、経済的な不安が少しでも和らぐことは大きな支えになります。葬儀社として相続税の基本を理解し、ご遺族様の心に寄り添った情報提供ができることが、より深い信頼関係の構築につながるのではないでしょうか。