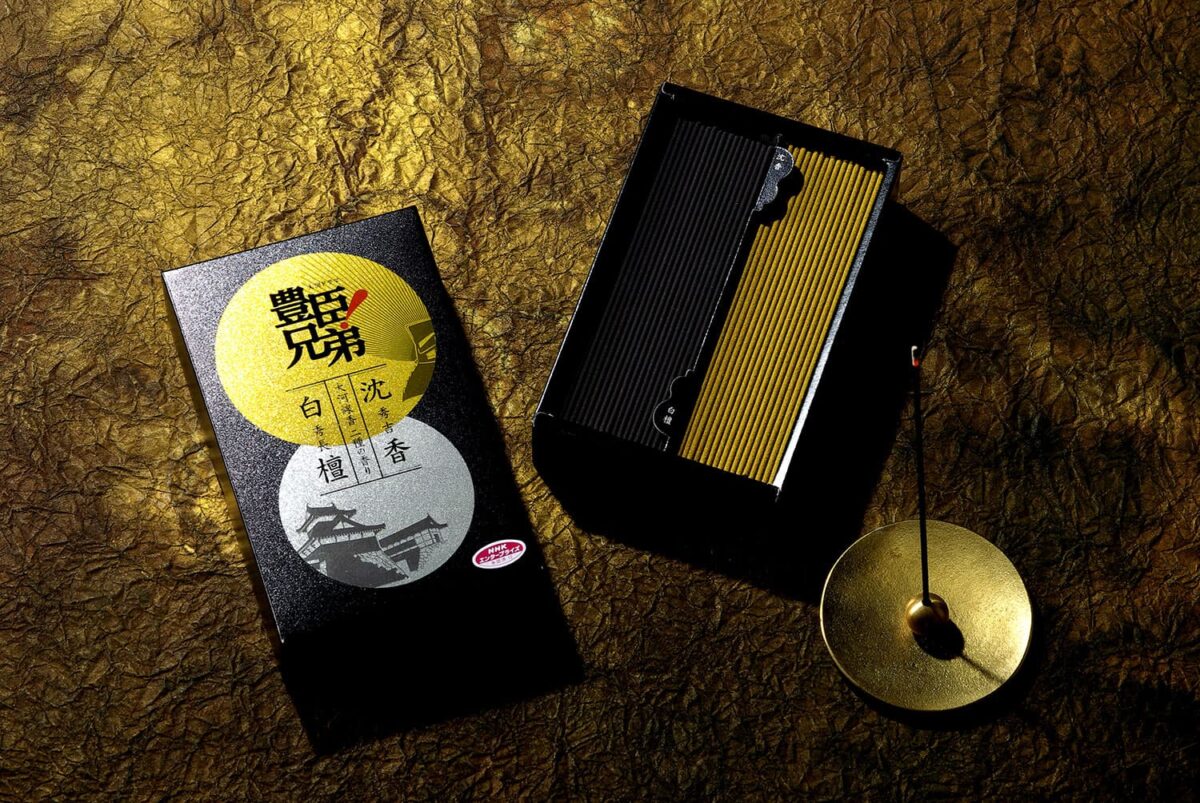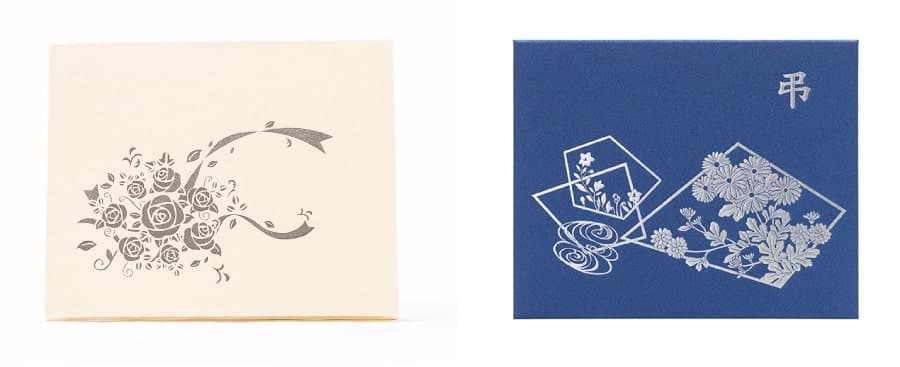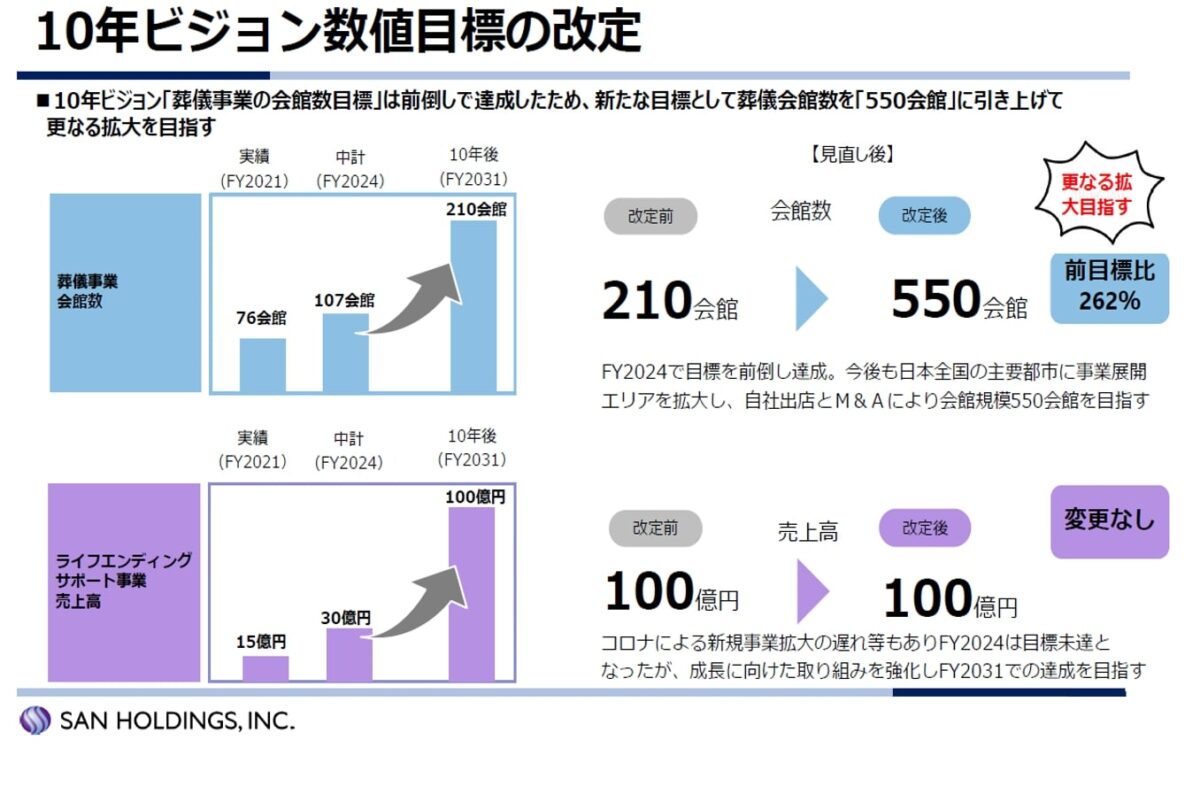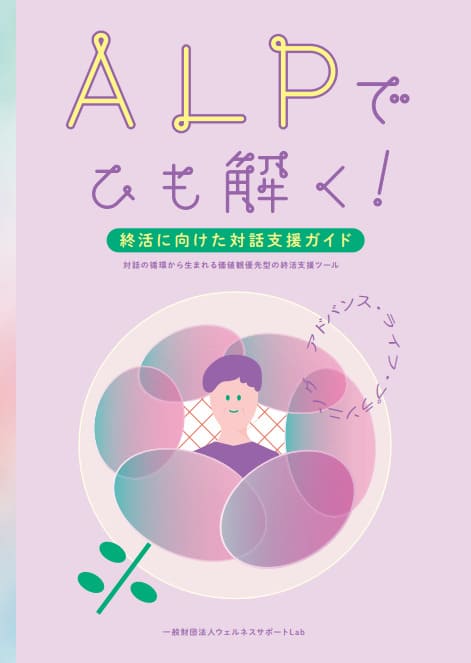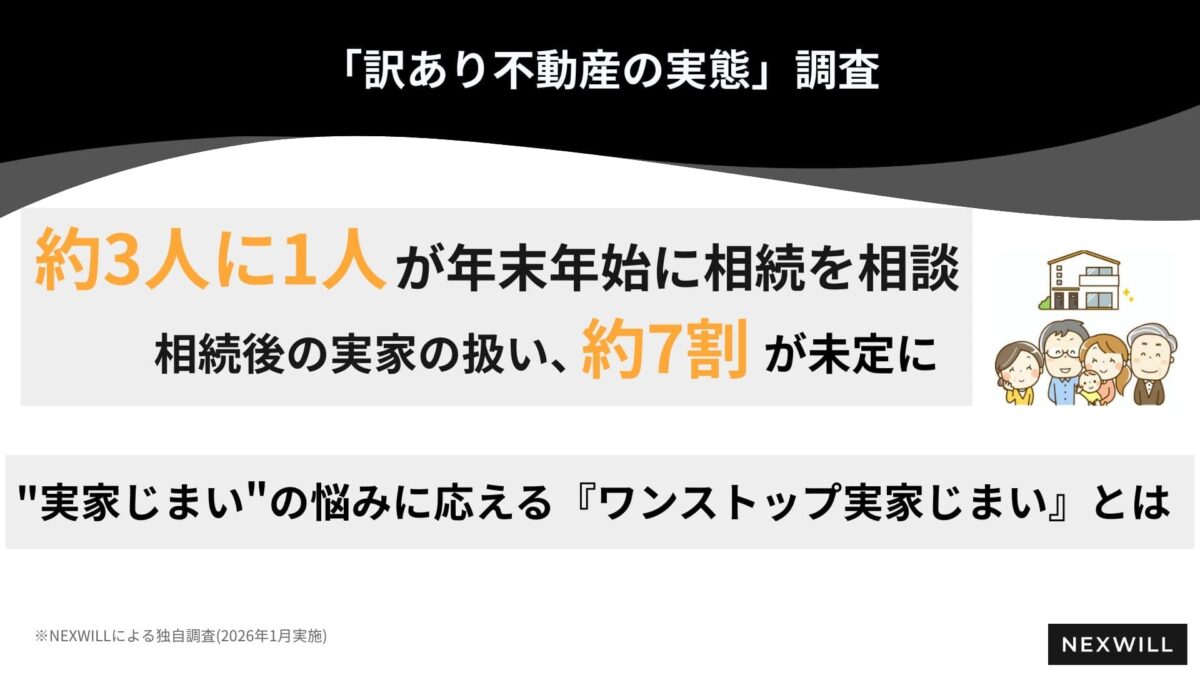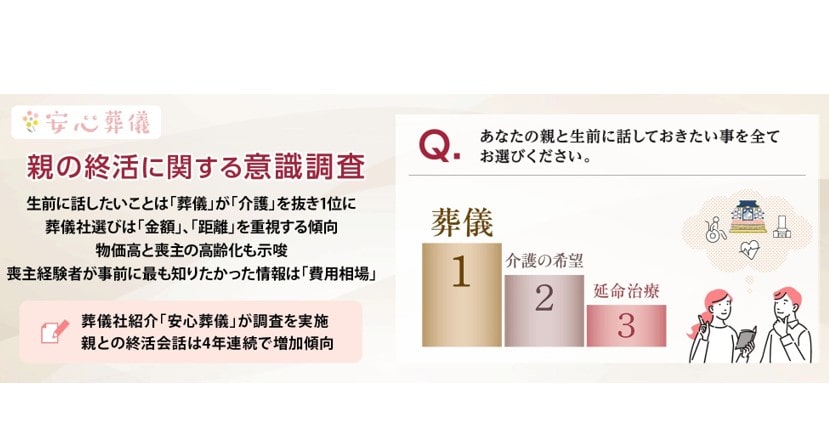高齢社会は、多死社会。いつか迎える親の死。息子である40代のわたしは、その一人でした。また、死はいつか自分にもやってきます。死は遠いことかもしれませんが、死を想うことは、今の生を想うこと。だからこそ、今、じぶんらしい弔いを考えてみたい。わたしは、自分の母の散骨をタイのメコン川でしました。その時の顛末を3回の連載でお伝えします。筆者は、サラリーマンを辞め、タイの大学で看護を学び、現在は、タイ人の妻とともに東北部にあるウドンタニ県に住んでいます。異国の地で出会った弔いに、母の老いと死に悩む私は多くのことを気づかされました。
第1回目は、義母のお葬式。第2回目は、母のメコン川での散骨。そして、最終回である第3回目は、わたしが出会った在タイの日本人で現地で亡くなった方のお話です。タイの人びとと家族になり、現地の人々の逝き方に接した彼が、今度は自分の死を迎える。彼の言葉から、彼が望む弔いの思いについて書いてゆきます。
「オレも、ばあちゃんの死に参加している」
タイには、多くの日本人が住む。ビジネス、留学、定年退職後のロングステイなど、様々な人々が住んでいる。多くの人はやがて日本に帰るが、なかにはタイ人のパートナーを持ち、異国の地で逝くことを選ぶ人もいる。そのなかには、日本での自分の親の介護・弔いだけでなく、タイでもタイ人の妻の父母について同様の経験をする人がいる。Cさんは、そのうちの一人だ。70代の彼は、タイ人の妻と結婚して23年になる。食品関係の会社に勤務時に、タイのバンコクに駐在する。また、日本での父母の介護のためにタイと日本を往復する時期もあった。会社の倒産、出産を契機に、妻の生まれ故郷に移住する。妻の父母と同居して居た時期もある。
「死がひたすら怖かった。ただただ、孤独。死んだら終わり、と思っていた」と語るCさん。その訳は、日本での自分の父母の火葬の時にあるという。「小さな部屋で焼かれて、煙さえみえなかった」、そして「気がついたら白い骨になってでてきた」のを見たからだという。しかし、タイ人の奥さんの母の葬儀の時は、「オレも、ばあちゃんの死に参加しているという気がした」という。なぜなら、「家族だけでなく村人も加わって、食事を作ることからはじめて、式のセッティング、焼き場へのお棺運び、みんなでやった」からだという。また「夜、みんなと同じ部屋で雑魚寝、みんなの間にいると、オレが守られているような感じがした。オレの親の葬儀の時はそんな感じじゃなかった」という。
[caption id="attachment_8652" align="aligncenter" width="225"] 逝く人生きる人[/caption]
逝く人生きる人[/caption]
そして、Cさんの話で印象的だったのは、義父の火葬を野原で行った件だ。「オレもお棺を他の村の人と担いだ、野原の真ん中で薪をくべ、その上にのせる、火をつける。だんだんと、とうちゃんの体が燃え、姿が変わっていくのがわかる、村の人はそれを周りで見てるんや。遺体の焼ける音、匂い。でも、怖いとか、そんな気持ちは起こらなかった。煙が空高く上っている、まるで父ちゃんが天に昇っていくように思えた。死が怖い、終わりという気持ちは起こらなかった」と日本での父母の死の時とは異なる印象を持っている。
[caption id="attachment_8651" align="aligncenter" width="400"] 寝たきりのおばあちゃんの向こうに赤ちゃんが[/caption]
寝たきりのおばあちゃんの向こうに赤ちゃんが[/caption]
「日本人は、世話されるのが下手やな。」
タイ人の妻の母はガンで亡くなった。彼女が死に際して「死が怖いけど、大丈夫。あんたらがいるから」と話したという。それを聞いたCさんは介護や死ぬときに他人に頼ってもよいということに驚いたという。「オレも頼っていいんかな」と言うCさん。Cさんが、さらに驚いたのは以下の妻の言葉だったという「べつにあなたが心配しなくても、ほっといたら、ここで死ねるよ」。
自分の父母の死との違いに驚いたCさんは以下のように話してくれた。「あのばあちゃんがうまいんや。だれかに世話されるのが、、、、。すべてをさらけ出して、あんたにおねがいしますって、そういうひとがこの村には、いっぱいおるな。でも自分の日本の父母は最後まで、他人にお世話されたくないといって、でも最後はお世話されるんやけど、大変やったな。日本人は、世話されるのが下手やな」。そして続けて「タイ人はオレに死について語り、多くを見せてくれた。とくに妻の父母の姿を見て、これやと思った」。やがて逝く人の気持ちの在り方を語るCさんは、すでに彼自身がタイで死ぬことを決めていたのだと思う。毎年の健康診断で特に何も問題がなかったCさんだが、やがて病に倒れることになる。