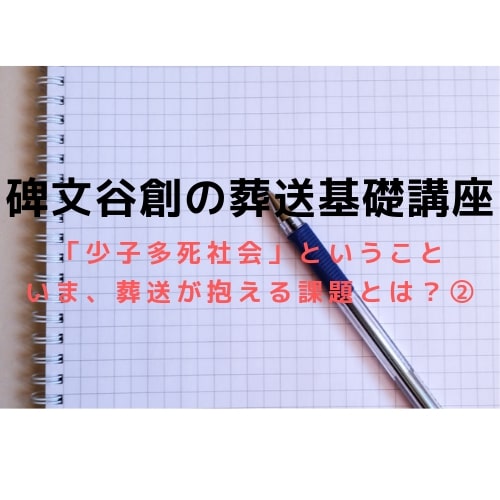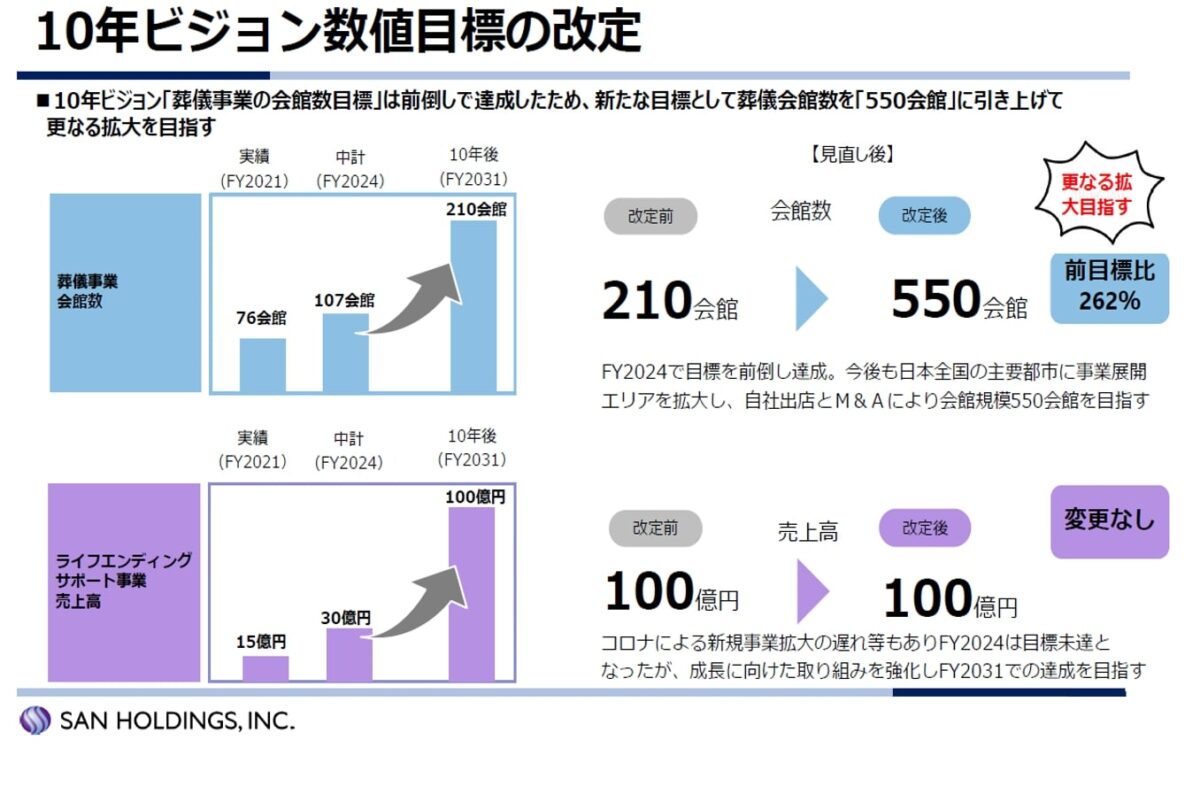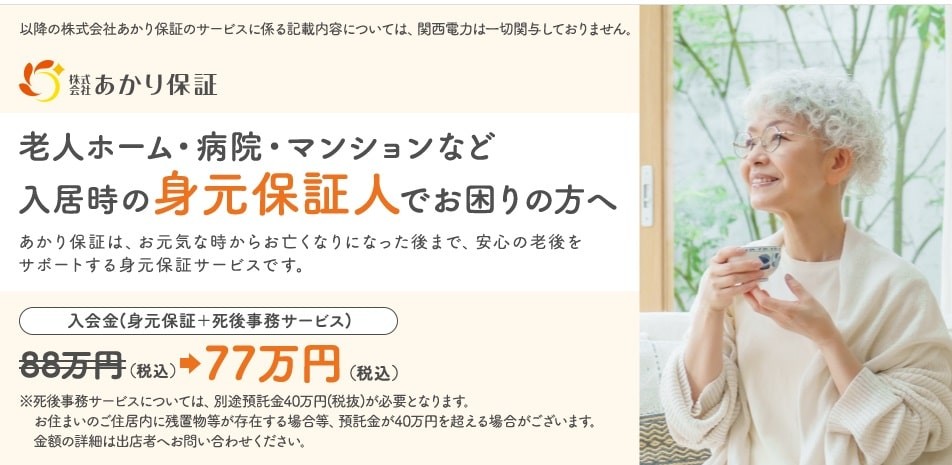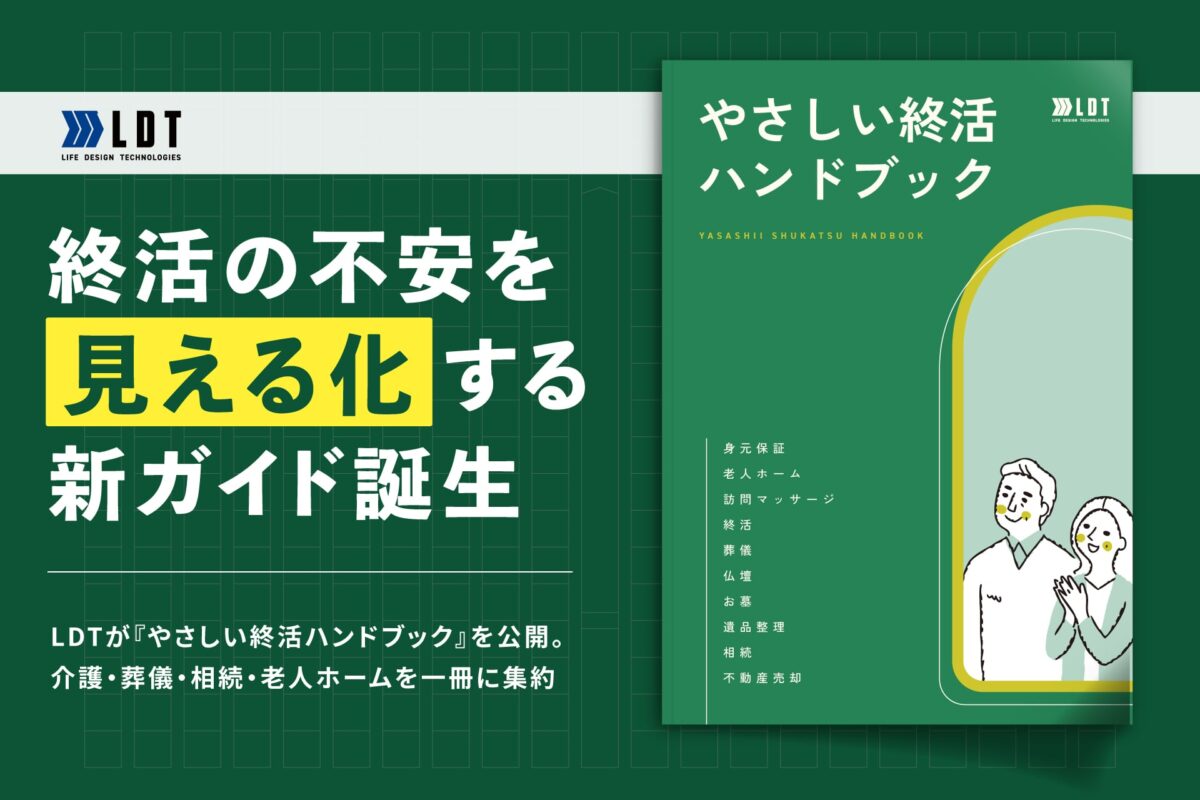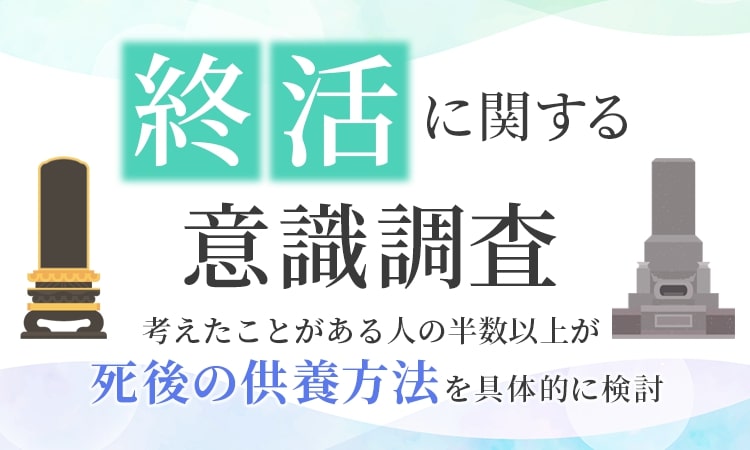碑文谷 創
少子化
「高齢化」と並ぶキーワードは「少子化」である。
最新の2017(平29)の出生数は100万人を切って946,065人。
最多が団塊の1948(昭23)年の2,681,624人であるから、その35.3%にすぎない。
日本では出生数が200万人を突破したのが、1947(昭22)年から1952(昭27)年であるから現在71-72歳から66-67歳の年代である。
まさにこの塊が定年後を迎えたことが週刊誌での異常とも言うべき「終活連続特集」の背景となっている。
※死の問題を熱心に考えるのは、女性は40代以降、男性は定年を控えた60代以降である。各種調査を見ても女性の40歳未満、男性の60歳未満のデータは信憑性が乏しい。あまりきちんと考えていないからだ。
女性が40代以降と早いのは家族の老いに直面し考えるからだ。男性はエゴイスティックな動物で、自分が定年を控え、自らの老いに直面して、ようやく考え始める。
もう一つの塊が「団塊ジュニア」と言われる1971(昭46)年から1974(昭49)年だ。出生数が200万人台を記録している。
47-48歳から44-45歳にあたる。就職氷河期の世代である。
1984(昭59)年に出生数は150万人を割り、平成元年である1989年に130万人を割り、2005(平17)年に110万人を割り、2016(平28)年についに100万人を割り976,978人を記録した。
「少子高齢化」というのは生産世代が縮小する時代。経済成長をあたりまえとする社会からの転換が求められる時代になったことを意味する。
多死社会
社会の高齢化が進めば当然のことながら死亡する人も増加する。「多死社会」と言われるゆえんだ。
日本経済の高度経済成長が始まるのが1955(昭30)年である。ここからバブル景気の最中の1989(平1)年まで約35年間にわたり日本の年間死亡数は60万人台、70万人台にとどまっていた。
これが変化するのが1990(平2)年、死亡数は80万人台に突入。以降、死亡数は増加し続けている。
1990(平2) 820,305人
1995(平7) 922,139人
2003(平15) 1,014,951人
2011(平23) 1,253,066人
2016(平28) 1,307,748人
多死社会というのは年間死亡数が増加しているということ。しかし、あまり実感がないのはなぜか?
それは寿命中位数が2017(平29)年で
男性84.08年 女性90.03年
であることが示すように、死者が6千人を超えた阪神淡路大震災や死者・行方不明が2万人を超えた東日本大震災等の災害死を除き、圧倒的に高齢者の死が増えたことによる。
私の義母は90歳で死亡した。
義母をよく知る旧制高女時代の友人は半数が死亡し、残った半数も、ある人は健康を害し、ある人は認知症となり、ある人は足腰が弱まり外出が不可能であった。
義母の葬式には友人本人の出席はなく、代理として友人のお嬢さんに数名出席いただいた。
町内関係は60代で娘に譲ったので、本当に近隣のご老人が数名出席されたのみ。
残りは子、孫の家族。唯一のきょうだいである弟は20代の学生で未婚のまま死亡しているし、たった一人の従弟も先年死亡していたので親戚は数人のみ。
葬式の参列者は合わせても20人足らずであった。
断っておくが「家族葬」をうたったわけではない。
「多死社会」というと「火葬場が足りなくなる!」という短絡的な報道がされがちである。
年間80万人から年間100万人まで増加するのに13年間要している。年間にして1.5万人が全国で増加している計算だ。
全国の火葬場数を1400とすると、1火葬場あたり年間10件増加するだけである。
そんなにすぐに火葬場不足の時代が到来するわけがない。
テレビ等で騒がれたのは、以前から火葬場建設計画があったものの地元の反対で建設が遅れているほんの一部の都市の例だけ。それがおもしろおかしく取り上げられたためである。
死に対する感覚の多様化
「死」に対する感覚はある意味露骨である。
40歳未満の人の死は「傷(いた)い」
70歳未満の人の死は「惜しい」
90歳以上の人の死は「納得」
どう扱っていいのか悩むのが70代、80代の人の死。
昭和前期までは80歳を超えて生きるのは3~5%の世界であったから、80歳を超えた人の死では長寿を寿ぐような祝いの葬式をされた。
今、80歳を超えて死亡する人は6割を超えていて、「最も一般的な死」である。
人の死には古来グリーフ(死別の悲嘆)がつきものであった。だが、グリーフが伴わない死が増加している。
「遺族」はグリーフを共有する者たちではなく、グリーフは遺族のほんの一部が体験し、あるいは遺族以外の友人、看護・介護した職員に悲嘆が代行される事例が増加している。