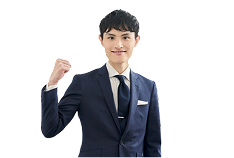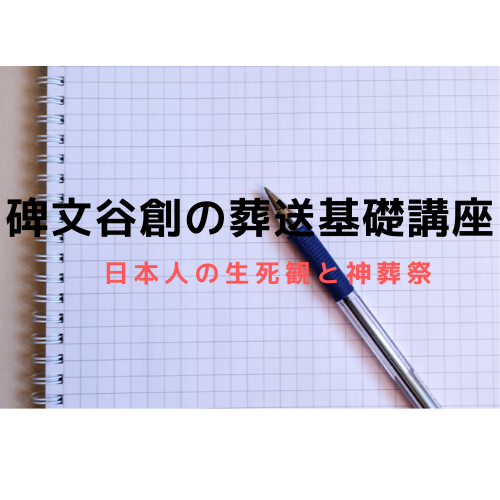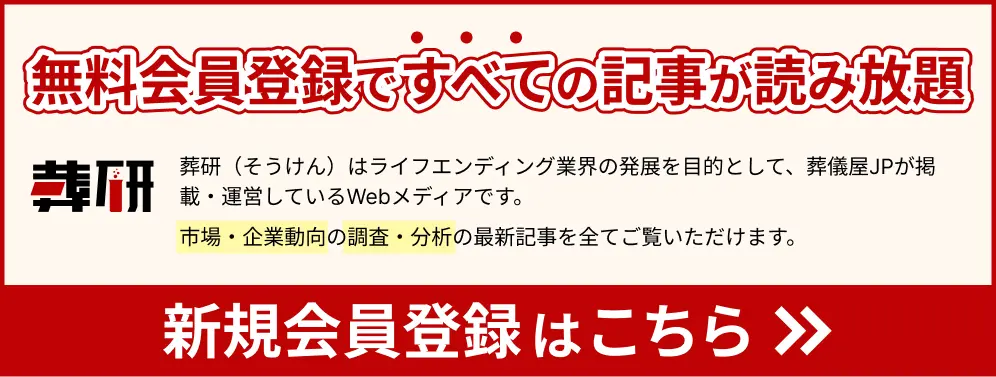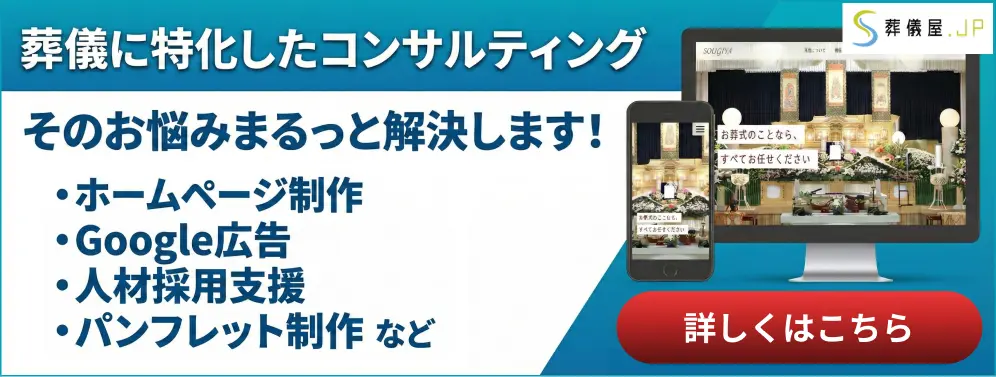この記事を音声で聴く
仏教の葬祭仏教化
仏教の葬祭仏教化が仏教の民衆化、庶民化のカギになったが、これは中世末期から近世初頭の戦国時代にあたる。
それまで仏教は貴族・武士の宗教であったのが、下級または半僧半俗ともいうべき僧侶たち(聖ヒジリなどと呼ばれた)が教団の意思とは異なり地方に放たれ、定住して民衆もまた成仏する、浄土へ往生すると説いたことによる。
その仏教の民衆化の力を江戸幕府が利用し、寺請制度という形で法制化した。
仏教の民衆向けである檀信徒向け葬法は、真宗を除き、僧侶とする儀礼を援用し、「戒名を与え仏弟子にしてあの世へ送る」という禅宗の葬法を基本としたものであった。
神葬祭運動―仏教葬の強制への神職たちからの反発
この江戸幕府の、神職すら寺の檀家となり、檀那寺での葬儀を強制することに儒学者、国学者、神職が反発し、神葬祭を志向。
近世末期(1785年)に吉田家からの免許状を条件に神職とその嫡子に限り神葬祭を行うことが許可された。
それ以前は水戸藩で日本古来の葬法は儒礼に近いものがあるとして朱子の「家礼」をアレンジする形で神葬祭が始まった。
神葬祭の誕生
実際に神葬祭の形式が誕生するのは幕末のことである。
それが集大成されたのが1872(明治5)年の教部省『葬祭略式』である。
この同じ年に明治政府が「自葬禁止の布告」を出し、一般の人まで自由に神葬祭ができるようになった。
しかし1882(明治15)年に内務省が官幣社、国幣社の宮司の神葬祭関与を禁止し、府県社以下の神職のみの関与を認めたので、すべての神職に神葬祭関与が認められたのは戦後のことである。
江戸時代に神葬祭運動が生じたのは仏教葬が僧侶の得度式を模したので、なぜ神々に仕えた神職まで出家しなければならないのか、と反発したことによる。
神社の信仰
神社神道とは、「神々とその建物や森などを守ってきた共同体の信仰」ということ。
聖書、教会を中心としたキリスト教や仏典、教団を中心とした仏教などの宗教とは異なる独自性をもっている。
神社の信仰とは、「自然の中で生活を繰り返してきた人たちの信仰」で、「自然の中で生活してきた人たちが、自然の人智を超えた美しさや畏さを知り、そこに神を実感し、自然の神気に触れて浄化されたい」という人間の感情、信仰心を本質としている、とまとめることができようか。
仏教以前の葬法としての神葬祭
神葬祭を「仏教以前の日本人の固有の葬法」で、これこそが日本人本来の葬法という理解がある。
古代においては食い別れのような食事、死者に対し馳走して別れるという儀式があったらしい。
太古から死者を葬るのには葬列が組まれたらしい、ということが『古事記』や『常陸風土記』等により推測される。
柳田國男が『先祖の話』で書いているように、日本人の死後観は西方浄土のような遠くに行くのではなく、霊は永久に国土に留まっている、と考えられるので、亡くなっても生前と同じように食事を出して仕える。
蘇生しなければ、死者の世界に完全に入るとして野辺の送りをして葬る。
御霊(みたま)は生きてわれわれの生活の周辺や山にいていつでも交流できる。
したがって生前と同じように御霊に仕える。
「神より出でて神に入るなり」という言葉があるように、死者の御霊は「土に還る」、大自然に還る。
したがって、死者、亡き人を生前と同じように送り、また、いつでも還っていただく。
御霊は、死後も子孫が繁栄し、子孫の手厚い祭りを受けられる、という日本人が安心立命できる境地が神葬祭の死生観といえよう。
『千の風になって』の流行
こうした死生観は実は日本仏教文化に生きている。
彼岸、お盆、仏壇という習俗を見れば、死者は近くにいる、という観念を共通に保持している。
2006(平成18)年の紅白歌合戦で歌われ大ヒットした「千の風になって」は作者不詳だがアメリカ人の手による、という説が有力である。
新井満の訳詩は
私のお墓の前で泣かないでください
そこに私はいません
眠ってなんかいません
千の風に
千の風になって
あの大きな空を
吹きわたっています
で始まる。
途中の「千の風になって」が詩、歌のタイトルとなっている。
原詩は詩の冒頭の「DO NOT STAND AT MY GRAVE AND WEEP」が通称となっている。
この歌が大流行したことは、家族や恋人など身近な人の悲しみを多くの人が抱え続けているという事実である。
日本人が春秋の彼岸、お盆、仏壇、法事を大切にしてきたし、いまもしているということは、死者を追悼し、覚えるということがいかに私たちの心性に強いかということを示している。
無常観
仏教の、というより日本人の死生観に強いのは「無常観」である。
これは東日本大震災でも見直されたものである。
死というのは、老年期(65~75歳未満の前期高齢と75歳以上の後期高齢を分けるようになっている)の後にくるという理解が現在は一般的である。
しかし、これは歴史でいえば「近年」の話で戦後のことである。
人間の生涯は老年期まで続くのが当たり前ではなかった。死は、幼少期—青年期—壮年期—老年期のどこの時期にも入り得るものであったし、その本質はいまも変わらない。
かつての社会では感染症や気候変動による飢餓、自然災害にはとても弱く、医療も発達していなかったので、老年期まで生き延びるが至難な社会であった。
むしろ老年期以前の死が当たり前の時代だったのだ。
昭和初期までは80歳以上の長寿による死亡は全死亡者の5%未満の稀少で、それゆえ長寿が渇望された。
80歳以上の死亡者が全死亡の63%となり、「普通の死」となった現在とは大きく異なる。
「無常観」について『広辞苑』(第六版)で見ると、
無常観 一切のものは無常であるという観想
無常 ①【仏】一切の物は消滅・変化して常住でないこと。②人生のはかないこと。③人の死
とある。
『佛教大事典』(小学館)を見ると、
無常とは「常なることのないこと」を意味するサンスクリット語からきた
と説明されている。
無常観の死生観としての現代語訳
そこで思いっきり私なりに一般に言われる無常観を死生観として翻訳すると、次のようになる。
①サクラの花に象徴されるように、つぼみの時、盛んに咲き誇る時、散る時、と人間の一生は流転し、最後には死ぬということ。
②人間は有限な生物であり、死を免れることはないこと。
③人間はいつ死ぬと定まっておらず、いつ何どき死に遭遇するかわからないこと。
3つに集約しても少しずつニュアンスが違う。
1995(平成7)年1月17日5時46分に発生した阪神・淡路大震災、2011(平成23)年3月11日14時46分に発生した東日本大震災を体験した時、私たちは、「いつ何どき何が起こるかわからない」という現実を恐怖の中で共有したのではないだろうか。
そしてこうした大災害は、歴史上繰り返し起こってきた。
「ケガレ」の再考
「ケガレ」はマイナスの感覚で理解されることが多い。
しかし神道で死を穢れと見る感覚は、死の現実をリアルに見ることにも通じているように思える。
大自然に対して恩恵だけではなく畏怖を覚えるのはそのリアルな凶暴さへの自覚があるからだと思う。
人間の遺体は放っておくならばそれは腐敗していくのは現実である。
「穢れを清める」とは、穢れから遠くに立つことではなく、そうした人間、自然のもつリアルな現実を見据えるから清め、祓うことが切実性をもつのではないか。
穢れ観の見直しが神葬祭を進めるうえで必要とされるように思われる。