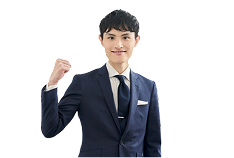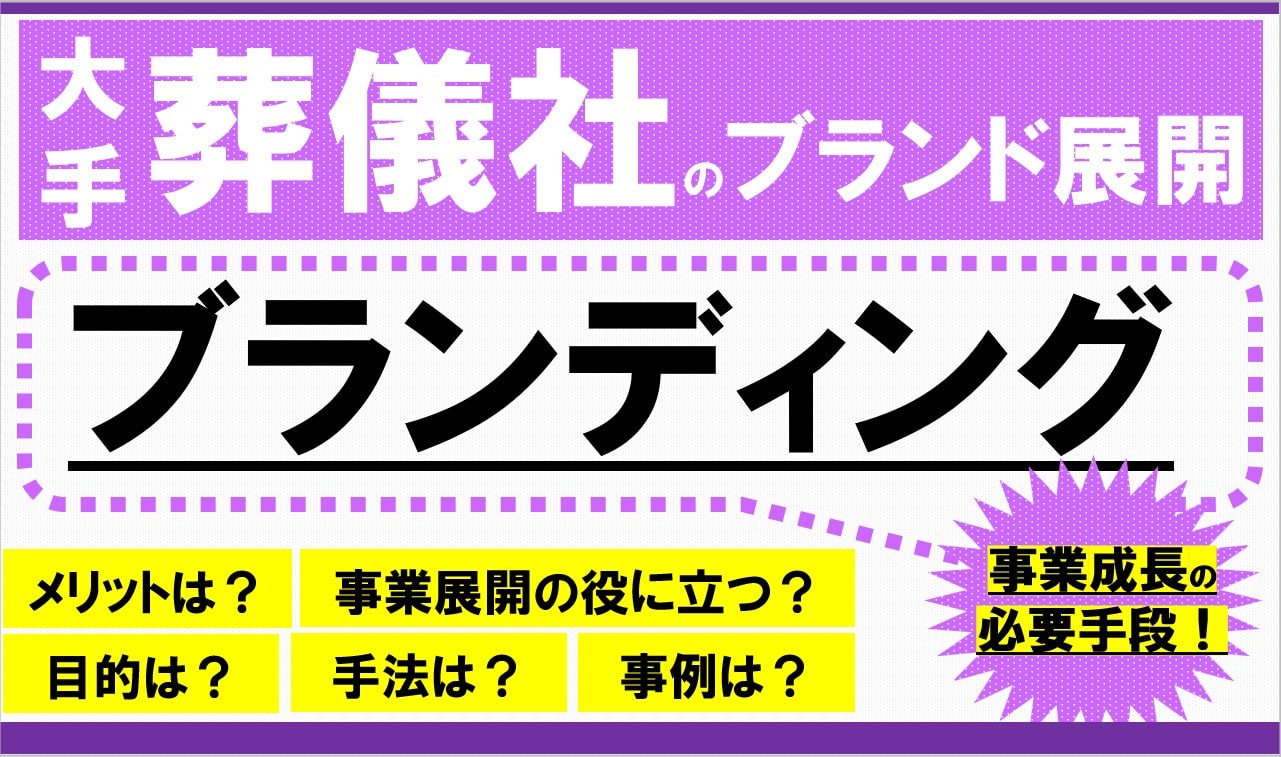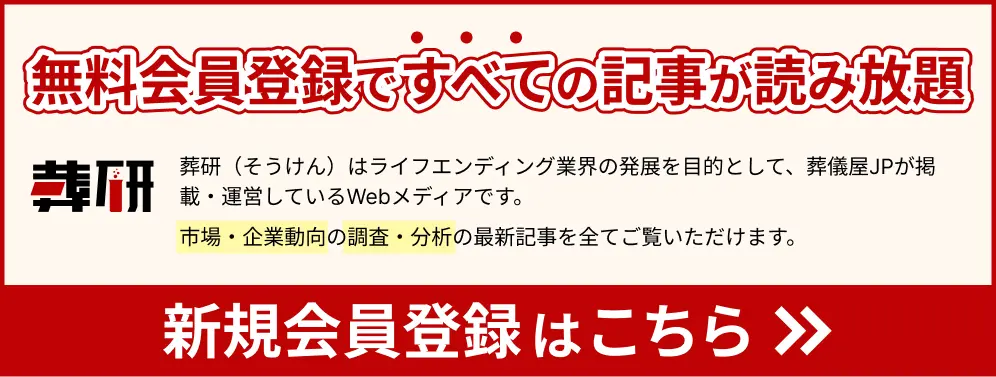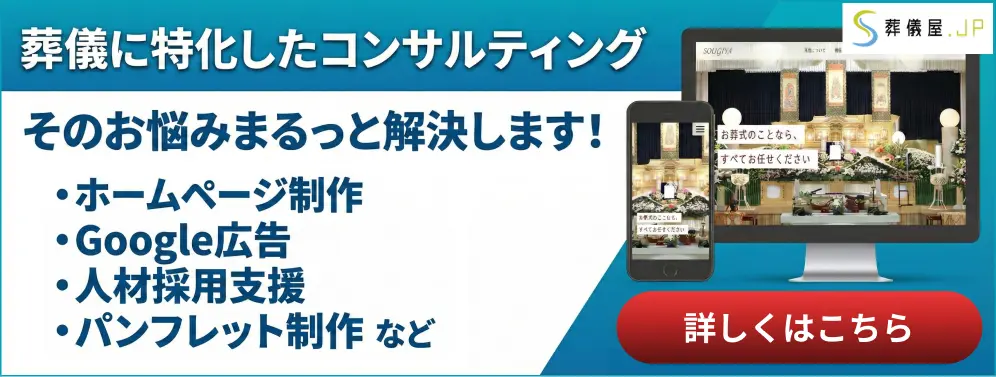近年の葬儀業界では、少子高齢化や核家族化などの影響から少人数で見送る家族葬が主流となりつつあります。
そのため家族葬に特化した専門葬儀社では、低価格を前面に押し出したTVCMなどで露出を増やし、葬儀ブランド名の認知度向上を図るケースが少なくありません。
一方、上場葬儀社や大手冠婚葬祭互助会では、メインの葬儀ブランド名を表に出さないマルチブランド戦略を用いて、新たに「家族葬」専門ブランドを立ち上げるケースが増えています。
大手葬儀社がマルチブランド戦略を選択する背景には、小規模化・簡素化が進む葬儀市場への対応以外にも、別の狙いがあるようです。
そこで本記事では、大手葬儀社ならではの課題や、マルチブランド戦略をとる理由などについて、詳しく分析します。
集客方法やブランディングの重要性など、事業規模を問わず葬儀社運営に役立つ部分もあるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
あわせて読みたい
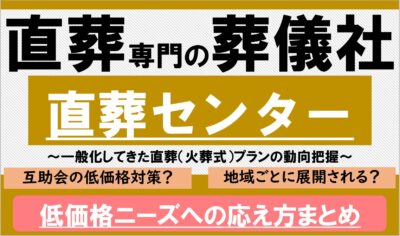
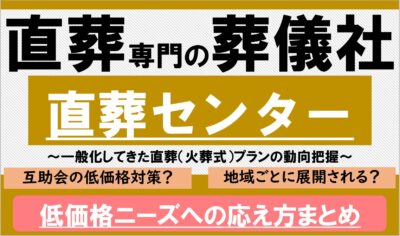
【直葬センター】直葬(火葬式)プランの訴求で低価格対応をおこなう事業者まとめ
「〇〇直葬センター」名義で運営されている斎場を近頃よく目にしますが、実際のところ運営元企業はそれぞれ異なります。一見すると、全国的な葬儀の小規模化・簡素化に...
目次
- 大手葬儀社ならではの課題
- 葬儀ニーズの2極化
- 二重価格問題
- 葬儀ポータルサイトとは
- 二重価格問題とは
- 会員制度との矛盾
- マルチブランド戦略とは?
- マルチブランド戦略のメリット・デメリット
- メリット
- デメリット
- 大手葬儀社がマルチブランド戦略を選択する理由
- マルチブランド戦略のメリット・デメリット
- 大手葬儀社が運営する家族葬専門ブランドの実例
- 家族葬のタクセル(アルファクラブグループ)
- 家族葬専門式場 はないろ(ベルコ)
- お葬式のひなた(メモリード)
- わが家の家族葬(サン・ライフホールディング)
- ENDING HAUS.(公益社:燦ホールディングス)
- まとめ
大手葬儀社ならではの課題

葬儀ニーズの2極化