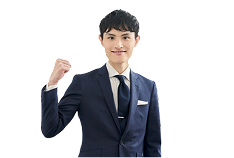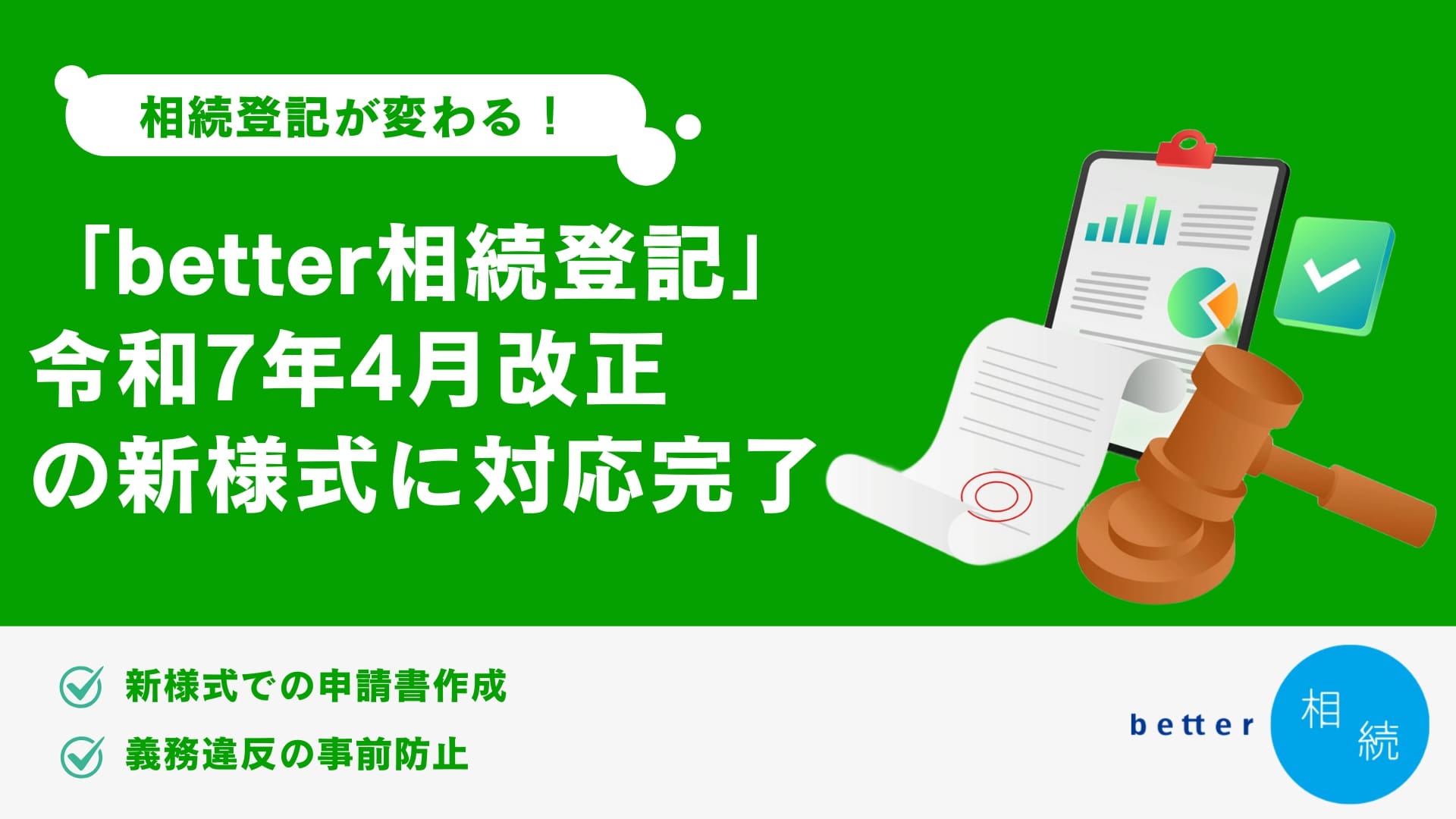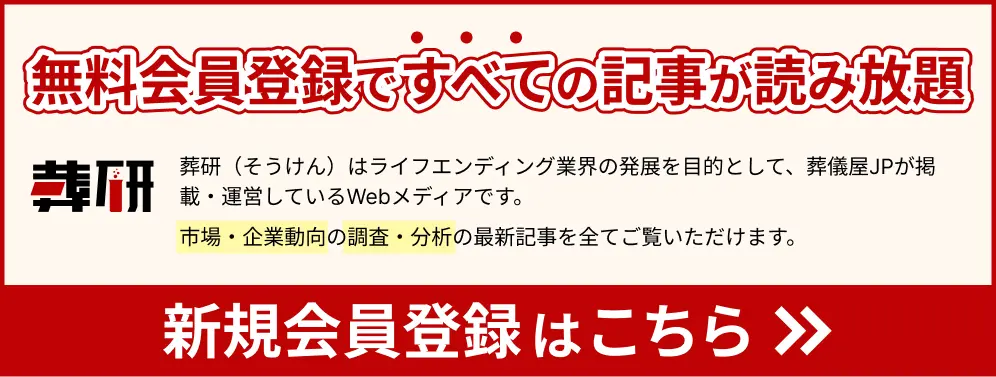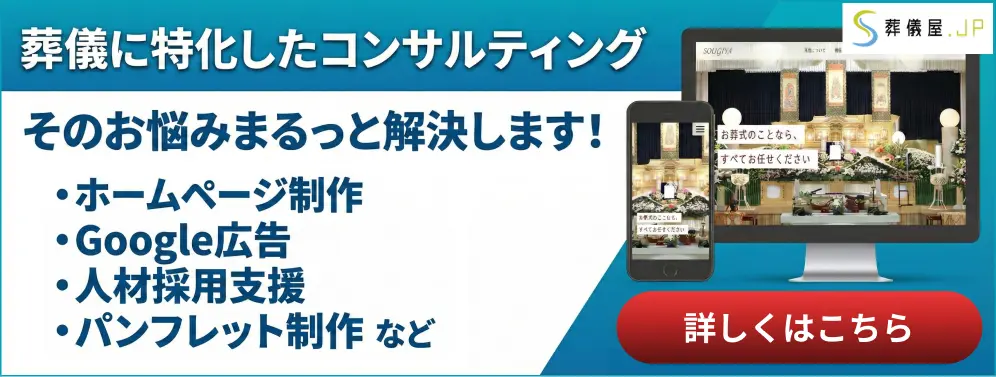辻・本郷 ITコンサルティング株式会社が提供するクラウドサービス「better相続登記」で、令和7年4月21日以降申請用の新様式で申請書作成が可能となりました。
令和8年4月1日の変更登記義務化を踏まえた改修となっています。
辻・本郷 ITコンサルティング株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:黒仁田 健)は、当社が提供しているクラウドサービス「better相続登記」において、令和7年4月21日以降申請用の新様式での申請書作成が可能となりましたので、お知らせいたします。
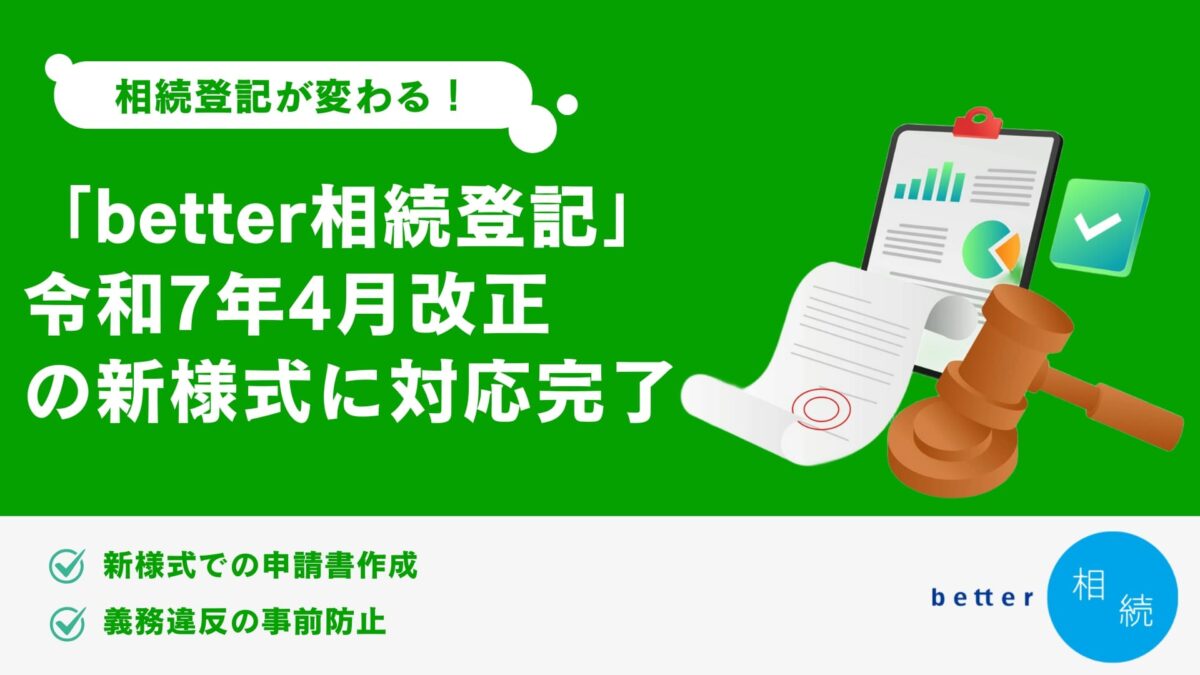
◾️背景
相続した土地・建物について、不動産登記簿の名義を変更する手続きを「相続登記」といい、2024年(令和6年)3月以前まで義務化はされていませんでした。
義務化されていないことによって、相続登記がされないケースも多々あり、不動産登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、今日の社会問題になっています。
このような背景を受け、令和6年4月1日より相続登記の手続き自体が義務化されることとなり、さらに令和8年4月1日より、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられることになりました。
また、この義務の負担軽減のため、所有者が氏名・住所の変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みが開始されます。
しかしながら、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者が氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出る必要があります。そこで、上記の変更登記の義務化や職権での登記を踏まえて、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際に、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことになりました。
検索用情報の申し出を済ませておくことで、令和8年4月1日以降の義務化の後、氏名・住所の変更を行ったとしても、法務局が氏名・住所の変更情報を取得した場合は職権による変更登記を行うことで義務履行済みとされるため、義務違反に問われることがなくなる便利な制度となります。
【今回のシステム改修について】
上記背景を踏まえ「better相続登記」では、令和7年4月21日以降の申請で必要となる新様式での対応が可能となりました。
具体的には、不動産取得者(不動産を相続する方)の
・氏名フリガナ
・生年月日
・メールアドレス
の記載が必要となりますが、これらの情報が記載された新様式での申請書作成が可能となります。
▶ 「better相続登記」のご紹介

「better相続登記」は、画面の案内に従って入力を進めるだけで、申請に必要な書類が自動でリストアップされ、相続登記申請書や遺産分割協議書を自動で作成することができます。また、法務局への提出方法までシステム内で詳細に解説しています。
必要書類のリストアップ、相続登記申請書や分割協議書の作成、申請手順まで「better相続登記」ひとつで完結いたします。
- 図解付きで相続登記申請までの手順を解説
- 入力項目に詳しい解説付き
- 必要書類には取得方法を明記
- 登記申請書や委任状を自動で作成
- 登録免許税を自動で計算
- 遺産分割協議書を自動で作成■「better相続登記」ご案内ページ:https://jp-better.com/lp/touki/
◾️better相続とは?
「better相続」は、全ての相続問題を解決する相続プラットフォームになることを目指しています。「better相続」に登録すると、誰でも、簡単に、相続手続きができます。従来は行政書士や司法書士、税理士等の専門家にそれぞれ相談する必要があった相続手続きを、一気通貫でできるのが「better相続」の強みです。
相続が発生して何から手を付けていいか分からない方がはじめに取り組む「相続手続きの概要把握」や、相続手続きの中でも税理士や司法書士など専門家に依頼することが多い「相続税申告」「不動産の名義変更」。これらをWEBブラウザで、簡単に、自分で行うことができるサービスを提供しております。
また、相続が発生したときに備えるための「生前対策」や、相続した不動産の「売却」についても相談することが可能です。
「better相続登記」の他に、以下のようなサービスがございます。
(1)better相続手続きガイド

「いつまでに何をするのか」「書類は何が必要?」
そのようなお悩みを解決する無料のWEBサービスです。
簡単な診断に回答すると、必要な相続手続きをリストアップ。役所以外の手続きも網羅しているので抜け漏れなく相続手続きを進めることができます。
手続きの進め方や必要資料なども詳しく解説しているほか、将来の相続に向けた対策などのご相談も無料で行えます。
パソコンやスマホはもちろん、資料を印刷して利用することもできますので、紙で確認したい方にもおすすめです。
◾︎URL:https://lp.guide.jp-better.com/
(2)better相続申告

相続税の申告を自分で簡単に完結できるWEBサービスです。
財産の洗い出しから必要資料のリストアップ、財産・土地の評価、申告書の作成・提出手順までこれ一つで完結します。
詳しい解説をシステム内に用意しているため、初めての方でも迷わずに手続きを進めることができます。
税理士へ依頼すると数十万円~数百万円かかる費用を大きく抑えられる可能性があります。
無料でお試しいただけますので、まずはご自身で申告できるかご検討ください。
自分で手続きを進めるのが難しいような場合は、税理士へ依頼することも可能です。
弊社がご紹介する税理士へ依頼した場合には、システム利用料をご返金します。
◾︎URL:https://jp-better.com/lp/shinkoku/
(3)better相続生前対策

「どんな相続財産があるのか、今のうちに相続人へ伝えておきたい」「将来相続税が発生する見込みだが、税金を少しでも抑えるために何か対策しておきたい」等、今後発生する見込みの相続や、将来のご自身の相続についてのお悩みがございましたらご相談ください。
最適な対策方法をご案内いたします。
また、相続が発生した場合についても、今回相続した財産を含めて、大切な家族にどのように遺していくべきか、どのように遺してもらいたいか、ご検討いただくのによいタイミングです。場合によっては、遺産分割の方針が大きく変わることもあるためです。
なぜ”いま”検討することが重要かという点から、お客様にあわせた対策のご提案まで、無料でご相談いただけます。
◾︎URL:https://lp.estate-planning.jp-better.com/
(4)better相続不動産売却

相続登記件数9,500件以上の実績をもつbetter相続が早く・高く売却を行うためのお手伝いをいたします。
売却を検討中の物件と同じエリアで、いまどのような物件がいくらで売り出されているのか、また直近の取引事例のご紹介も可能です。
遺産分割協議にあたっても、不動産の「相続評価額」と「市場価格」は異なるため、
相場を把握された上で分割方針を相談することで、後々のトラブル防止にも繋がります。
すぐにご売却というケースでなくとも、相場や査定額を把握しておきたい等、お気軽にご相談ください。相談は無料ですので、安心してお問い合わせくださいませ。
◾︎URL:https://lp.real-estate-sale.jp-better.com/
会社概要
- 辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 概要
- 代表者 :代表取締役社長 黒仁田 健
- 所在地 :東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル5F
- 事業内容:経営管理部門全般に係るコンサルティング、ソフトウェア・ハードウェア販売/導入支援、経理/人事アウトソーシング、個人向け相続及び会計事務所向けWEBサービスの開発・運営
- URL :https://ht-itc.jp
このリリースに関するお問い合わせ先
辻・本郷 ITコンサルティング株式会社
better相続登記お問合せ窓口
Email:souzoku-info@jp-better.jp