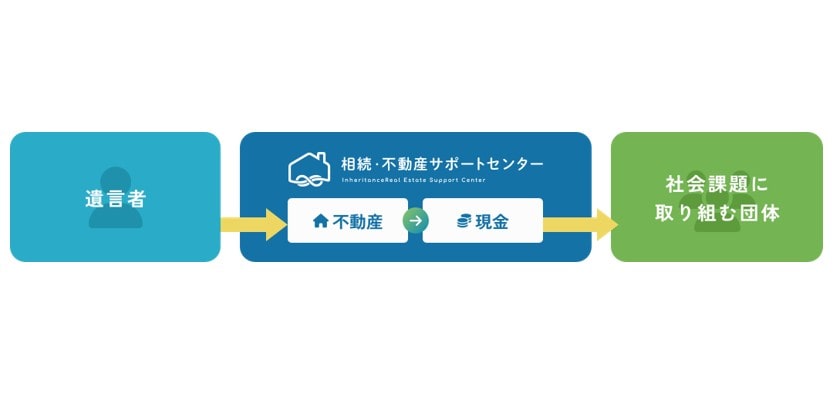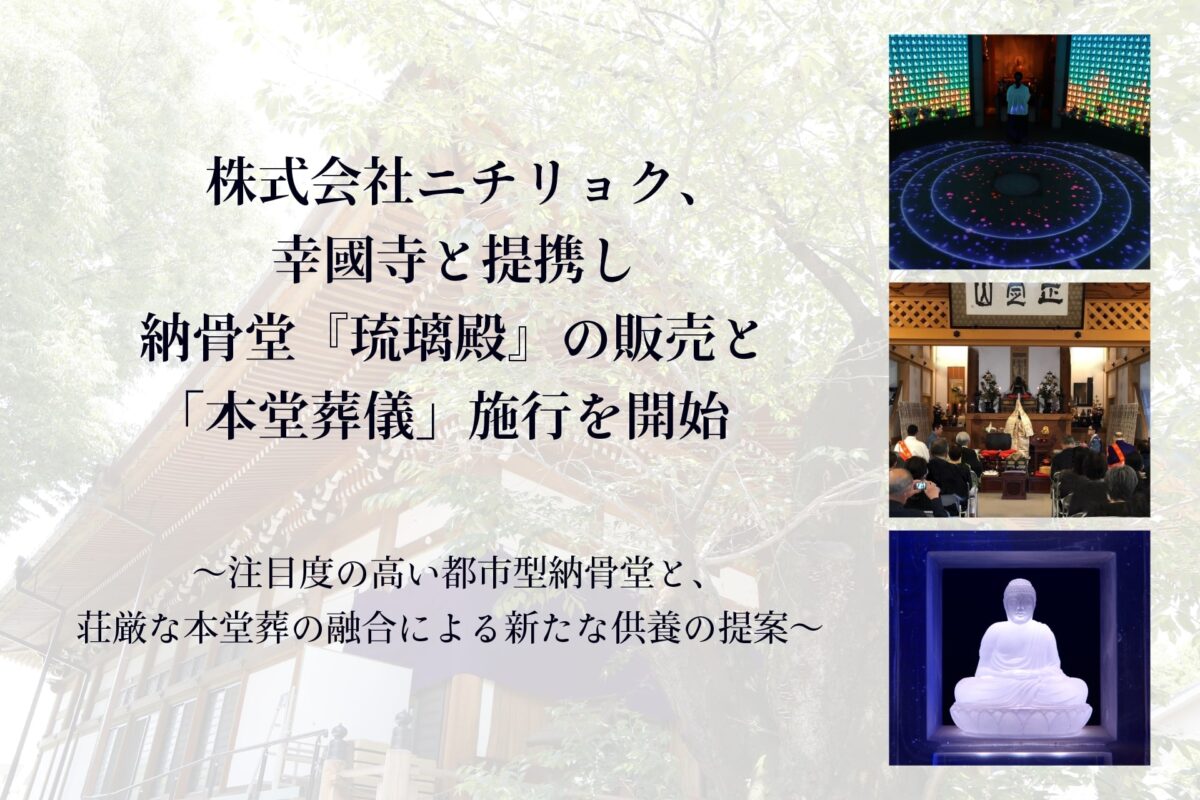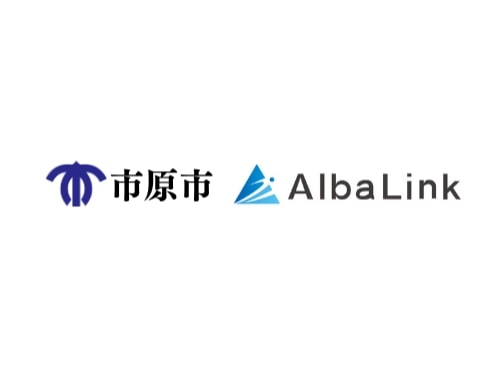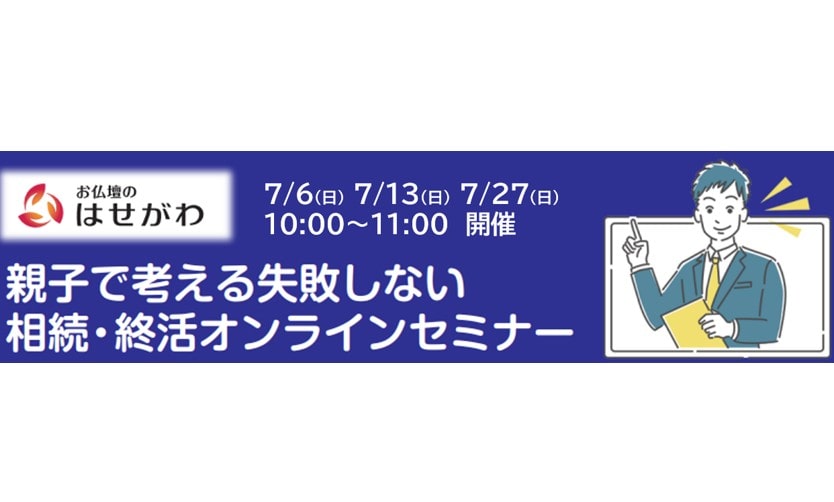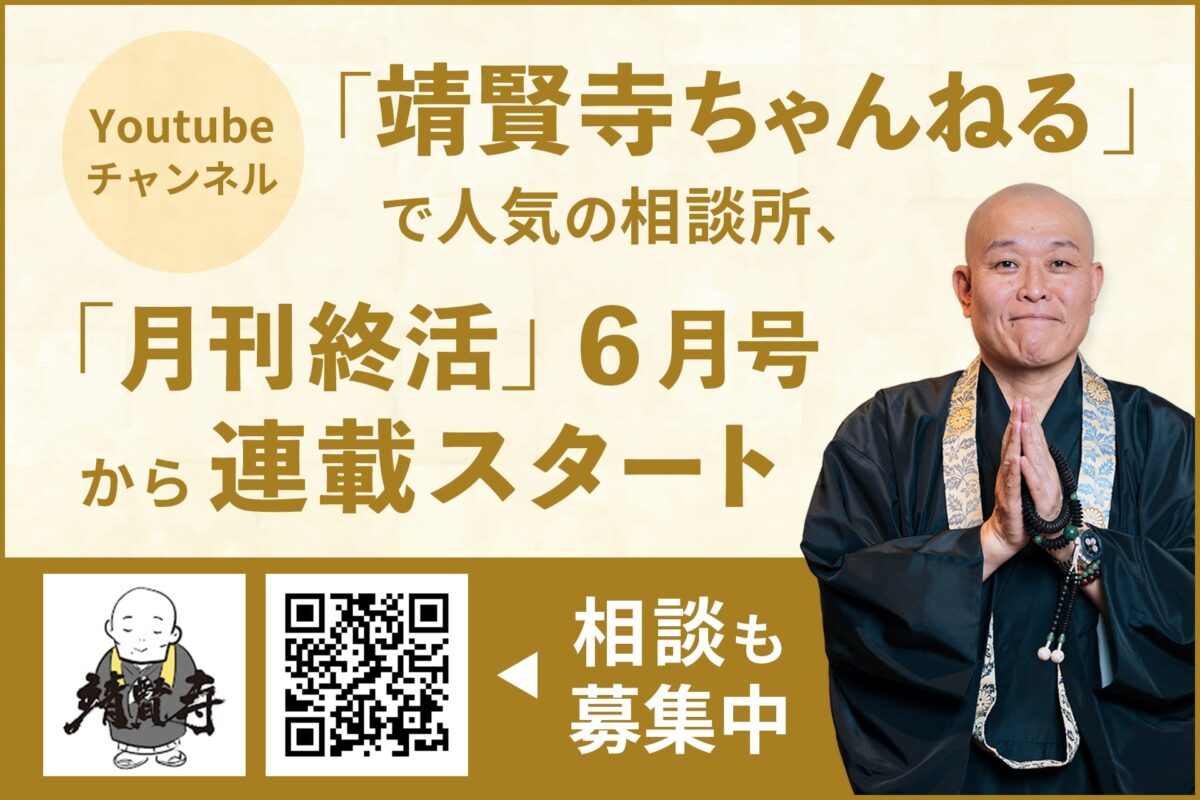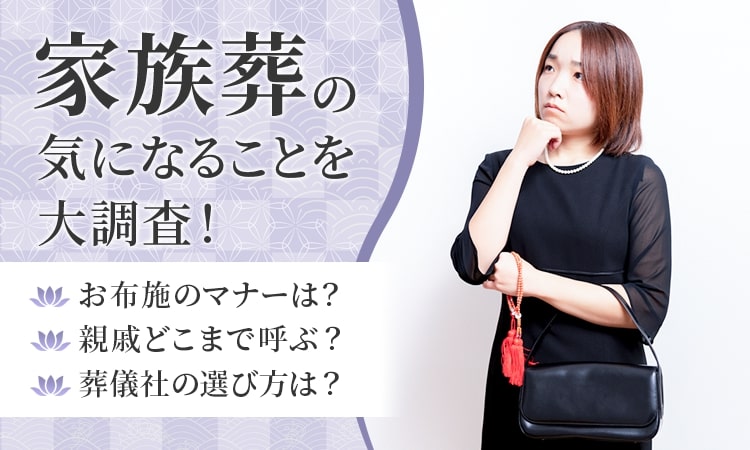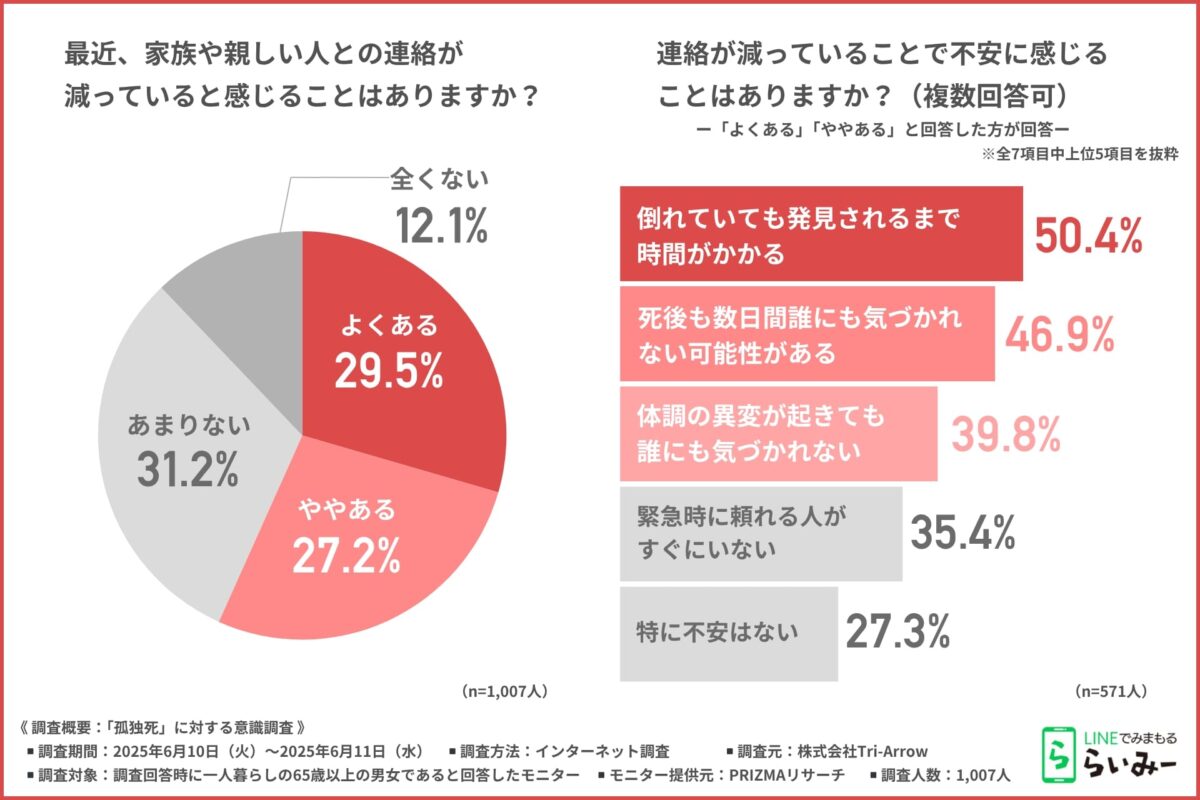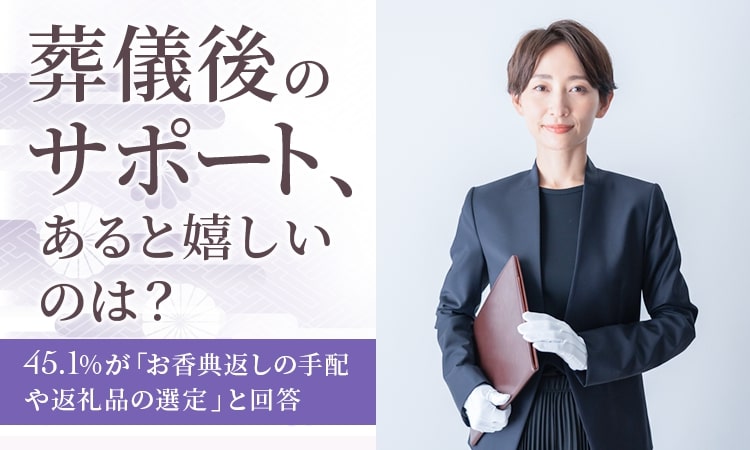葬儀市場の構造
葬儀市場は戦後の高度経済成長期とは平成の30年間で大きく変化した。
(参照)格差社会の葬送https://souken.info/himonya3
社会構造が「一億総中流」社会から「格差社会」に大きく変わっている。
それが葬儀市場に影響していることを顕著に示しているのが「家族葬」の流行である。
葬儀市場は、「人並み」「平均」を論じる時代ではすでになく、構造的に大きく分化している。
「格差社会の葬送」で示した葬儀一式費用の分布(日本消費者協会「第11回葬儀についてのアンケート調査」2017【平成29】年1月発表に基づく)を再掲する。
・1~500,000円 21.0%(低)
・500,001~1,000,000円 28.3%(やや低)
・1,000,001~1,500,000円 24.6%(中)
・1,500,001~2,000,000円 14.3%(やや高)
・2,000,001円以上 11.9%(高)
葬儀費用の観点だけで見ると葬儀市場は単一ではなく、「低」「やや低」「中」「やや高」「高」の5つに分かれている、と見るべきだろう。
「中」が多いわけではない。「中」は全体の4分の1にすぎない。
高所得は約1割、平均以下が6割の世界
件数的には「低」「やや低」層が増加している。
世帯所得分布においては平均所得金額560万2千円を下回る世帯が61.5%を占めている(2017(平成29)年「国民生活基礎調査」)。
葬儀費用においても同様で、平均額1,214,000円を下回るのが約6割の58%を占めている。
年間所得が1千万円を超えるのはわずか12.6%でしかない。
葬儀でも200万円以上を消費するのは約1割にすぎない。
一般層を対象とした事業者が死亡数の増加により取扱件数は増加しているのに、中以下の層の単価低下を受けて、売上が思うように伸びず、利益を減少させている例は少なくない。