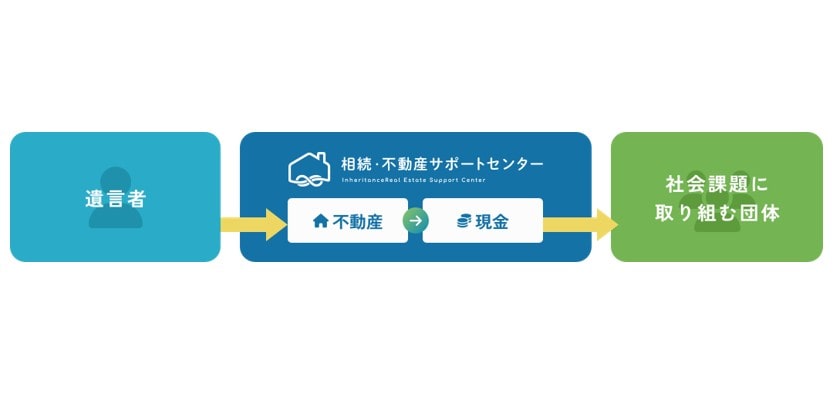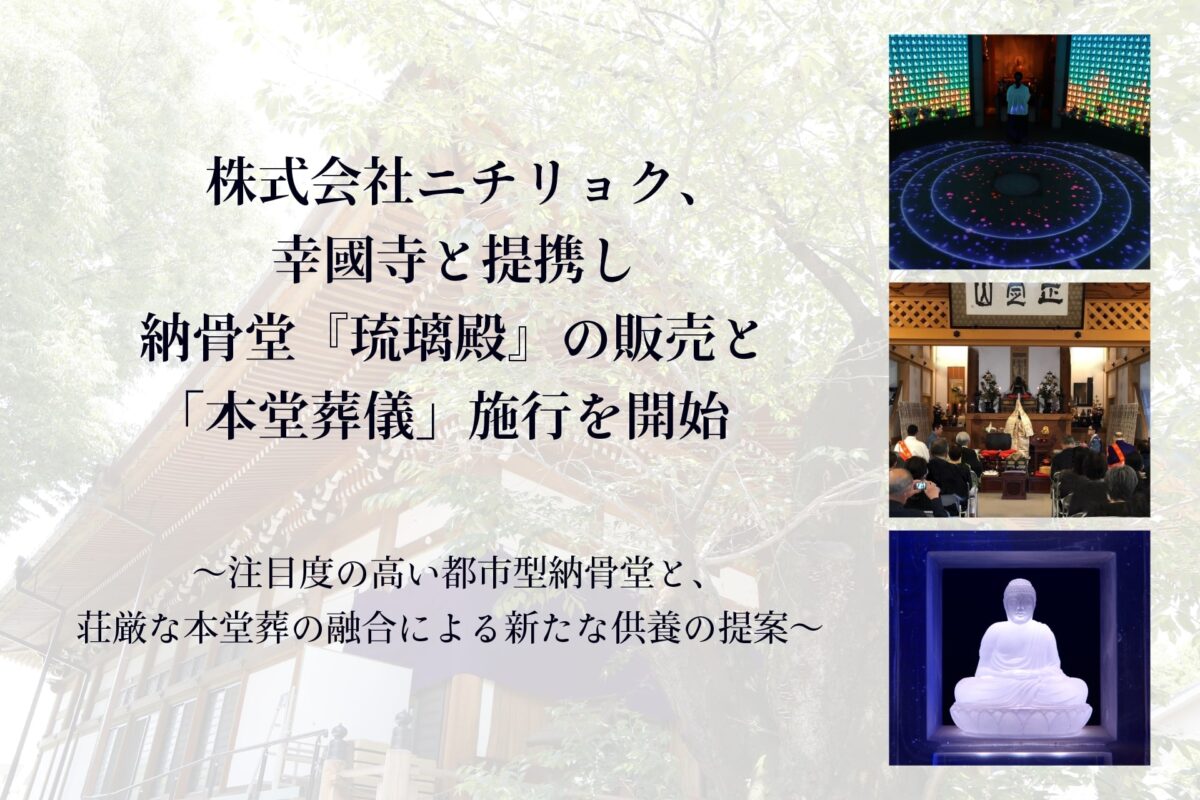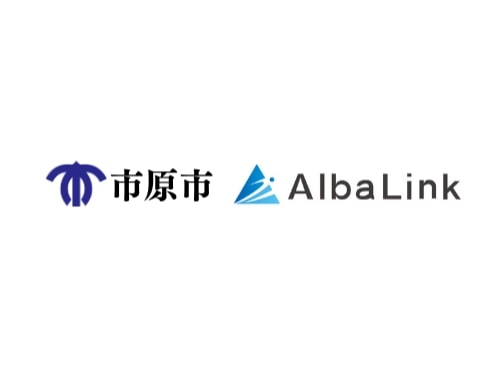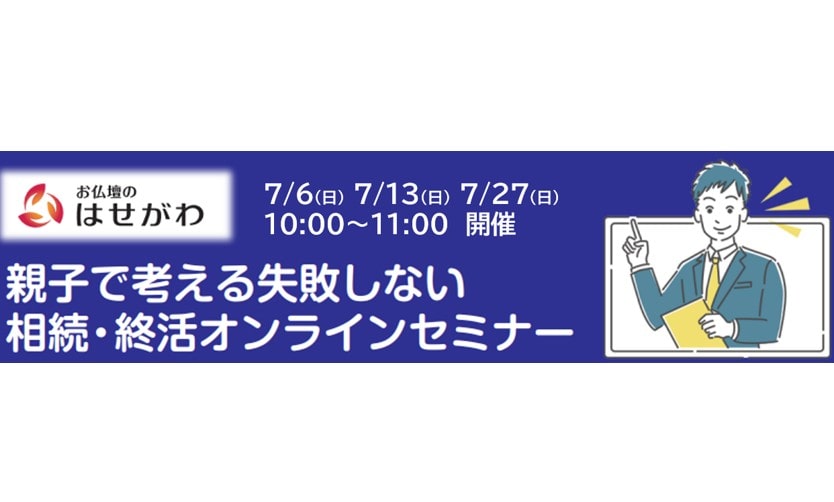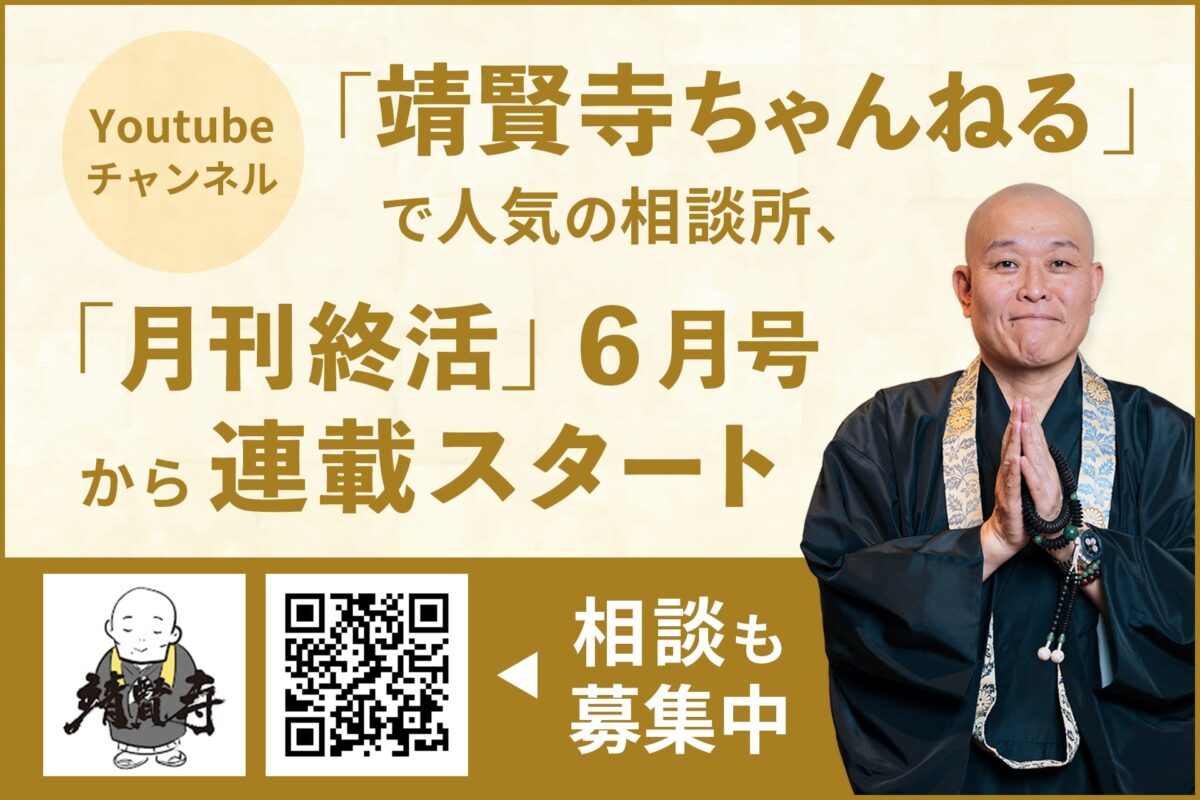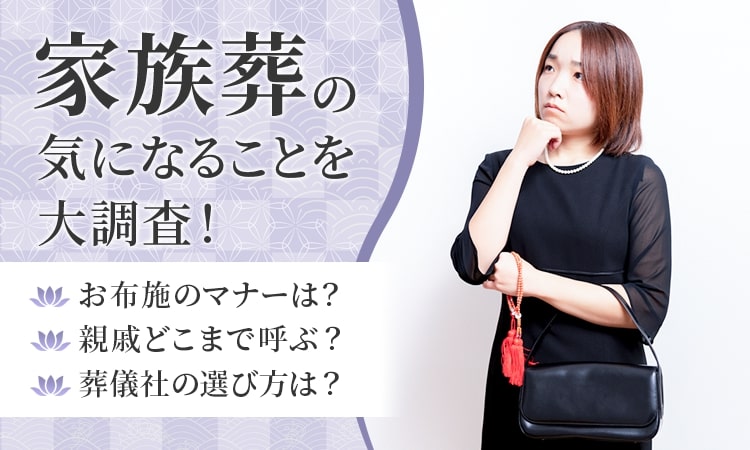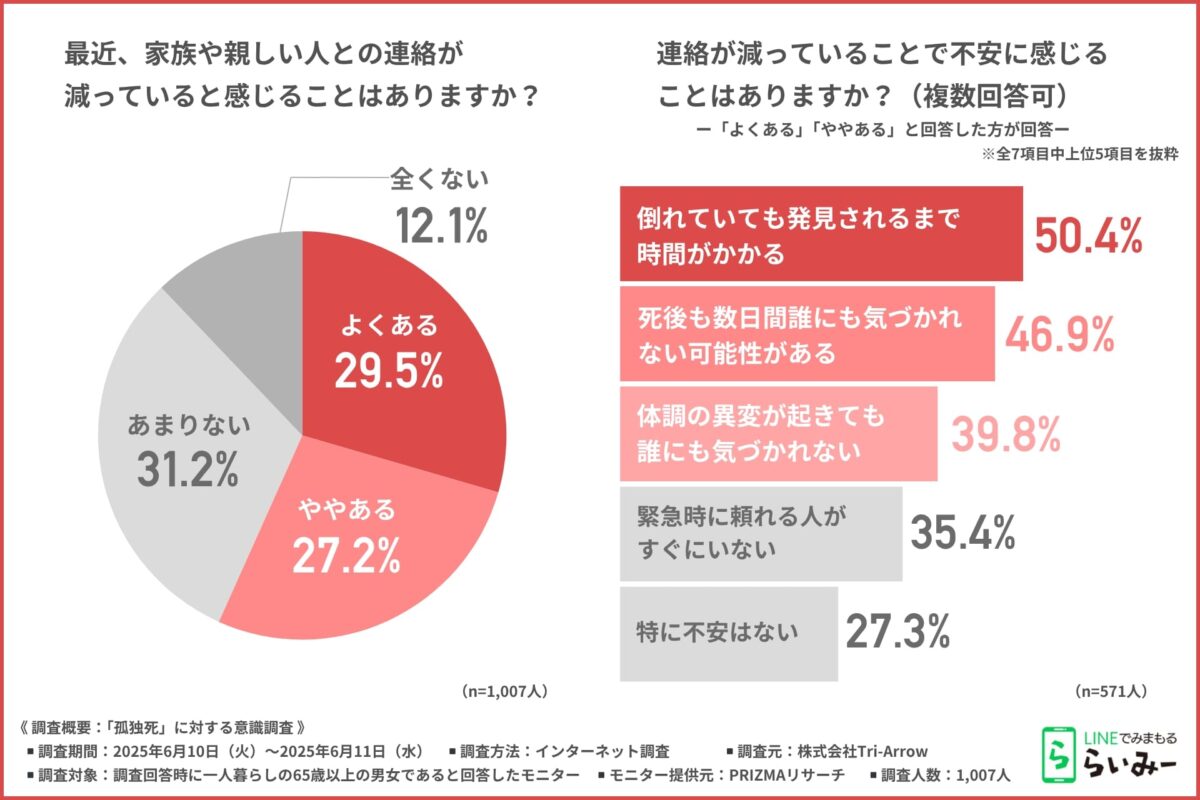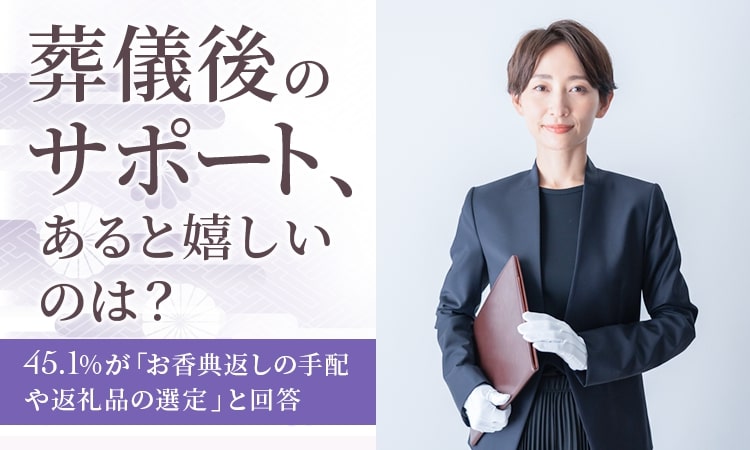邸宅葬とは1棟1組限定のゲストハウスで行う葬儀

近年、邸宅葬用の会館が全国各地に生まれている。邸宅葬とは、ゲストハウス風の施設で行う1棟1組限定の葬儀を指す。既存施設で例えるなら、遺族控室に小さな葬儀場を隣接させ、家としての機能をプラスして一棟とし、そこで通夜から葬儀までを終わらせてしまうイメージだ。
2000年代後半から家族葬ブームが始まり、今では会葬者が50人を割るような小規模葬儀が当たり前になってきた。葬儀をせず火葬のみを済ませる直葬も、都市部では2~3割の遺族が選ぶといわれている。すでに、社縁・地縁・血縁者すべてが集う葬儀は過去のものになり、死者は縁の濃い人々だけで見送る時代を迎えたといっていいだろう。
近親者だけの葬儀となると、そこにはゆったりと気兼ねのない空気が流れる。大人数の会葬者を迎えるための大きな祭壇も、改まった受付も、大容量の駐車場も必要ない。大事なのは、故人を見送ることに集中できる空間の提供だ。それを叶えるのが邸宅葬だと気づいた葬儀社が、2010年代に入ってから次々に邸宅葬用の会館を建設している。
邸宅葬の特徴
邸宅葬の特徴は、以下の3つに集約される。
- 自宅よりも上質な空間で、便利なサービスを受けながら「自宅葬」ができる
- 通夜から葬儀までワンストップサービスが可能
- 会葬者は遺族と近しい親族の10~50名を想定
それぞれ解説したい。
上質な空間と便利なサービスのある「自宅葬」
邸宅葬は、いわば「自宅とは違う一軒家を借りて行う自宅葬」だ。しかし、だからといって会館が自宅と同じようなつくりでは儀式の特別感がなく、満足度に欠ける。そこで、邸宅葬で使用する一軒家は、まるで高級ホテルの一室のようなラグジュアリー感を漂わせているのが一般的だ。ミニキッチンやバスルームも、一時的な仮住まいのための簡単なつくりではなく、新築の一軒家に負けないシステムを備えている。まさに「邸宅」を彷彿させる施設だ。
また、「自宅葬」といえば、自分の家というまたとないくつろぎの空間で葬儀ができる反面、掃除やかたづけなどの準備、会葬者の湯茶接待に追われてしまうのが一般的だ。しかし、邸宅葬であれば、スタッフが全てのサービスをいわば代行してくれる。それはまるで、グランピングの葬儀バージョンといってもいいかもしれない。グランピングとは、炊事やテントの設営などの準備を全てサービス側が引き受けてくれるキャンプのこと。くつろぎの自宅葬が、より一層上質な空間で、面倒なことを一切せずに叶えられるのだ。
通夜から葬儀までワンストップサービスが可能
邸宅葬は、一棟貸し切り型のハウスウェディングに例えられることもある。しかし、ハウスウェディングは「1日1組貸し切り型」。対して邸宅葬は、短くても2日は貸し切ることになる。通夜から翌朝の葬儀まで、ワンストップサービスが可能なのだ。遺族側の予算と会館側の予定の兼ね合いがつけば、病院からすぐに邸宅葬会館へ移り、そのまま火葬まで滞在することも可能だ。
会葬者は遺族と近しい親族の10~50名を想定
ラグジュアリー感漂う邸宅とはいえ小ぢんまりとした一軒家であり、またそのコンセプトからも想定している会葬者はそれほど多くない。くつろぎの中心となるリビングは、遺族と近しい親族の5名から10名ほどがゆったり過ごせるよう設計されている。式場は収容人数が多くとも50名で、完全に家族葬向けのつくりだ。
邸宅葬の流れ
このコンテンツは会員様限定です。
メールアドレスを登録して仮会員になっていただくと、2記事限定で全文をご覧いただけます。
さらにユーザー情報を登録して葬研会員(無料)になると、すべての記事が制限なしで閲覧可能に!
今すぐ会員登録して続きを読む
新規会員登録
葬研会員の方はコチラ
ログイン
 近年、邸宅葬用の会館が全国各地に生まれている。邸宅葬とは、ゲストハウス風の施設で行う1棟1組限定の葬儀を指す。既存施設で例えるなら、遺族控室に小さな葬儀場を隣接させ、家としての機能をプラスして一棟とし、そこで通夜から葬儀までを終わらせてしまうイメージだ。
2000年代後半から家族葬ブームが始まり、今では会葬者が50人を割るような小規模葬儀が当たり前になってきた。葬儀をせず火葬のみを済ませる直葬も、都市部では2~3割の遺族が選ぶといわれている。すでに、社縁・地縁・血縁者すべてが集う葬儀は過去のものになり、死者は縁の濃い人々だけで見送る時代を迎えたといっていいだろう。
近親者だけの葬儀となると、そこにはゆったりと気兼ねのない空気が流れる。大人数の会葬者を迎えるための大きな祭壇も、改まった受付も、大容量の駐車場も必要ない。大事なのは、故人を見送ることに集中できる空間の提供だ。それを叶えるのが邸宅葬だと気づいた葬儀社が、2010年代に入ってから次々に邸宅葬用の会館を建設している。
近年、邸宅葬用の会館が全国各地に生まれている。邸宅葬とは、ゲストハウス風の施設で行う1棟1組限定の葬儀を指す。既存施設で例えるなら、遺族控室に小さな葬儀場を隣接させ、家としての機能をプラスして一棟とし、そこで通夜から葬儀までを終わらせてしまうイメージだ。
2000年代後半から家族葬ブームが始まり、今では会葬者が50人を割るような小規模葬儀が当たり前になってきた。葬儀をせず火葬のみを済ませる直葬も、都市部では2~3割の遺族が選ぶといわれている。すでに、社縁・地縁・血縁者すべてが集う葬儀は過去のものになり、死者は縁の濃い人々だけで見送る時代を迎えたといっていいだろう。
近親者だけの葬儀となると、そこにはゆったりと気兼ねのない空気が流れる。大人数の会葬者を迎えるための大きな祭壇も、改まった受付も、大容量の駐車場も必要ない。大事なのは、故人を見送ることに集中できる空間の提供だ。それを叶えるのが邸宅葬だと気づいた葬儀社が、2010年代に入ってから次々に邸宅葬用の会館を建設している。