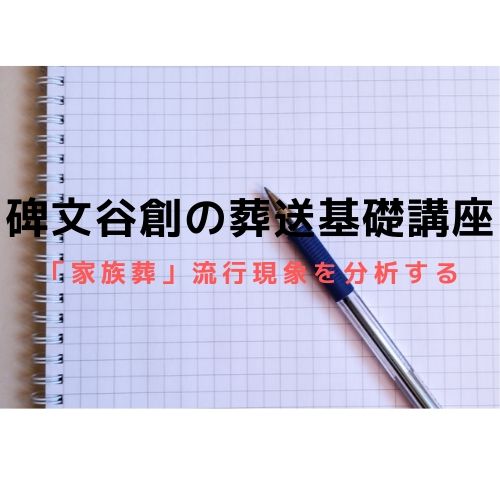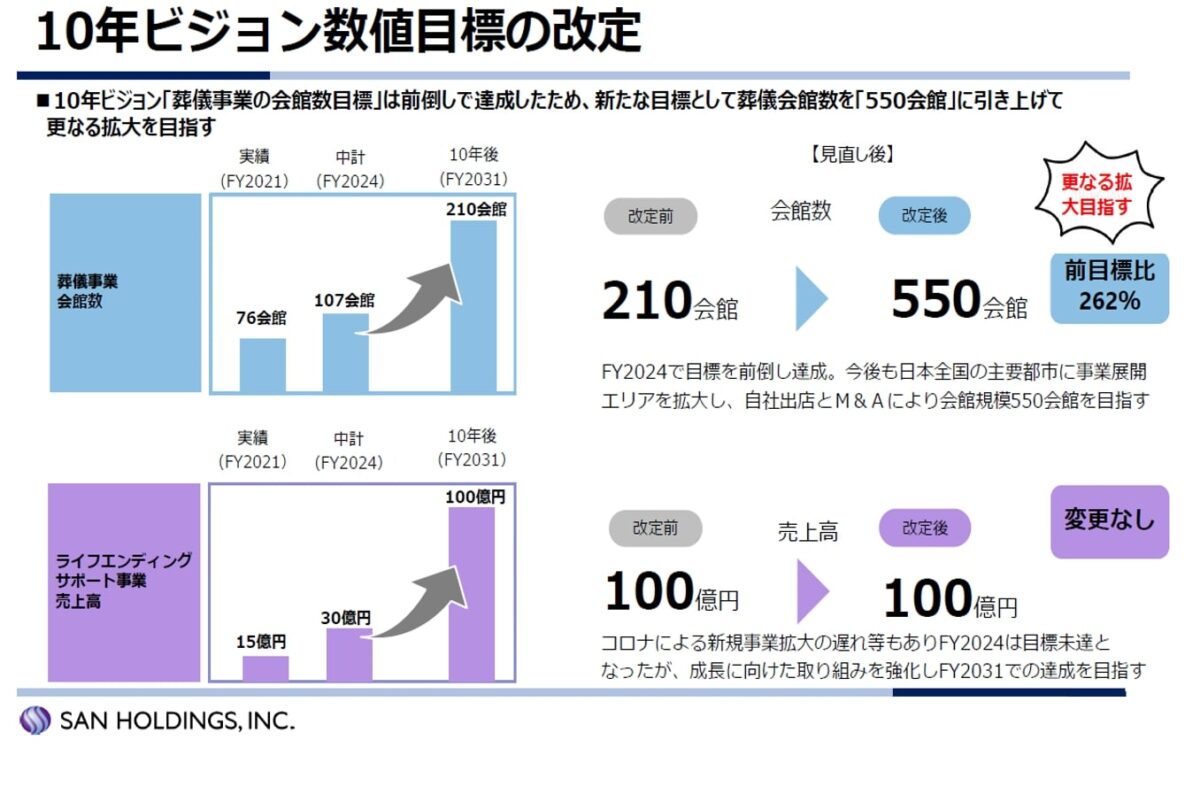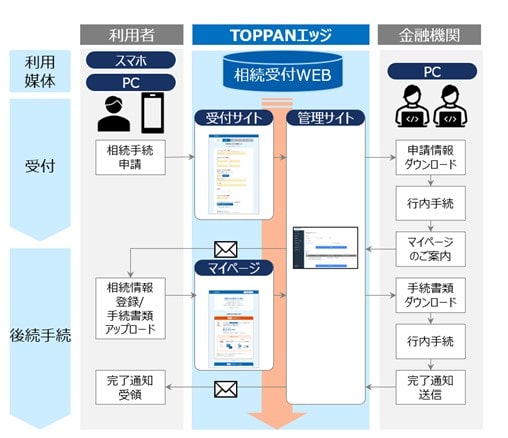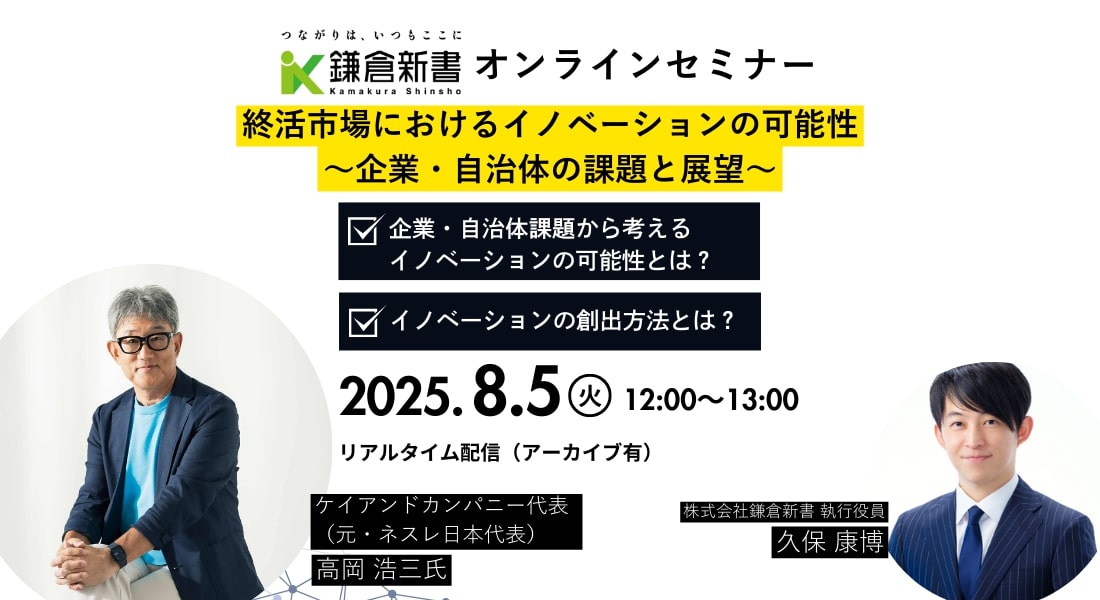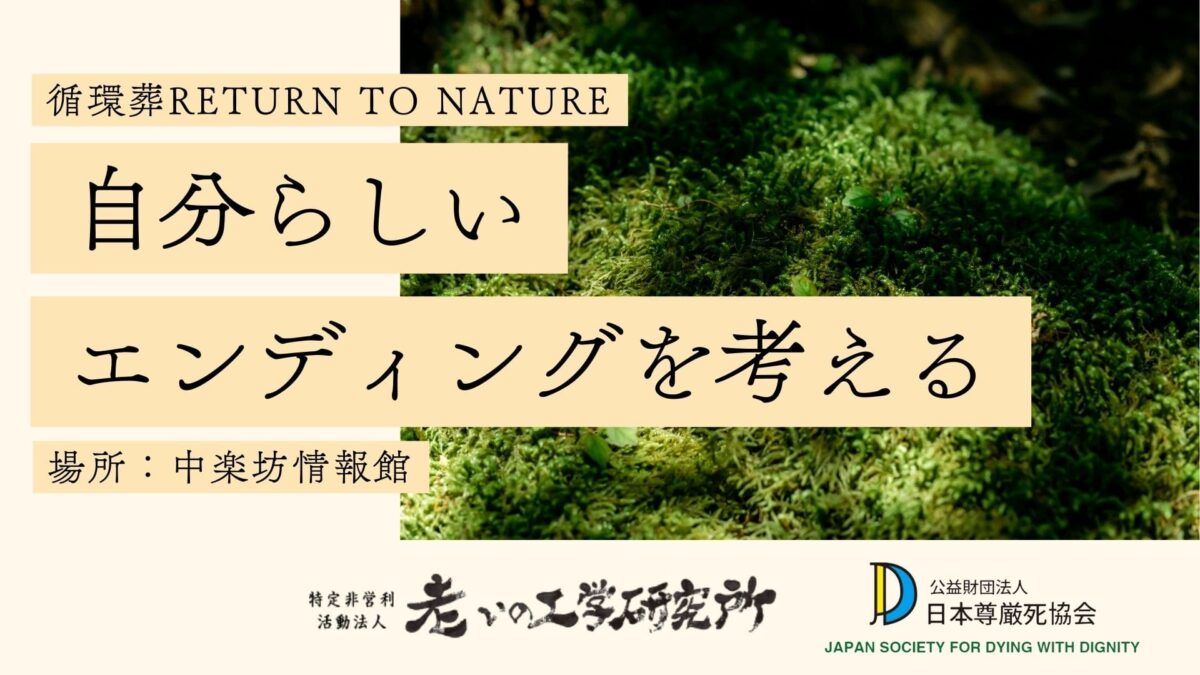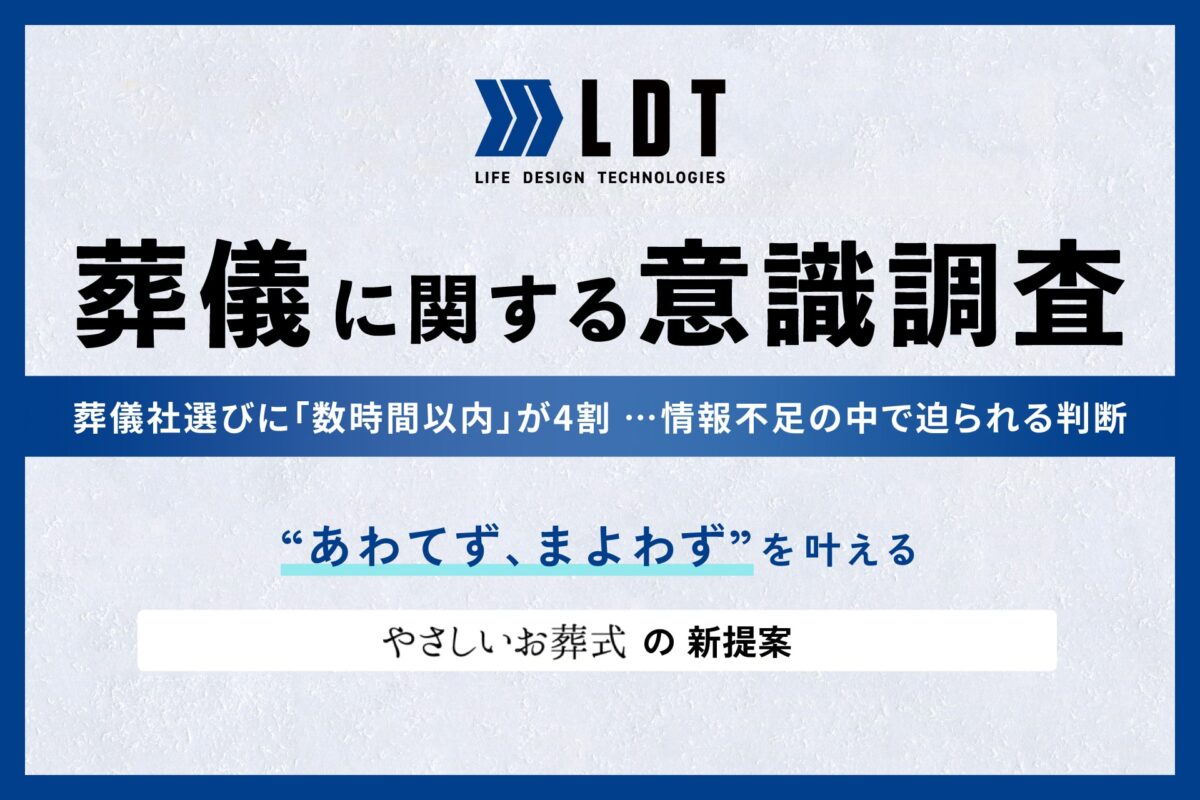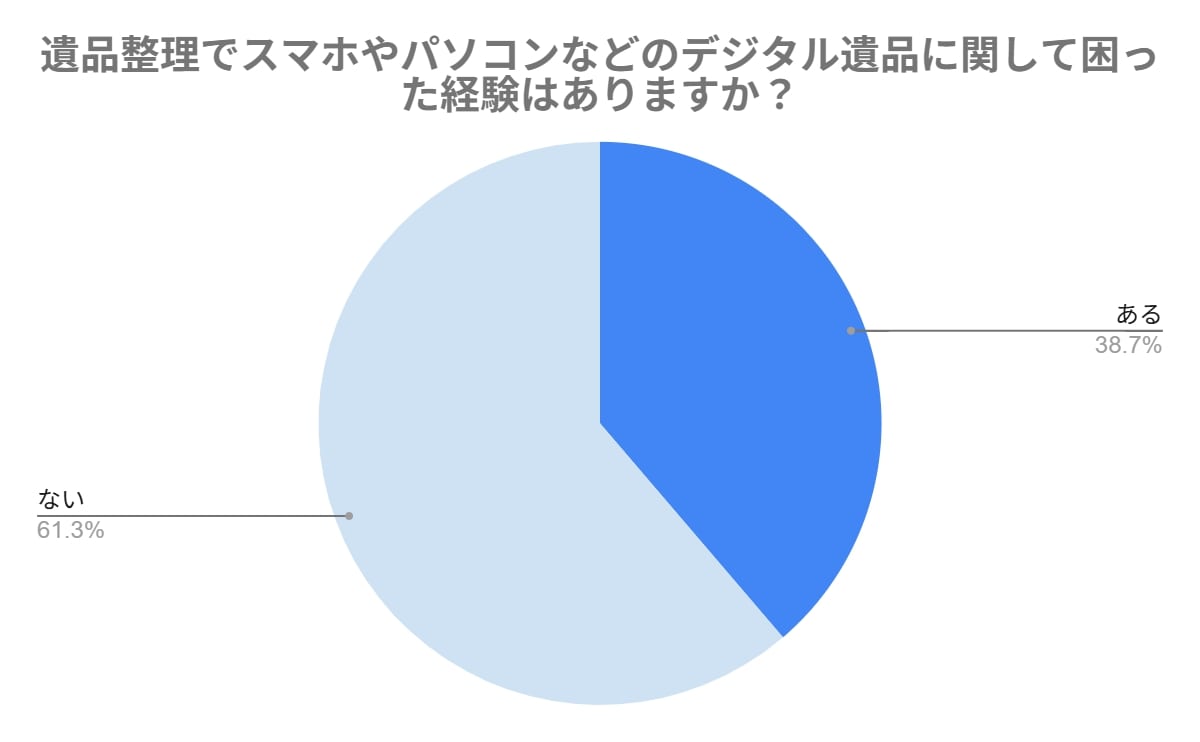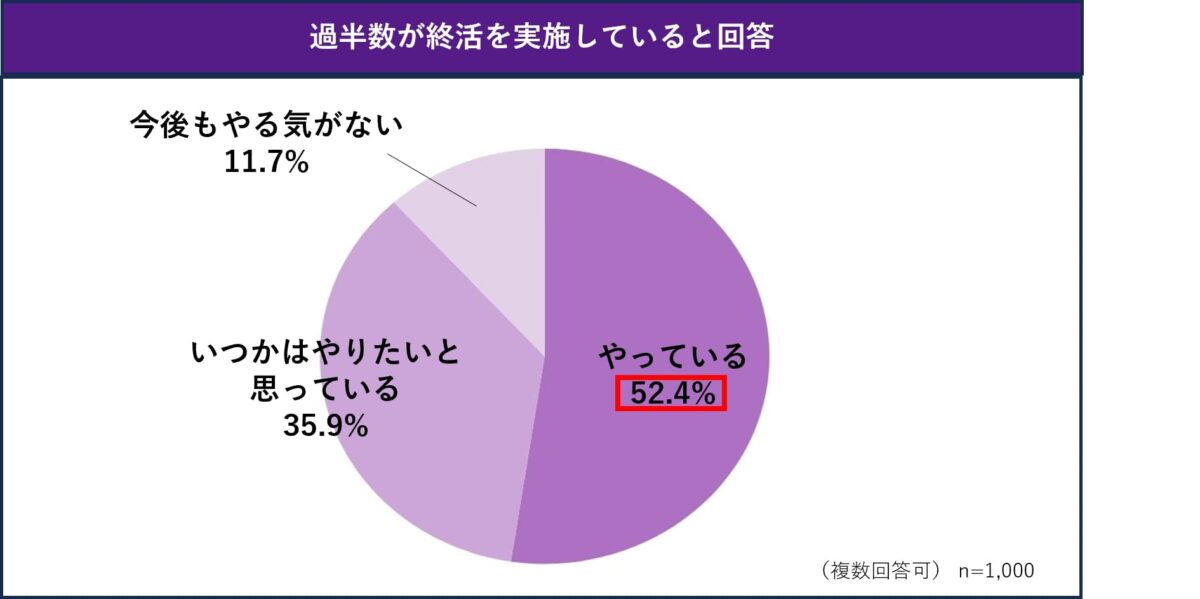「家族葬」が3分の2を占める時代
「葬式の個人化」は、1995(平成7)年に始まり2008(平成20)年のリーマン・ショック(リーマン・ブラザーズの経営破綻を契機とした世界規模金融危機)によって明確になった。
「葬式の個人化」を象徴するのは1995年に始まった「家族葬」である。
「家族葬」という用語は未定義ながら、現在行われている葬式の3分の2が「家族葬」とされている。
葬式の個人化の背景には「超高齢社会の到来」、「家族の変容・分散・縮小」、「地域共同体の弱化」、「企業共同体の崩壊」その他が深く関係しているが、ここでは「家族葬現象」に限定してみてみよう。
長谷川町子さんと渥美清さんの「密葬」
最初に「家族葬」があったわけではない。まず「密葬」志向が始まった。
長谷川町子さんの場合
有名人の例をとれば「サザエさん」の作者で知られる長谷川町子さん。
1920(大正9)年生まれの長谷川町子さんは1992(平成4)年5月27日に72歳で死亡。
但し、その死亡は約1か月間秘された。
「密葬された」と報じられた。
長谷川町子さんの場合、その後には本葬もお別れの会も行われることはなかった。
だが、死亡公表後はマスメディアで大々的に報道された。
その様相はまさに「マスメディア葬」であった。
政府は国民栄誉賞を贈った。
渥美清さんの場合
1996(平成8)年8月4日に68歳で死亡した俳優・渥美清さんの葬式は、菩提寺の僧侶により家族数人だけによる「密葬」として行われたという。
渥美清さんは山田洋次監督映画『男はつらいよ』の「寅さん」で知られた国民的俳優。
「密葬」は渥美本人の遺志によるものとされ、撮影現場やスタッフに死亡が知らされたのも死亡から2日後のことであった。
松竹からの死亡の公表は3日後。すでに密葬は終え、火葬がされていた。
渥美清さんは国民的俳優だったからこれで終わるわけにはいかなかった。
映画撮影現場である葛飾区等ではファン独自の追悼が盛り上がった。
死亡後約1か月後の8月13日、松竹大船撮影所で「寅さんのお別れの会」が開かれ、4万人を集めた。
政府は国民栄誉賞を贈った。
長谷川町子さん、渥美清さんの例以前に80年代の後半期より「密葬」人気は生じていた。
長谷川町子さん、渥美清さんの密葬が社会的に大きく報道されたことから、葬式は個人的であるべきとする人たちの背中を押し、葬式の個人化の流れを加速させる効果があった。