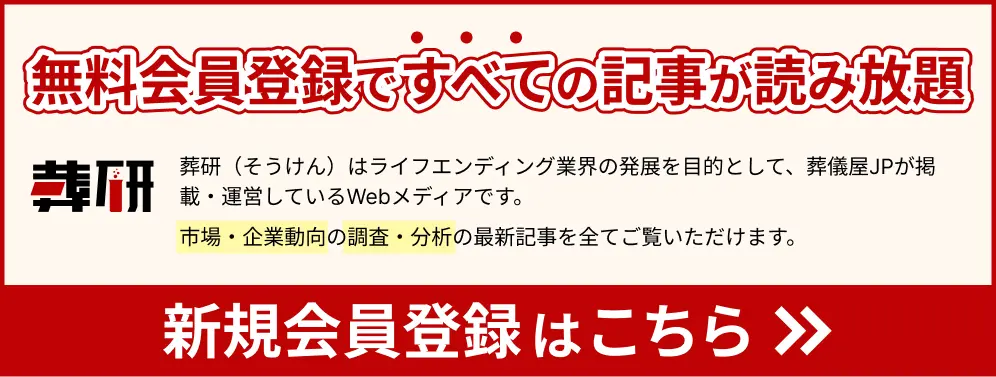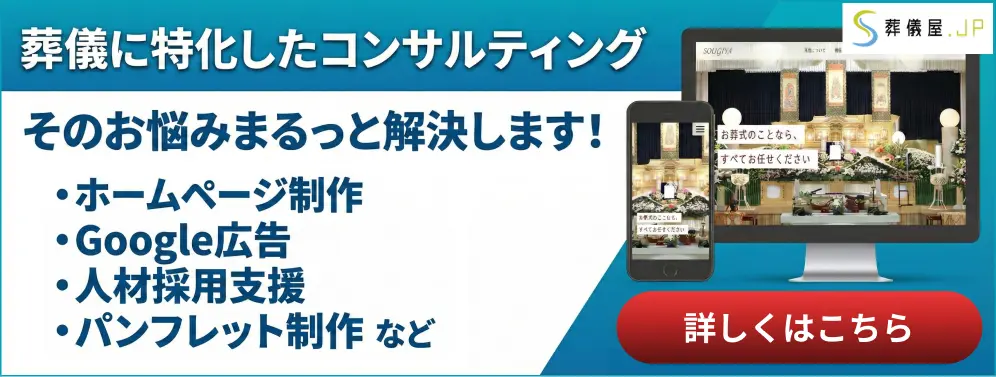この記事を音声で聴く
「供養業界」という言い方
いつからか、そんな昔ではなく、2004(平成16)年以降であろうが、葬儀業、墓石霊園業、仏壇仏具業等を「供養業界」という言葉で括られることが多くなった。
もっとも世間で一般化しているわけではなく、あくまで「業界」においての話。
「供養」とは仏教では「真心をもって仏に供え物をする」という意味だろうが、一般的には(つまり民間の理解では)「死者を供養する=弔う」という意味として使われる。そこから葬儀、墓石・霊園、仏壇・仏具は「弔いに関係する事業」ということでは同じとし、「供養業界」と名づけたのであろう。
「供養業界」という言葉の創始者はわからないが、広めたのは鎌倉新書である。
同社の設立は1984(昭和59)年、仏壇仏具業界向け書籍の出版から。
同社の沿革によれば
2000(平成12)年には、全国の葬儀社検索、お葬式のマナーや葬儀に関する総合情報サイト「いい葬儀」を開始。
ネットに注目した事業展開としてはかなり早い。
2001(平成13)年には、月刊誌「月刊『仏事』」創刊号発売。
創設者である元社長が長く仏壇仏具関係の業界紙に携わっていたので、業界誌の発行を始めた。取扱い分野は、従来の仏壇仏具業界のみならず葬儀、墓石という関連業界を包含するものとあった。
当初の記事内容は「専門的」というよりは「業界情報」的傾向のものが多かった。
2003(平成15)年に、霊園・墓地・お墓探しの総合情報サイト「いいお墓」、
仏壇と仏壇店探しに関する総合情報サイト「いい仏壇」を開始。
ネットで葬儀、墓、仏壇の販売を斡旋する、という現在の主要業務を次々と立ち上げる。
その後の事業展開は目を見張るものがある。
2015(平成27)年にマザーズ上場、2017(平成29)年には東証一部上場。
仏壇・仏具、墓石、葬儀の業界情報誌を発行しながら同じ分野のネットを介した販売斡旋事業を展開する。
鎌倉新書にしてみれば分かれている業界を自らが取り上げる事業をまとめる用語を必要とし、これを「供養業界」としたのだろう。
どうかするとこれに全日本仏教会も加えようという勢いである。
もっとも同社のホームページでは「(1)ライフエンディングサービス事業:ライフエンディングに関わるサイト運営・情報サービスの提供 (2)ライフエンディング関連書籍出版事業:「月刊『仏事』」他」と記されている。
「終活」
「終活」という言葉について、私は過去に書いている。
2014年頃だろうが「『終活』ブームのコンテキスト」という題で雑誌『SOGI』に書いた。再掲する。
「終活」という言葉は『週刊朝日』が2009年に連載した記事名「現代終活事情」が最初と言われる。2010年6月に連載のまとめとして刊行された週刊朝日MOOK「2010終活マニュアル」のタイトルは『わたしの葬式 自分のお墓』となっているように「葬式」と「お墓」がメインテーマだった。
ちょうど2010年は島田裕巳『お葬式は、要らない』(幻冬舎新書)が刊行されてベストセラーになった年。葬式や墓についての要、不要論が話題になった。
しかし、2011年3月11日に発生した東日本大震災が一気にそのブームを消し去った。現実の大量死を体験して、死者・行方不明者への想い、その家族の想いの痛切さ、リアルな死の衝撃の大きさを感じさせるものであったからだ。
そうした状況を背景に、東日本大震災の発生で発表が延期されていた経産省の「ライフエンディング・ステージ」に関する報告書が同年8月に発表された。
報告書では生前の「老」で抱える終末期医療、介護の問題から死後の葬式、さまざまな事務処理、遺族のケア、お墓、遺産相続まで続くステージについて、バラバラではなく一連のプロセスと考え、ネットワークを組んで消費者をサポートできるシステムづくりを提言した。
『週刊朝日』の葬式、墓中心の「終活」に異を唱えた一人がファイナンシャルプランナーの本田桂子さん(当時、現在:弁護士)。中高年の遺言や相続の相談を手がけているなかで本田さんが提起したのが「老」の問題。超高齢社会になった日本社会でのリスク、認知症、延命治療、老後の生活資金、財産分与…等を加えた「終活」を提起した。本田桂子監修『終活ハンドブック』(PHP)が刊行されたのは、経産省の報告書発表と同年7月末のこと。同年8月には「おひとりさま」問題に取り組んでいたフリーライターの中澤まゆみさん『おひとりさまの終活―自分らしい老後と最後の準備』(三省堂)が刊行された。
この公の報告書、民の本田桂子さんらの提言にくらいついてきたのが司法書士、行政書士や保険関係の人たち。
「終活ブーム」を代表する終活カウンセラー協会は、2011年10月に第1回終活カウンセラー初級検定を実施。『終活の教科書』(タツミムック)を2013年6月に刊行。「終活」ブームは、ここ2年くらいに生じたブームである。
注視しておく必要があるのは、ここでの終活は「事業」である点。そして終活事情についての講演会等が事業として展開されている点である。
そしてこの背景には戦後の大量のベビーブーマーが65歳以上の高齢者になりつつあることがある。こうした団塊の世代が「終活」や「エンディングノート」に関心を寄せてきた。
関心が高いことを証明したのが、2013年、「終活」をテーマとする季刊誌『ソナエ』(産経新聞社)を刊行、創刊号は約5万部を売り上げたこと。「ペットの葬儀」や「おひとりさまの終活」を特集した第2号は創刊号を上回る勢い。
多くのデータが示すように、「関心がある」が3割程度はあるが、「実際に準備している」のは5%未満、という壁ははたして破られるのだろうか?
「終活」という用語が登場した2009(平成11)年から産経新聞社が季刊誌『ソナエ』を創刊した2013年にかけた変化を記したもので今でも有効であろう。
2011年(東日本大震災発生の年!)に民間では本田桂子さん、中澤まゆみさんが「終活」を題した書籍を出版し、経産省が「ライフエンディング・ステージ」に関する報告書を発表、これが大きな影響を与えた。
2012年に「終活」がユーキャン新語・流行語のトップテン入り。
そして2013年創刊したのが、俗に言う「終活雑誌」である『ソナエ』、これが現在まで続く「終活ブーム」を牽引した。
ライフエンディング産業
「供養業界」という言葉を業界に普及させた鎌倉新書がいま「ライフ・エンディング」サービス事業というようになったのは経産省報告書「ライフエンディング・ステージ」研究会報告書が大きく影響しているように思う。
終末期医療・介護のその後のステージ(段階)のサービスのありようをトータルに課題として提起したのが経産省報告書であった。
そのちょっと洒落た表現で、かつ公が最初に問題提起したという客観性が「ライフエンディング」あるいは「エンディング」という用語が支持される背景にあるのだろう。
「供養業界」という言葉は、日本ではあくまで事業分野として分離している葬儀業界、墓石霊園業界、仏壇・仏具業界を総称するという以上の意味をもちえない業界の総称である。
「終活」は単身世帯の増加、ひとり死の増加、核家族の非継承性という社会構造の変化を受けて、自らの終末期、死後について予め準備活動を行う必要性を訴えるもの。
そこから発展し「家族の終活」も含む。
それ以前の「エンディングノート」ブームを背景にし、包摂するものとしてあった。
「就活」をもじった「週刊朝日」の造語「終活」は瞬く間に市民権を確立した。
まさに塊である団塊世代が65歳定年、前期高齢者入り、そして70歳へという動きの中で雑誌読者の高年齢化を背景にマスコミはこぞって「終活」を取り上げ、また売れることによって狂騒の最中にある。
格差社会の拡がりは、かつては「相対的富裕」といわれた高齢者にまで及び、貧困で社会的サポートを受けにくい高齢者が増大し、さまざまな社会問題を提起するに至っている。
ライフエンディングサービスの収益性
かつて「葬儀の生前契約」が、事業者にとっては富裕高齢者の事前囲い込みを企図したものの、実際のニーズは貧困高齢層において高かったように、「終活」事業は関心の高さ、広さと比例せず、高齢者の問題を抱える層に、しかも多くは事後に問題を発生させており、事業を企図した人たちの期待は裏切られつつある。
要は「儲かる事業」ではない。
経産省報告書が提起した問題とは、超高齢社会にあって進む個人化の中で、公的にも適正なサポートを得られない高齢者のライフエンディング・ステージが抱える課題を民間においてどのように支援するサービスを確立していけるかは近々(キンキン:差し迫った未来)の喫緊(キッキン:重要)な問題としてある。
しかし現在それに関係する業界は問題意識が乏しく、情報提供能力も低いのが実情。どうやってそうした事業分野のサービスを立ち上げ、あるいは連携し、確立していくべきか、を問うものであった。
富裕層を対象として事業展開している信託銀行は、社会的ニーズがあるとしてもそこに進出することで収益性を悪化させる、と最初から自らの顧客以外に係わることに対しては否定的であった。
おそらく「事業者としての計算」としてはそれが正しいのであろう。
係わった、係ろうとした事業者の姿勢としては大きく3つあったと思う。
第1は、社会的関心が高いから本等による情報提供、セミナーということで収益を求めようとするもの。
第2は、サポート資材の必要性が高まることが見込まれるので、サポート資材を開発して販売し収益を求めようとするもの。これには大手警備会社を筆頭にさまざまな取り組みがある。
第3は、直接手がけると危険なので、ネットを介した紹介事業等による手数料で収益を求めようとするもの。ネット系葬儀・墓石・霊園等の斡旋事業者がこれに当たる。
皆、傷つくことを怖れ、周辺で収益を求めようとしている。
まともに社会的ニーズに応えようとする事業者、あるいは事業者間の連携の仕組みはまだできていない。
だから特定非営利法人りすシステム等のNPOの活動は貴重である。
言葉だけはやたら賑やかしいが、現実は前にほとんど進んでいない。
民間に知恵なく、公に問題意識がない
公の取り組みが弱いからといって、こうした福祉的要素を抱えた事業を民間任せにすること自体に無理がある。
国―自治体―民間がうまく連携して社会的ニーズに応える仕組みを模索する必要があるだろう。
これからはかつての福祉がそうであったように、上から下の保護というだけではなく、サービスの受益者の意思を尊重し、うまく生かす水平の形でないと多様な状況に対応したサービスを提供することは不可能だろう。
そして常に第三者の適正なチェックを入れていく必要がある。
社会的ニーズが高い保護的サービスは、一方ではサービス従事者に過重な負担を負わせがちであり、他方で腐敗の温床になりがちであるからだ。
経産省が「ライフエンディング・ステージ」についての報告書を出したこと自体画期的なことであった。報告書発表は少なくとも民間に問題の所在を明らかにし、「終活ブーム」を引き起こす要因の一つとなった。
しかし経産省全体の問題意識ではなく、担当室長と数人のスタッフ、ほんの一部の外部協力者の熱意によって作成されたものだったため、次の担当者はこれを放置して現在に至っているのは極めて残念である。