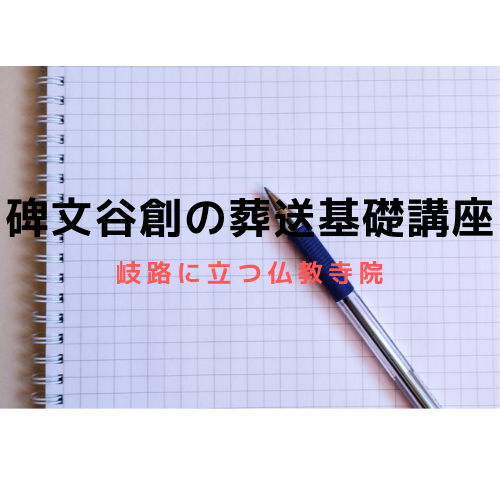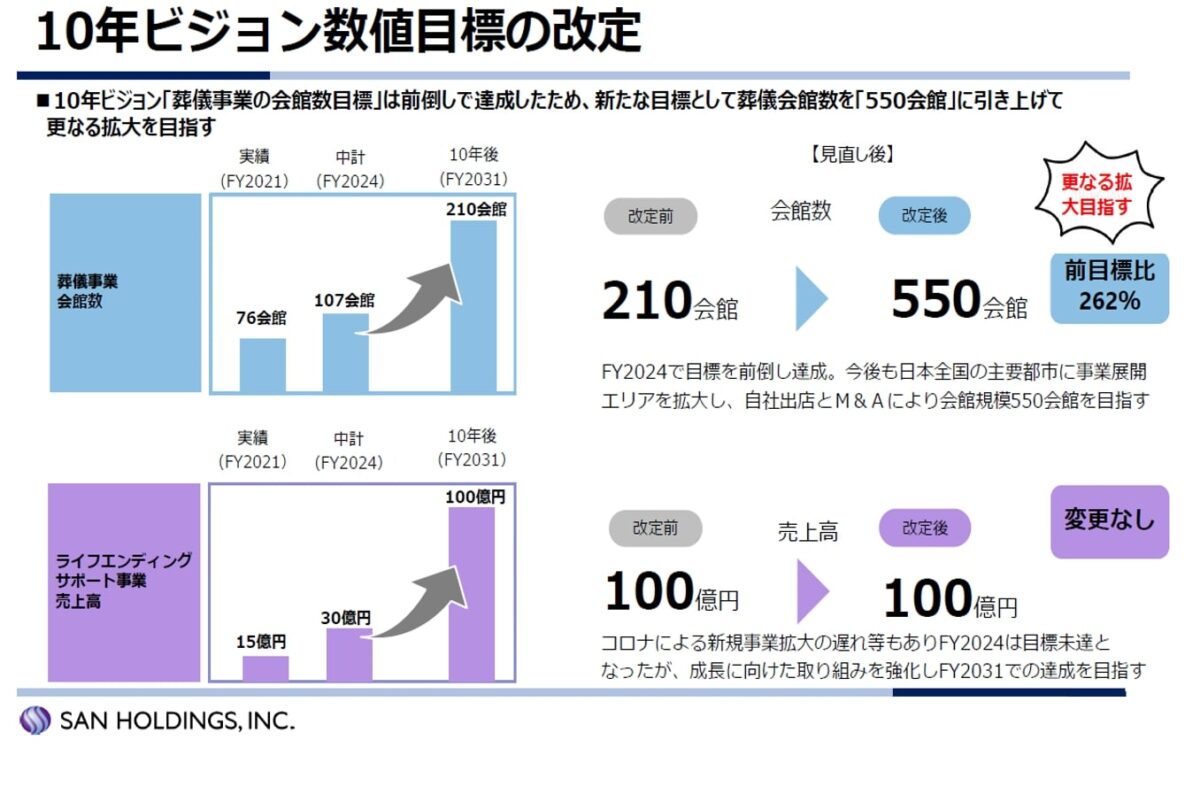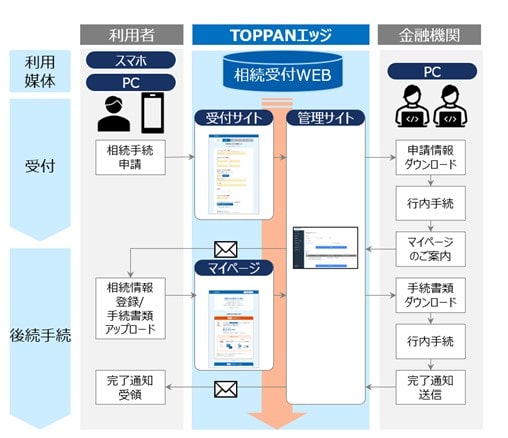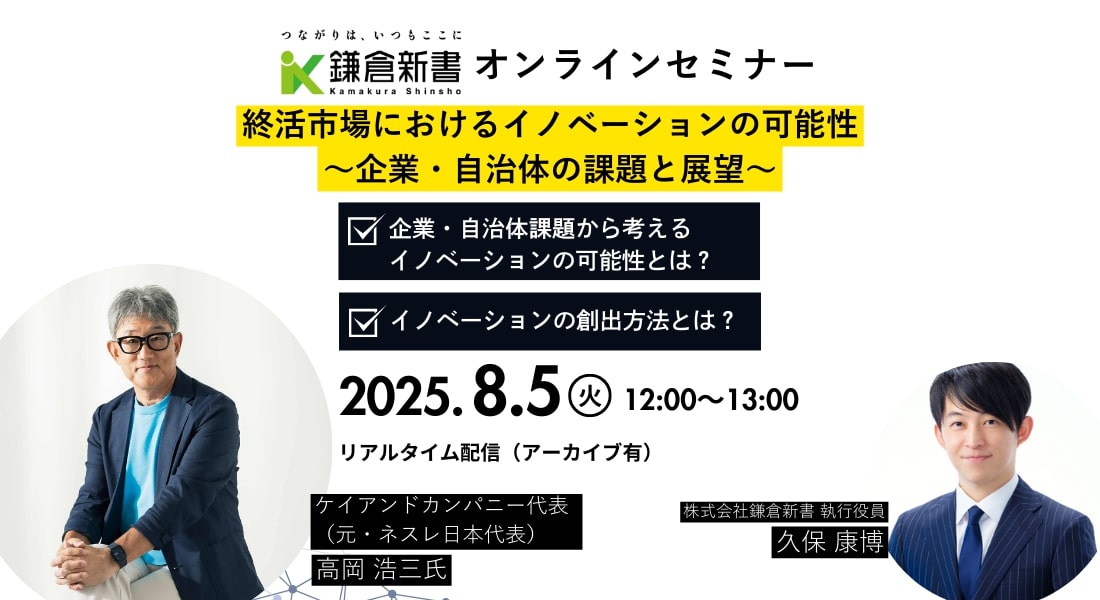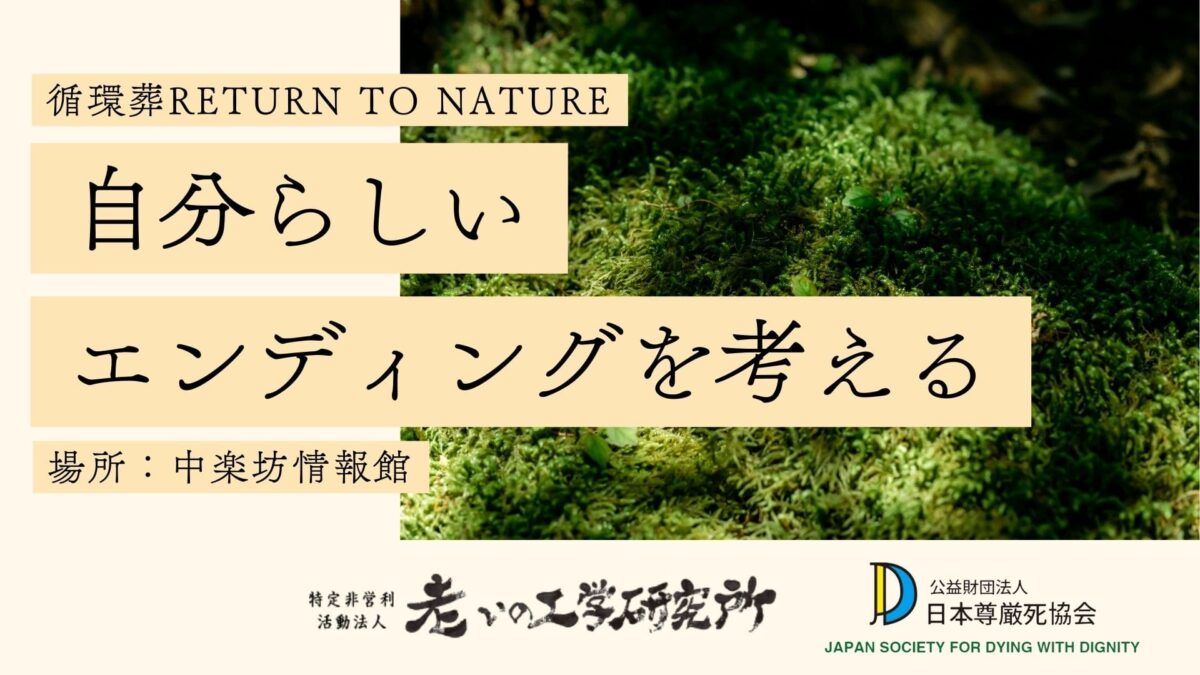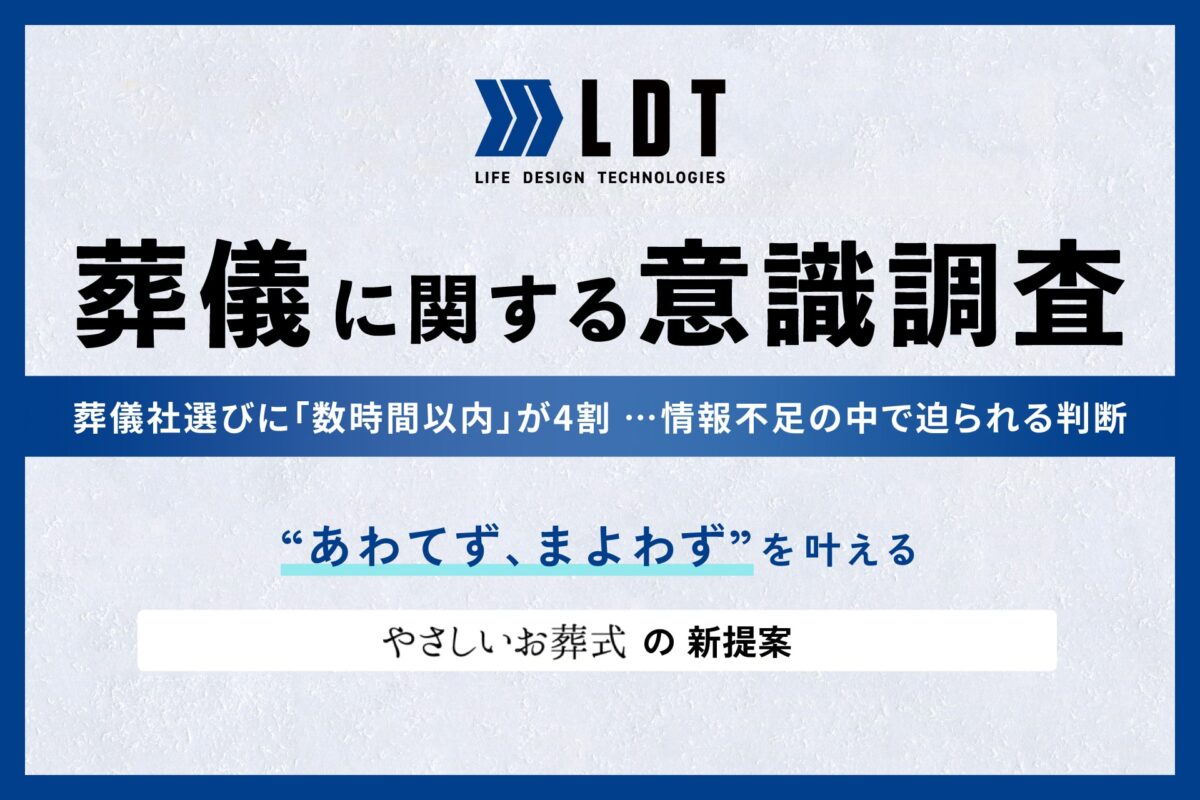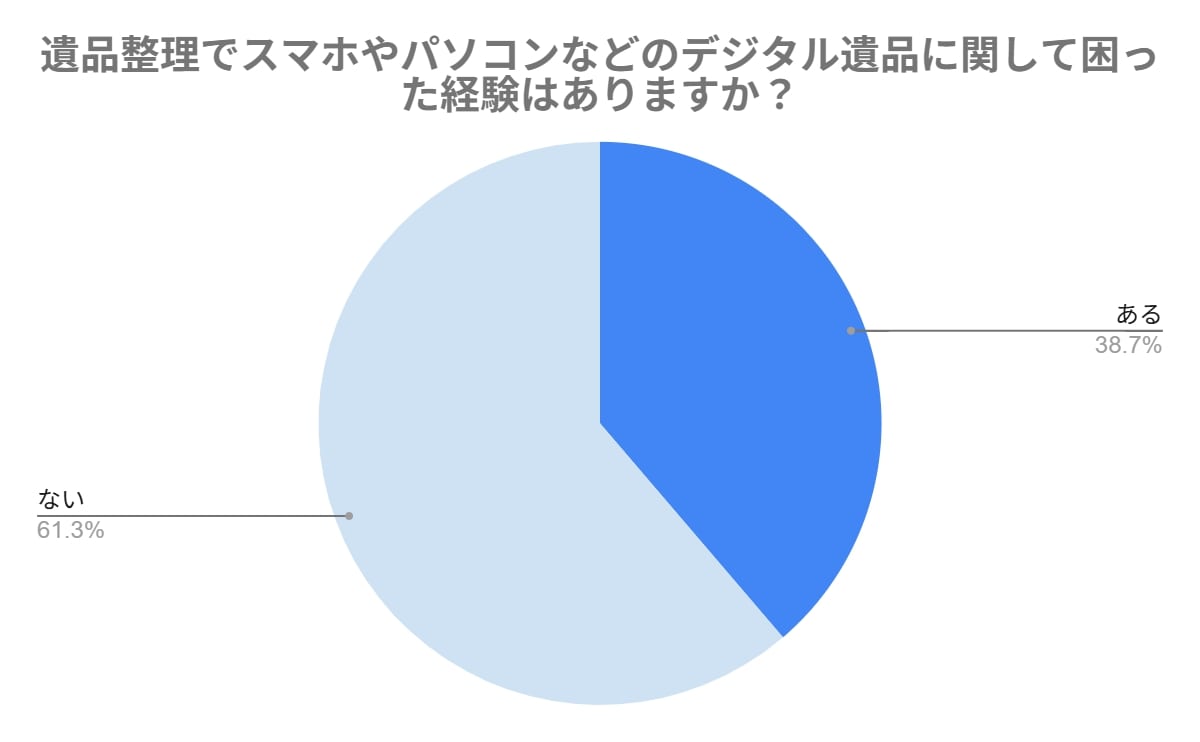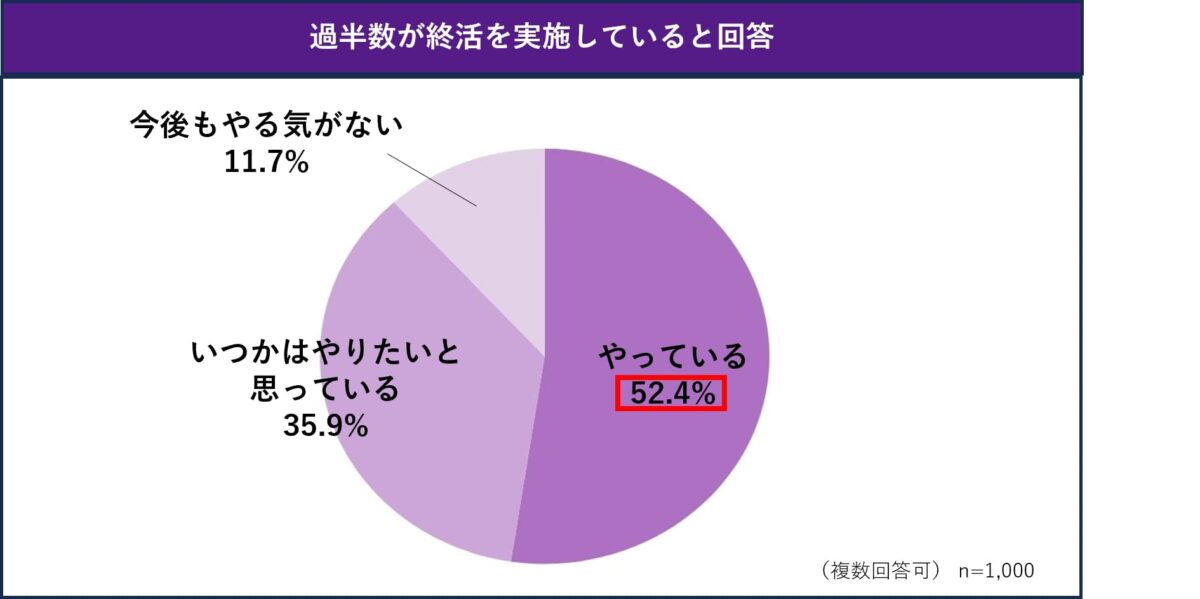直葬における炉前の読経
15年前くらいになるだろうか。ある仏教教団の研究会に顔を出したとき、仏教民族学の指導的研究者が私に話しかけてきた。
私が2000年頃から「直葬」問題を提起していたことを知ってのことであった。
「直葬では火葬炉前で読経をするのかね。それとも何もしないで火葬するのかね」
―頼まれ僧侶が炉前で読経することも多いようですよ。
「そうか、安心した。やはり日本人はお経を必要とするんだよね」
―先生それは少し違うと思います。檀那寺とか知った僧侶が読経するのではないですよ。まったく見ず知らずの僧侶で、遺族は本来読経を必要としていなくて、何もしないと後から親戚等から非難されることを危惧して、弁解できるように読経を頼んだというケースも多いのではないでしょうか。むしろ「読経が今でも必要とされている」のではなく、「読経を必要としない葬儀の始まり」ではないでしょうか。
「直葬」を「火葬式」と呼び換える葬祭事業者が多くなっている。
「死体処理ではなく葬式です」という言い訳を与えているようにしか見えないのは私がへそ曲がりなせいだろうか。
私はそこに「葬式である建前を守ろう」とする葬祭事業者の理念よりも、「僧侶手配の手数料稼ぎ」の本音を見てしまうのだ。
これは今流行のネット系葬儀斡旋事業者にも共通する。
仏教僧の葬送への係わりの端緒
仏教僧が葬式へ係わりだしたのは飛鳥時代の聖徳太子の葬式が最初といわれる。
奈良時代から聖(ひじり)とよばれた下級、半官半民の僧侶が放置された民衆の遺骸を集め、火葬して塚に埋めたという記録はある。
だが、民衆の死に際し、その葬送に本格的に係わるようになったのは中世末期、近世直前の戦国時代のことであった。
この仏教の葬送への係わりは生活仏教としての日本仏教にとって革命的なことであった。
今では「葬式仏教」「建前(教理仏教)と本音(生活仏教)の乖離」などと揶揄されることが多いが、「葬祭仏教」化しなければ仏教が日本民衆に受け入れられることはなかっただろう。
しかし「葬祭」が僧侶の「生業」となることによって堕落したことも事実である。
また檀信徒や信者の葬送に深く関与することで、とかく観念的になりがちな信仰のあり方を突き詰めた寺、僧侶もいる。
僧侶手配、派遣僧侶の問題を論ずる前に、歴史的に寺、僧侶と葬送の問題を私なりに概観しておく。